東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近「民事信託」「家族信託」のことをよく聞かれます。
マスコミや雑誌などで「家族信託」とか話題になっているので、あなたも耳にしたことがあるかもしれません。
今回は「民事信託」について書いていきます。

「信託」って何?
信託とは、自分の財産のこれからの管理の方法や承継の方法についての約束事を信託法という法律に基づいて決めておくことです。
信託には、大きく分けて「商事信託」と「民事信託」にわかれます。
「商事信託」とは、信託銀行や信託会社などに手数料を払って管理してもらう信託をいいます。
今回紹介する「民事信託」は、商事信託以外の、信頼する人に管理をしてもらう信託をいいます。
「家族信託」とか呼ばれているものです。
民事信託にするメリットとはなにか?
自分の持っている「特定できるプラス財産」をまず信託財産とします。
信託財産とすることで、財産の名義人と権利を持つ人となります。
信託をすると、名義が変わってしまうので自分の物ではなくなるという心配をする人がいます。
信託財産は、信託をすると、受託者名義になり、受託者が管理することになります。
ただ、信託財産の利益を受けるのは、受益者となるので、実質的には財産は「受益者のもの」となります。
民事信託の場合、一般的には、信託当初は「委託者=受益者」が多いので、財産が自分のものでなくなるということはありません。
ただ、「信託財産」となると、名義は受託者となりますが、受託者個人の財産ではありません。
なので、受託者は自分の財産と分別して管理しなければなりません。
民事信託の3要素 委託者・受益者・受託者とは何?
「委託者」とは、もともと財産を持っている立場で、自分の決めた特定の財産について信託をする立場の者です。
「受益者」とは、信託財産について、受益権(利益を得る人)を持っている立場の者。一般的には当初の委託者が受益者にもなります。
「受託者」とは、信託財産の名義人となり信託の目的を達成するために必要な義務を負う役割の者をいいます。
「信託」の手続をすると、これまで「所有者」が全て行っていた役割を、「委託者」「受託者」「受益者」という立場に分かれて行います。
役割を分けることで「信託財産」をいう、新たな独立した財産の集合体が誕生します。
3つの役割がありますが、同じ人が兼ねることもできます。
民事信託はどんな場面で活用されるのか?
「民事信託」を活用する場面で一番多いのは、「認知症対策」の場合です。
認知症となってしまうと、被後見人の口座は凍結され、後見人の管理下に置かれてしまいます。
そのようになってしまうと、被後見人の意思通りにならないことがあります。
そのため、認知症になる前に「信託」しておくことで、名義と権利を分けることができ、万が一のときにも、被後見人の意思で財産を使うことができます。
ただ、最近気になっているのは、成年後見制度がデメリットが多いから、事前に「民事信託」契約しておくことをすすめるビジネスが多いこと。
私は「民事信託」と成年後見制度は両立できるものと思っています。
なので、どうしても「信託財産」にしておくものは民事信託を活用し、身上監護などは成年後見制度を活用するなどするのがいいでしょう。
さらに、民事信託とともに、認知症対策の一環として「任意後見制度」の活用もありです。
もうひとつ活用できる場面として「事業承継」があります。
相続や贈与で株式が分散することを防ぐことができ、現在注目されています。
経営者の高齢化が深刻な問題となっており、株式をどう渡すのかを「信託」で解決する方法があります。
民事信託の最近の問題点
ここからは私見となりますのでご承知起きください。
どうも、最近の民事信託は認知症前の問題の側面しか捉えていないように感じます。
民事信託をビジネスにするのはありですが、後見制度の代替手段というイメージが浸透し過ぎのように感じます。
民事信託でしかできないこと、後見制度でしかできないこと、きちんと分けて考える必要があります。
最近では、司法書士の説明義務不足や遺留分と民事信託の問題も出てきています。
ただ、楽だから契約するというのではなく、お互い納得してやらないと、登記ができなかったとか、口座ができなかった、信託財産を組成できなかったなどトラブルが出てくると思われます。
あと、信託契約は元気なときにしかできません。
そのことも考慮して、早めに対策をする必要があります。
「民事信託」は一種の予防法務のように感じます。
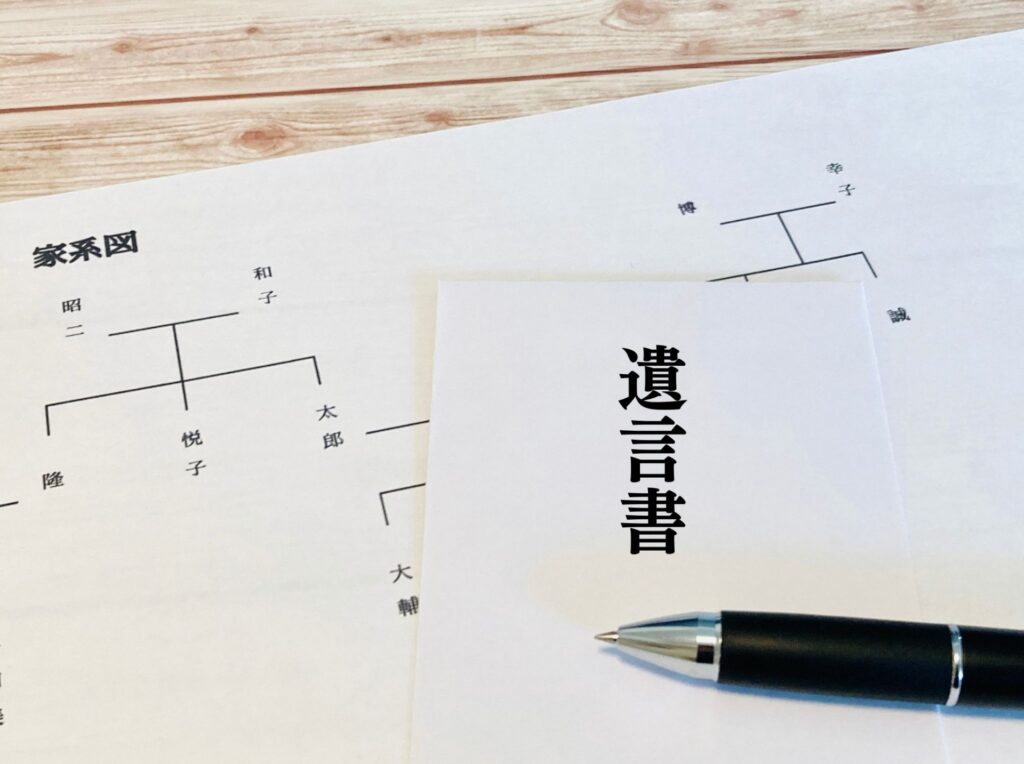
まとめ
最近は一般の方でも「民事信託」を知る機会が増えてきました。
簡単そうで実は難しい側面もあるので、専門家に相談されることをお薦めします。
今回は
『「民事信託」「家族信託」って何?民事信託にすると何がメリットなのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
最近のブログはこちら



