東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、事務所に多くの方から民事信託についての問い合わせをいただくようになりました。
民事信託は、家族の財産を守り、未来を安心させる法律の仕組みです。
特に、親がいない子どものための安全な財産管理や、認知症の懸念を持つ高齢者の方々にとって、民事信託は大きな安心を提供できる方法です。
今回は、民事信託の基本とその活用事例をわかりやすくご紹介します。
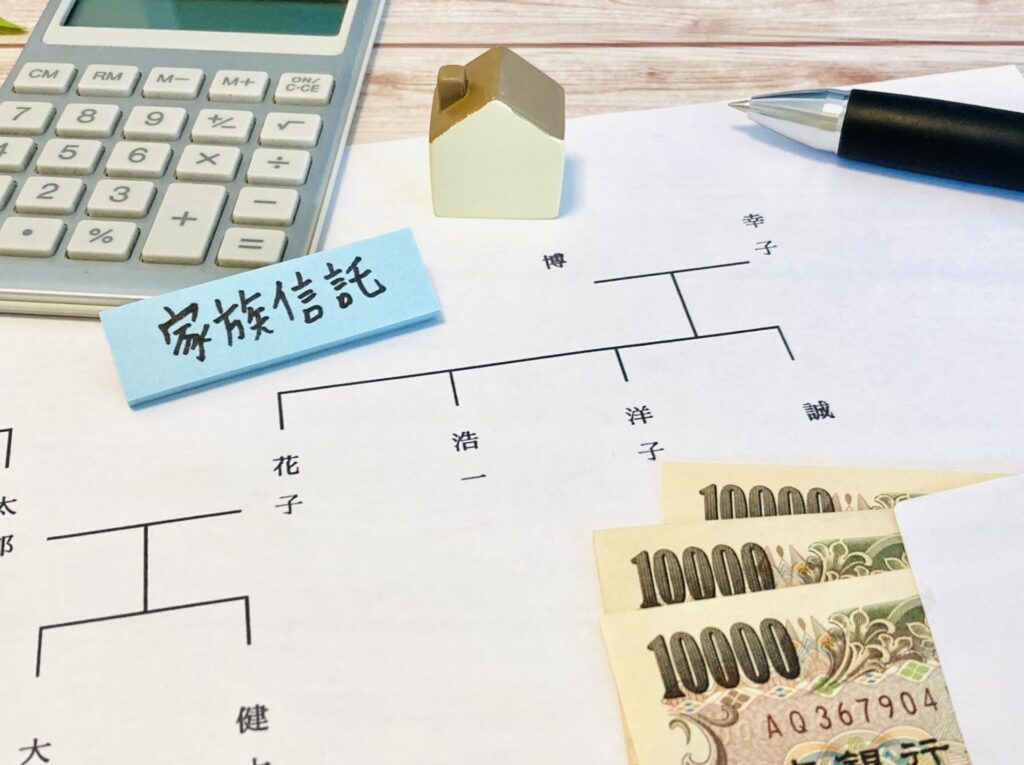
そもそも民事信託(家族信託)って何?
自分で築いた財産は自分のために使いたいもしくは後世はこのために使ってほしいという願いは多いでしょう。
そのためにあるのが「民事信託」です。
委任者(自分)が家族もしくは信頼できる人(受託者)に財産を託し、託された財産から発生した利益を受ける(受益者)のために契約をするのが「民事信託」です。
つまり、受託者の利益のために行うのではなく、委託者が意図してきたことを受益者に行わせるために財産を管理するのが民事信託です。
なので、受託者は利益は発生せず、家族間で行わるので「家族信託」と言われることがあります。
信託銀行の場合は、受託者に財産管理料として一定の金額を支払いますが、民事信託にはそれがありません。
民事信託の主な特徴
民事信託の主な特徴を紹介します
1 民法上の所有者は受託者
信託の設定により、民法上、信託財産の所有権(名義)は委託者から受託者に移ります。
2 税務上の所有者は受益者
税務上は、受益者が信託財産に属する資産・負債を有しているものとみなして、信託財産に係る収益・費用は受益者に帰属します
3 信託財産は、委託者や受託者の財産とは分別して管理される
信託財産は、委託者や受託者の固有財産とは分別して管理することが求められています。
これを分別管理義務といいます。
4 信託財産を管理・処分等した結果得られた財産も信託財産となる
信託行為において信託財産と定めた財産の他、信託財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由によって受託者が得たものも信託財産となります。
5 民事信託は商事信託より柔軟な設計・運用が可能
その裏返しに契約内容をしっかり作り込
民事信託の活用事例: 後見制度との併用
先程、活用事例として
高齢で将来の財産管理に不安のある人が、今後の財産管理にかかる負担を軽減したい場合
を紹介しました。
認知症が進行すると、本人の財産管理が困難になり、後見制度を利用するケースがあります。
しかし、後見制度だけでは本人の意向が十分に反映されないことがあります。
そこで、元気なうちに民事信託契約を結ぶことで、もし認知症になっても、受託者が委託者の意向に基づいて財産を利用できるようになります。
後見制度と民事信託を併用することで、より安心して財産の管理を任せることができます。
民事信託の契約と意思表示
民事信託は契約に基づく仕組みなので、委託者が意思表示できない場合、民事信託の契約はできません。
認知症の進行などで意思表示が困難になった場合は、民事信託ではなく後見制度を利用することが推奨されます。
ただし、意思表示が可能なうちに民事信託を検討し、適切な契約を結ぶことで、未来のトラブルを回遍することが可能です。

まとめ
このように、民事信託は家族の未来を守りながら、財産を適切に管理する法律の仕組みです。
是非、この機会に民事信託のメリットを理解し、家族の安心と未来を守るための準備を始めてください。
今回は
『民事信託の基本と家族の未来を守る方法を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
最近の相続に関するブログはこちら
参考書籍
| 増補版 相続・事業承継・認知症対策のための いちばんわかりやすい家族信託のはなし | ||||
|




