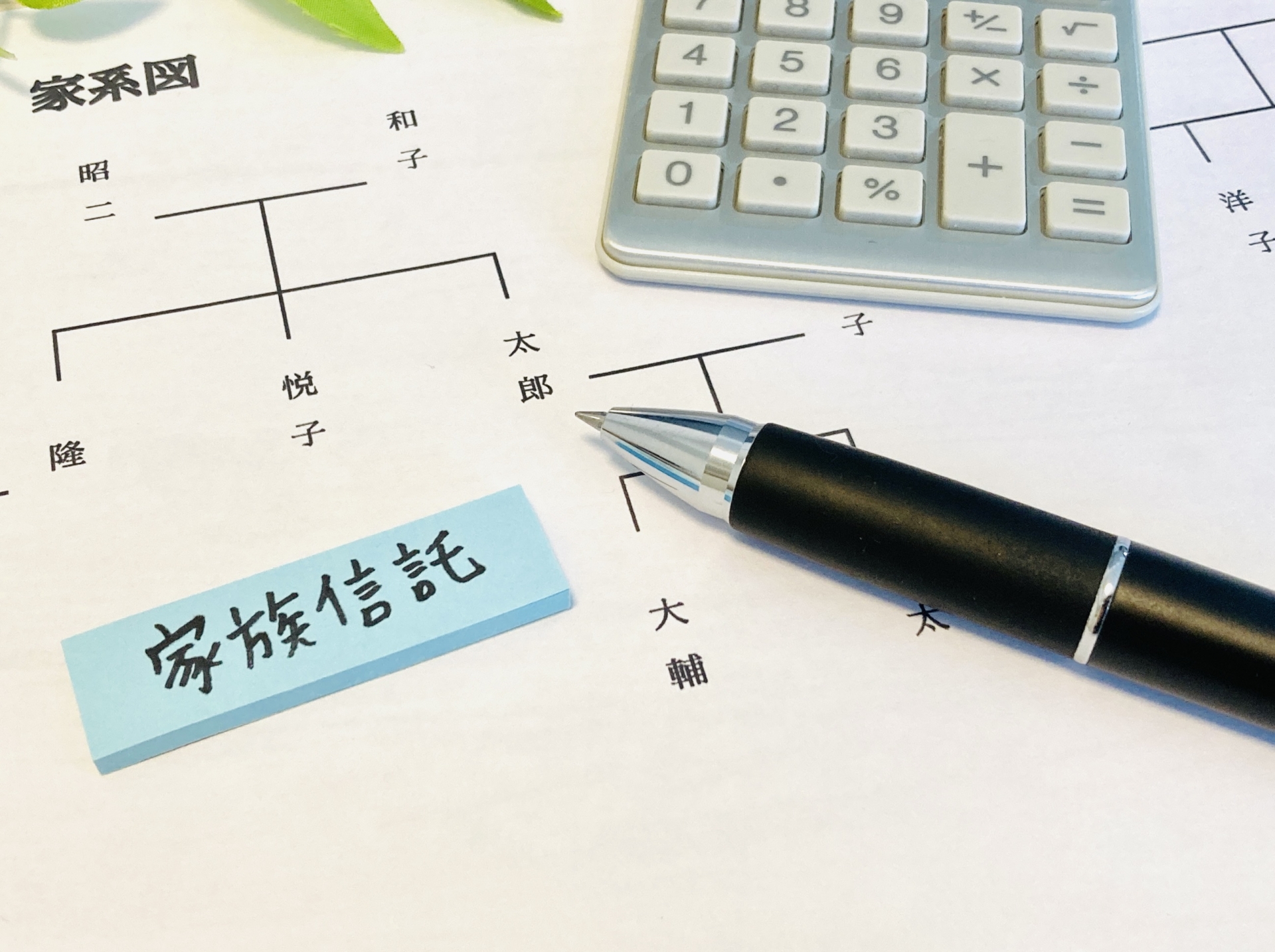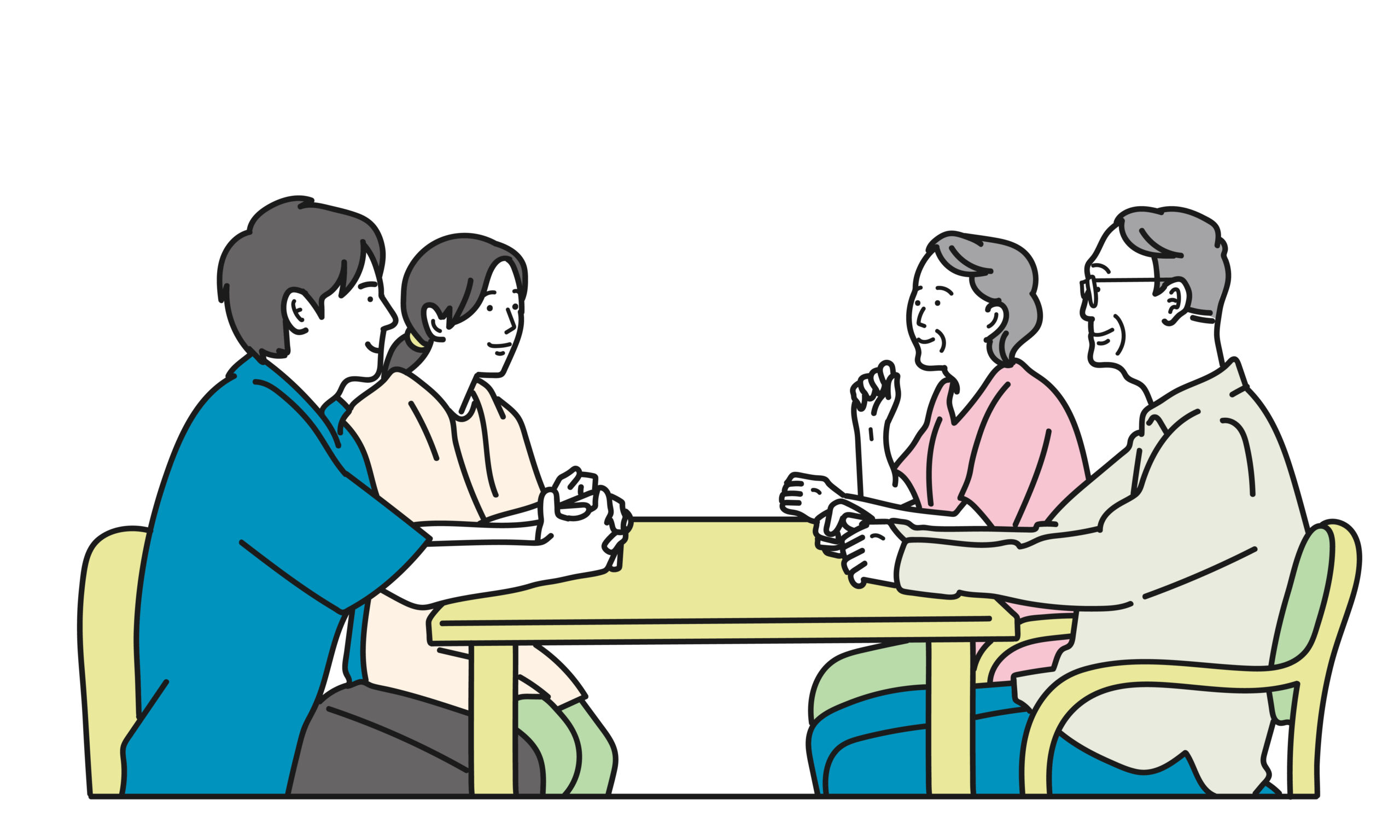東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
皆さんは、人生の大切な瞬間に、家族や大切な人たちとの絆を感じることはありませんか?
会社の設立、相続の瞬間など、私たちの生活の中で大切な節目に立ち会う時、そんな絆を感じることが多いと思います。
今回は、特に「相続」と「家族信託(民事信託)」に焦点を当てて、その魅力や役割をご紹介します。
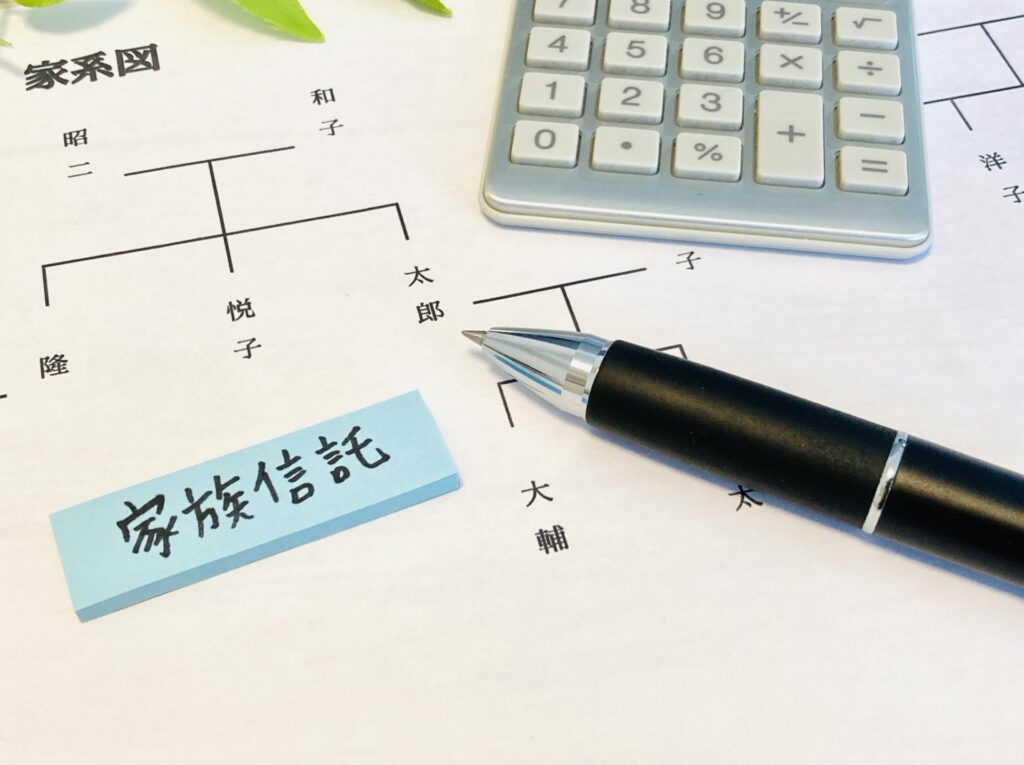
相続の概要
「相続」とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産がどのように分けられるかを決める法的な手続きのことを指します
相続は誰もが避けて通れない、密接に関わるものであります。
後日紛争などを避けるため、また、円滑に進めるためには、遺言や適切な手続きが不可欠です。
民事信託(家族信託)とは
最近、「民事信託(家族信託)」という言葉を聞いたことがある方が多いでしょう。
このブログでは表記を基本「民事信託」と統一して書いていきます。
民事信託は、委託者の財産について、目的を定めて所有権等の権利を受託者に移転し、管理・処分その他の行為を任せる手法です。
基本は受託者は委託者の親族などがなり、専門家は信託契約書の作成などでサポートしています。
民事信託が注目されるようになったのは、信託契約などの定めにより、柔軟に受託者の財産管理の方法や死後の財産の承継について定めることができるところです。
よく比較される成年後見制度では実現の難しい積極的な資産活用を図ることもできたり、事業承継のために株式を信託したり、いま注目されているのが「民事信託」です。
民事信託のメリットとは
まずは、財産の保護についてです。
病気や事故で判断能力を失っても、信託契約を結んでおけば、信託に基づき適切に財産が管理されます。
次に、相続のトラブル防止が挙げられます。
事前に信託を設定することで、相続時の家族間のトラブルを避けることが可能です。
最近話題となっているのが「遺言代用信託」です。
遺言では、遺言者の死後に財産を承継する者を定めることはできますが、財産を承継した相続人又は受遺者に対して、財産の利用方法等を指定することは難しいです。
遺言によって財産を承継させることができるのは一代限りで、複数世代にわたる承継を遺言で指定する、いわゆる「後継ぎ型の遺贈」はできないといわれています。
民事信託の場合だと、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を用いることで、複数世代にわたる受益者を指定し、かつ、委託者の死後の財産の管理方法についても指定できます。
遺言でカバーできないところを民事信託でカバーすることは可能ですが、遺留分の排除を民事信託でできるかについては争いがあり、実務では否定する方が多いようです。
最後に、柔軟な財産管理ができます。
例えば、子供が成人するまでの教育費用を指定したような形で使わせる、といった具体的な条件を設定することができます。
民事信託の設定方法
まずは目的の明確化。
何のために信託を設定するのか、その目的を明確にします。
次に信託の内容を決定します。
どのような財産を、どのような条件で、誰に渡すのかを決定します。
民事信託を他の代用手段と考えることも大事ですが、なぜ利用するのか、他の制度と比較して検討することが重要です。
民事信託の注意点はあるのか?
家族信託は非常に便利な制度ですが、設定や運用には専門的な知識が必要です。
また、信託の設定や解除には費用がかかる場合がありますので、しっかりとした計画や相談が必要です。
なので、専門家の関与が必要なのが民事信託の特徴です。

まとめ
今回は相続を書いた後、民事信託のことに触れてみました。
民事信託は、私たちの財産を次世代に確実に継承するための重要なツールです。
しっかりと計画を立てることで、家族の未来を守る手助けをすることができます。
もし民事信託に興味を持たれたら、専門家との相談を検討してみてください。
今回は
『家族の絆を法的にサポート!相続の基本と、注目の民事信託とは?江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください。