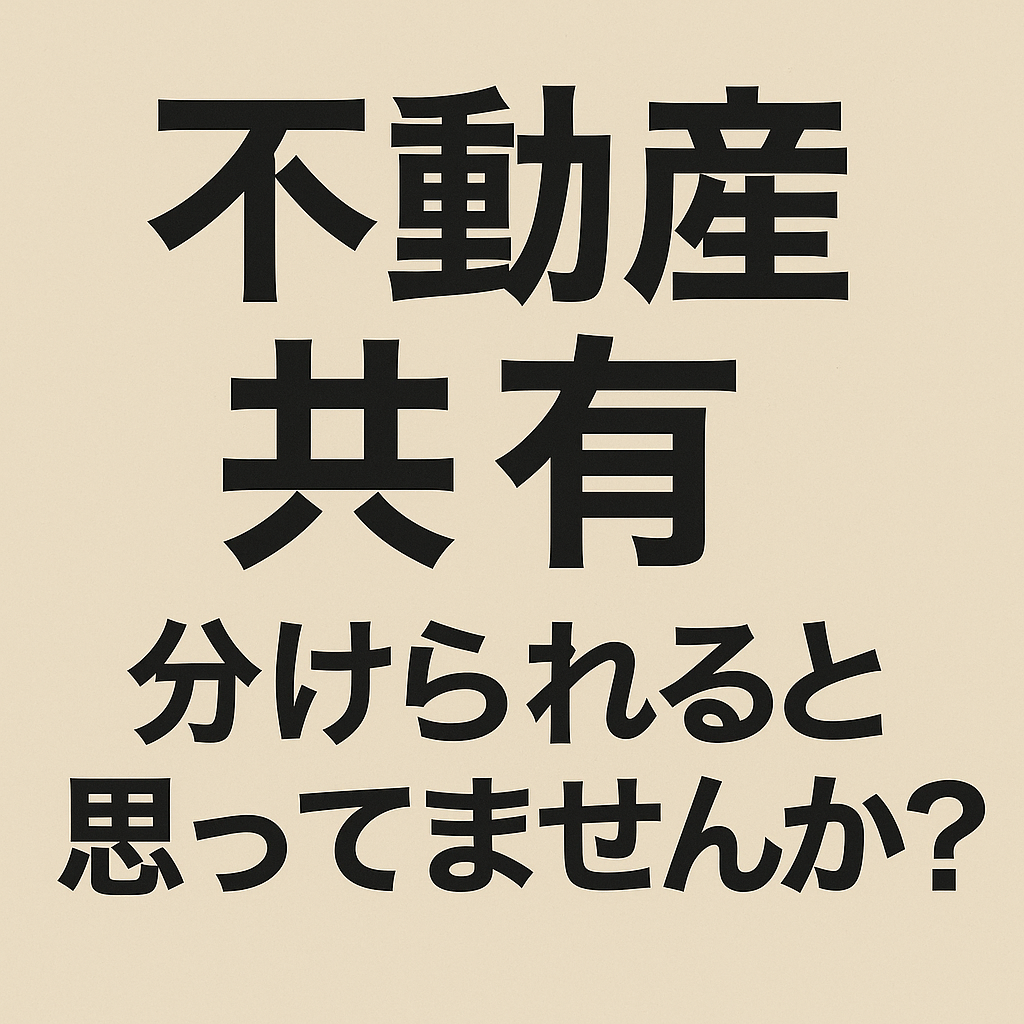こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに:「共有」ってどういうこと?
相続や離婚、資産購入の場面でよく出てくる言葉に「共有名義」があります。
「共有」と聞くと、「不動産をきれいに分け合える」と思っている方が多いのですが、民法上の“共有”はそんなにシンプルな話ではありません。
むしろ、不動産を共有にしてしまうことで、あとあと思わぬトラブルや手続きの複雑さを生むケースもあります。
この記事では、司法書士の立場から、初心者の方にもわかるように「不動産の共有とは何か?」を丁寧に解説します。
共有=持分を分けている状態です
不動産の「共有」とは、簡単に言えば、1つの不動産を複数人で所有している状態です。
それぞれが所有しているのは、建物や土地そのものではなく、「持分(もちぶん)」です。
たとえば、父親が亡くなり、子ども2人で不動産を相続した場合、登記簿上にはこう表示されます:
つまり、家全体を半分こしているのではなく、「権利の割合」を持っているだけです。
リビングを長男、キッチンを次男、というように「場所」で分けているわけではありません。
「持分」では使い方を自由に決められない
ここが大事なポイントです。
不動産が共有になっていると、持分を持っているだけでは自由に使えないことが多いのです。
たとえば…
-
家を売却したい → 共有者全員の同意が必要
-
家をリフォームしたい → 多くの場合、共有者の同意が必要
-
賃貸に出したい → 単独ではできないことが多い
つまり、共有=自由に使えるわけではなく、お互いの合意が前提になるのです。
よくある誤解:「持分があれば、自分の部屋を自由に使える」
特に相続後によくあるのがこの誤解です。
「親の家を兄弟2人で相続したから、自分の持分は自分の部屋に相当する」と思ってしまうケース。
実際には、家全体を一緒に所有している状態であり、物理的に分けているわけではありません。
ですので、「この部屋は俺のものだから勝手に貸すね」ということは、できないのです。
相続後に共有にするとどうなるか?
相続の場面では、話し合いがまとまらない場合に、とりあえず「共有名義」にして登記してしまうことがあります。
しかしこれは、後々に大きな火種となることがあります。
たとえば:
-
相続人の1人が死亡し、共有者が増える
-
不動産の売却時に全員の同意が取れず、売れない
-
持分を第三者に売却され、知らない人が共有者になることも…
共有は「相続を後回しにした結果」として発生することも多く、争続(そうぞく)=争いが起きる相続の原因になりがちです。
解決策①:共有状態を解消する方法
共有状態を続けることにはリスクがあるため、できるだけ早い段階で共有を解消することを検討しましょう。
方法としては:
-
他の共有者から持分を買い取って単独所有にする
-
家を売却し、現金で分け合う
-
揉めそうなときは調停・審判で解決する
いずれにせよ、放置しても解決しません。
解決策②:生前の備えとして遺言書・家族信託
もしこれを読んでいる方がまだご自身の不動産の所有者であれば、将来の相続で共有トラブルを防ぐために遺言書や家族信託の活用もおすすめです。
-
「自宅は長男に相続させる」と遺言書に書いておく
-
高齢の親が判断能力のあるうちに信託契約を結ぶ
など、あらかじめ分け方を決めておくことで、将来の混乱を回避できます。
まとめ:共有は便利ではなく、むしろ不便な制度です
不動産の「共有」は、民法上の制度であっても、現実の生活では不自由が多いものです。
感覚的に「分けた」つもりでも、実際には「話し合いが必要な共同所有」なのです。
江戸川区や船堀エリアで不動産の共有相続についてお悩みの方は、相続の実務に強い司法書士へぜひご相談ください。
電子書籍でさらに詳しく学ぶ:がんばらない相続手続き
相続で悩んでいる場合は、電子書籍『がんばらない相続手続き:効率よく進める3つの方法』をお読みください。
基礎的な相続手続きについて詳しく解説しています。
今すぐ手続きを始めて、安心した未来を手に入れましょう!