東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
あなたは「任意後見制度」というものを聞いたことがあるでしょうか?
任意後見制度は、あなたと大切な人の未来を守る手段。
人生には予測できない出来事がついて回ります。
高齢になったり、突然の疾病や事故に見舞われたりすることがあります。
そのような状況下では、財産や医療に関する意思決定が難しくなることがあります。
こうした場合、任意後見制度はあなたと大切な人の未来を守るための重要な手段となります。
今回は、任意後見制度について詳しく解説し、その重要性について考えてみましょう。

任意後見制度を利用する
任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。
法定後見制度の場合、判断能力が不十分になったときに家庭裁判所に申立てをして行う制度で、後見人は家庭裁判所で選任された人になります。
任意後見制度を利用すると、自分の信頼できる人を後見人とすることができるのが大きな魅力です。
任意後見契約を結ぶにはどうするか?
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
なので、公証役場にいって当事者間同士で契約をすることになります。
任意後見制度の特徴
任意後見制度には以下の特徴があります。
まずは、自由な選択ができるところ。
任意後見制度では、後見人を自分で選ぶことができます。信頼できる家族、友人、または専門家(司法書士、行政書士など)を選び、自分の希望に合わせて後見人を指定できます。
これにより、あなたの生活や財産について、あなた自身が納得いく形で計画を立てることができます。
次に、柔軟性が挙げられます。
後見人には、財産管理、医療の意思決定、日常生活のサポートなど、多くの役割を委任することができます。また、必要に応じて複数の後見人を指定することも可能です。これにより、個別のニーズに合わせたケアプランを柔軟に立てることができます。
最後に、財産保護があります。
後見人は被後見人の財産を管理し、不正な取引や損失を防ぎます。
これにより、被後見人の経済的な安定が保たれ、財産の保護が行われます。
この点が、高齢者や障害を抱えた方々、あるいは自己判断が難しい状況にある人々にとって非常に重要です。
任意後見人はいつから仕事が始まるのか?
任意後見契約は、委任者本人の判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ締結されるものですから、任意後見人の仕事は、委任者がそういう状態になってから、始まることになります。
具体的には、任意後見受任者や親族等が、家庭裁判所に対し、委任者本人の判断能力が低下して任意後見事務を開始する必要が生じたので「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任すると、その時から任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
任意後見監督人の仕事は?
任意後見監督人は、任意後見人から定期的にその事務処理の状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。
家庭裁判所がその選任した任意後見監督人を通じて任意後見人の事務処理を監督することで、万が一、任意後見人による代理権の濫用(使い込み等)があっても、これを防止することができる仕組みになっています。
判断能力があるもののあらかじめ財産管理をお願いできるのか?
任意後見契約は、委任者本人の判断能力が低下した場合に備える契約で、本人の判断能力が不十分となったことを前提として、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生ずるものなので、基本は対応できません。
しかし、多くの場合、任意後見契約と同時に「(財産管理等)委任契約」を締結することにより、対処することになります。
実務で多いのは、「(財産管理等)委任契約」を「任意後見契約」と組み合わせて同時に締結することが多いです。
このような契約形態を「移行型」と呼んでおります。こ
れは委任者の判断能力があるうちは委任契約によって対処します。
その後、委任者の判断能力が低下し、裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力が発生した場合は、委任契約の効力を失効させ、委任契約から任意後見契約に移行します。
そこで「移行型」と呼ばれているのですが、本人の判断能力が低下しない間は、委任契約のみで対処することになります。
なので、多くの任意後見制度を活用する場合には、「移行型」と呼ばれる形になっています。
任意後見契約は自由度が高いが…
任意後見契約は「契約」ですから、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り、自由にその内容を決めることができます。
誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどのような代理権を与え、どこまでの仕事をしてもらうかは、委任者本人と任意後見受任者との話合いにより、自由に決めることができます。
なので、よくわからないまま任意後見制度を活用することにはリスクがあり、専門家を活用することをおすすめします。
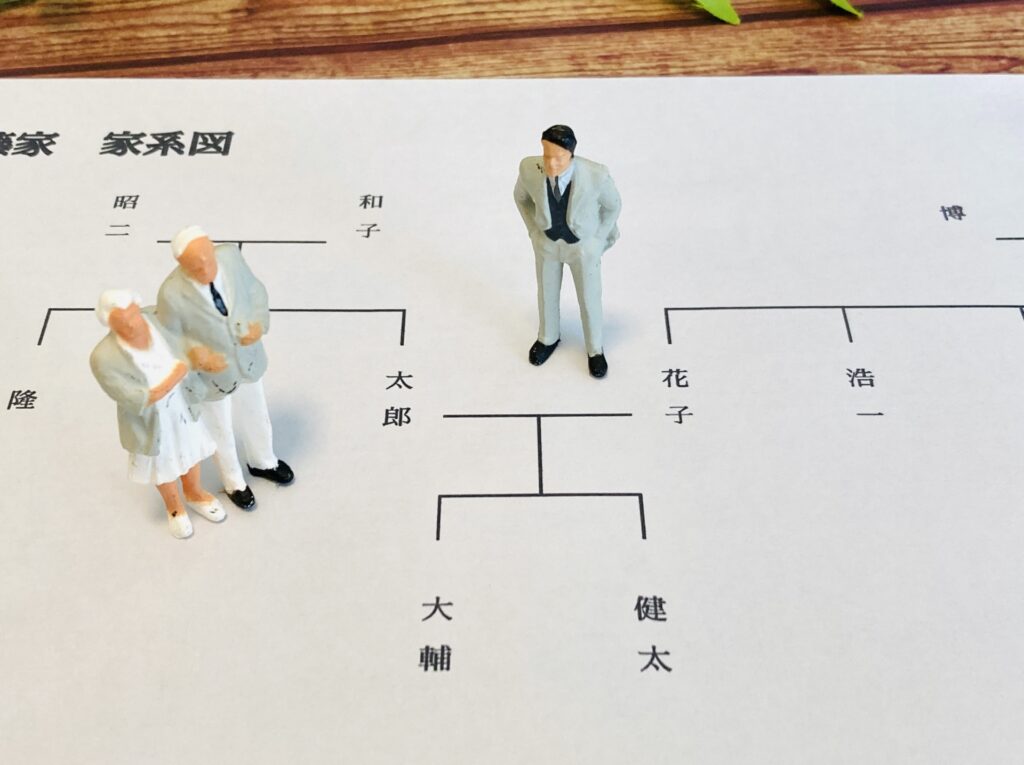
まとめ
任意後見制度は、将来の不確実性に備え、自己決定権を尊重しながら安心して生活するための重要な法的仕組みです。
信頼できる後見人を選び、具体的なケアプランを立てることで、あなたと大切な人の未来を守る手助けとなります。
任意後見制度について詳しく学び、必要な手続きを進めてみましょう。
あなたとあなたの家族の安心と幸せのために、重要なステップとなることでしょう。
今回は
『任意後見制度とは?大切な人を守る安心の手段のひとつに!江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください




