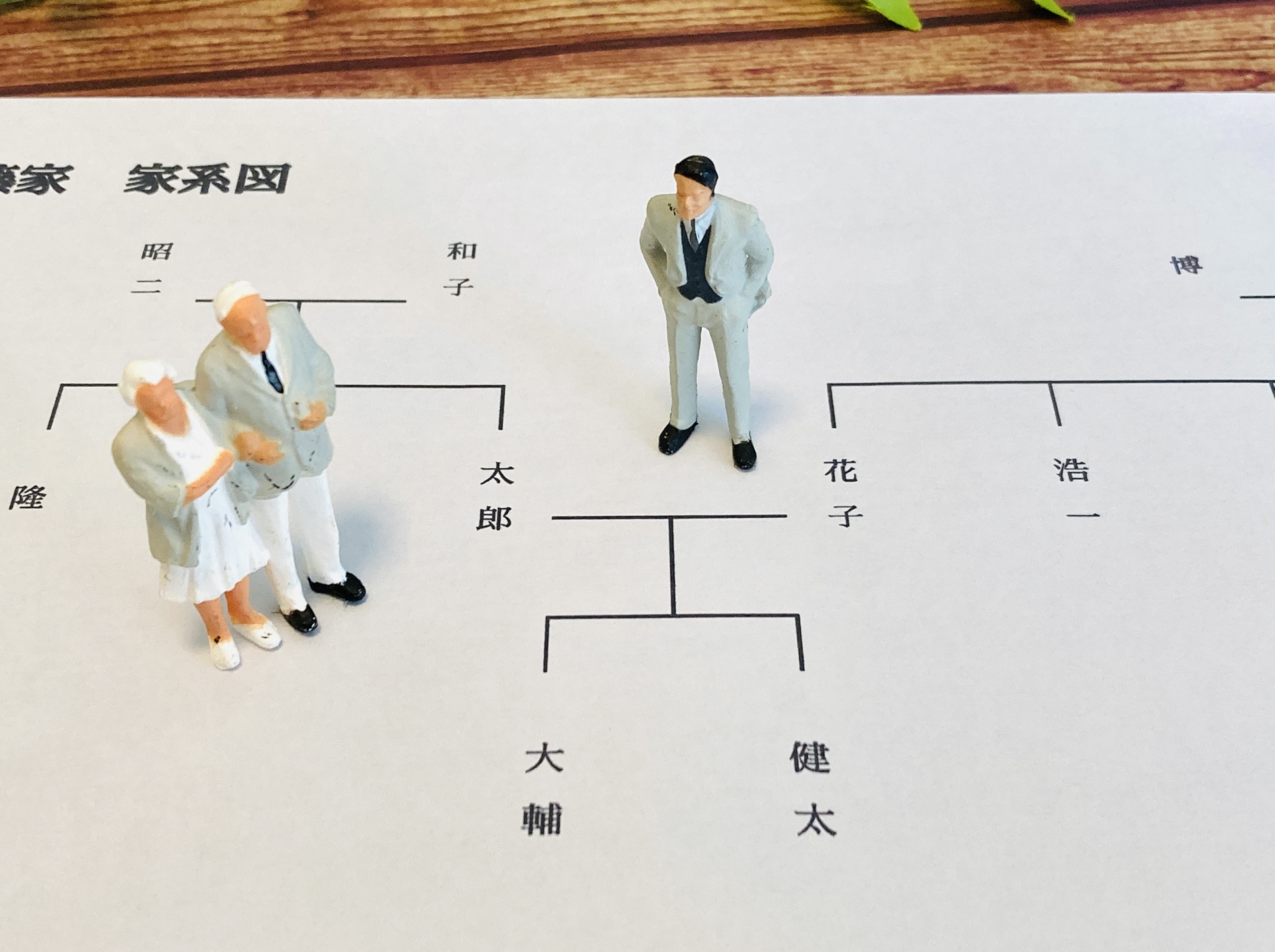東京都江戸川区 「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
当事務所では「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」のキャッチコピーのもと、皆様と共に歩むパートナーとして、相続に関するサポートを行っております。
今回は「相続手続きと成年後見制度」について、異なる背景や目的を持つ一方で、共通点もいくつかあります。
以下では、両制度の基本的なポイントを比較しながら解説していきます。
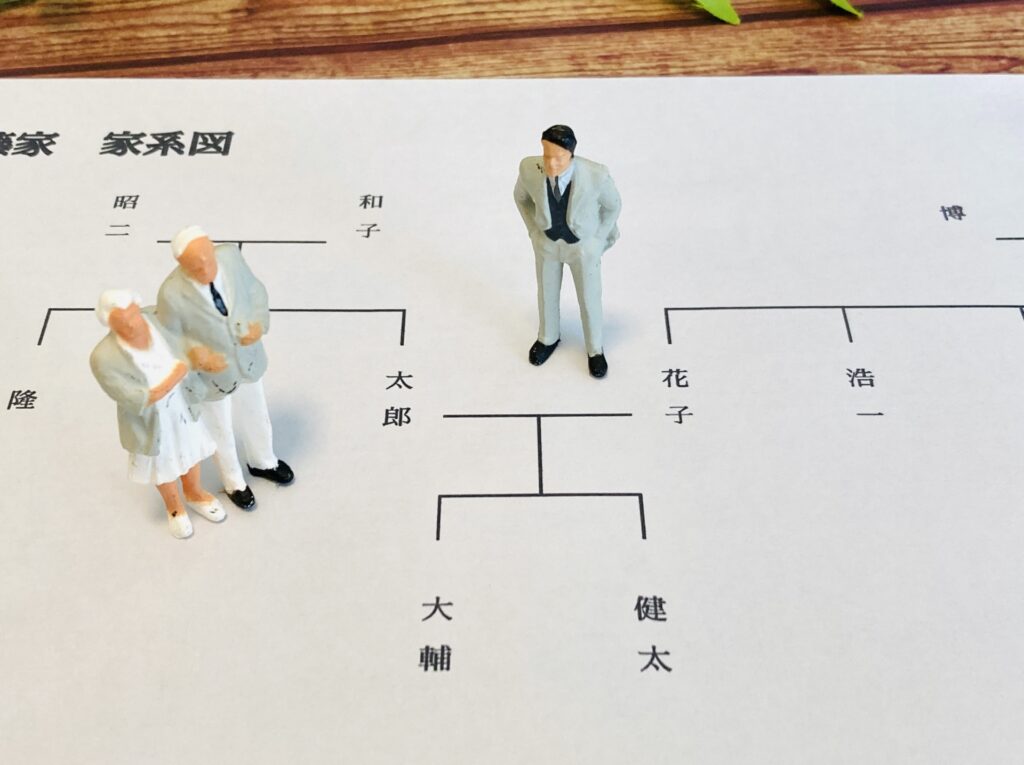
相続手続きの基礎知識と手続きのポイント
相続とは、故人の財産や権利が、法定相続分や遺言に基づき、相続人に移すことをいいます。
相続手続きのポイントを紹介します。
まずは相続開始後に「遺言書」の存在があるかを確認してください。
遺言書がない場合は、法定相続分に従って相続手続きをしますが、多くは「遺産分割協議」で相続財産を分けることがほとんどです。
なので、相続人調査をした上で、相続人を特定していきます。
なお、相続手続きから自分は抜けたい場合は相続放棄の手続きを行います。
なお、相続放棄をすることで次順位に相続人が移ることもあるので、注意してください。
成年後見制度の基礎知識とポイント
成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を守るための制度です。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人が指定され、後見人が本人の意思を代表して行動します。
成年後見制度の手続きポイントを紹介します。
後見開始の申立てを家庭裁判所に行います。
財産等の資料や戸籍謄本等を用意して後見の開始を申し立てます。
合わせて本人の現状がどうなのかも把握しておくことが大事です。
申立てを行った後、成年後見人が選任されます。 裁判所が成年後見人を選任し、後見・保佐・補助の3類型のどれかで決定されます。
類型によっては代理権の範囲や内容を決定します。
被後見人等(被保佐人・被補助人を含む)の財産状況の提出を提出します。
被後見人の財産がどれだけあるかを調査し、選任後1ヶ月を目処に家庭裁判所に提出します。
なお、後見人については親族が選ばれるか、親族以外の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)になるかは、家庭裁判所の判断によります。
相続と成年後見制度の比較表
| 項目 | 相続 | 成年後見制度 |
| 目的 | 資産の受け継ぎ | 判断能力低下者の保護 |
| 関わる人物 | 相続人、遺言者 | 被後見人、成年後見人 |
| 手続きの開始 | 死亡時 | 裁判所の判断 |
| 期間 | 一定期間内に手続き完了 | 判断能力が回復するまで |
| 資産管理 | 遺産分割、遺言の実行 | 成年後見人による管理 |
| 重要性 | 資産の正確な分割・継承 | 被後見人の利益を守る |

まとめ
私たちとの絆を大切にしながら、法的手続きを進める際のポイントや注意点をお伝えすることで、皆様の悩みや不安を少しでも和らげられることを願っています。
相続や成年後見制度に関するご相談や疑問がありましたら、お気軽にご連絡ください。
私と二人三脚で、安心して未来を歩んでいきましょう。
今回は
『家族の絆を守る:相続と成年後見制度の法的ポイントを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が徹底解説します!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら