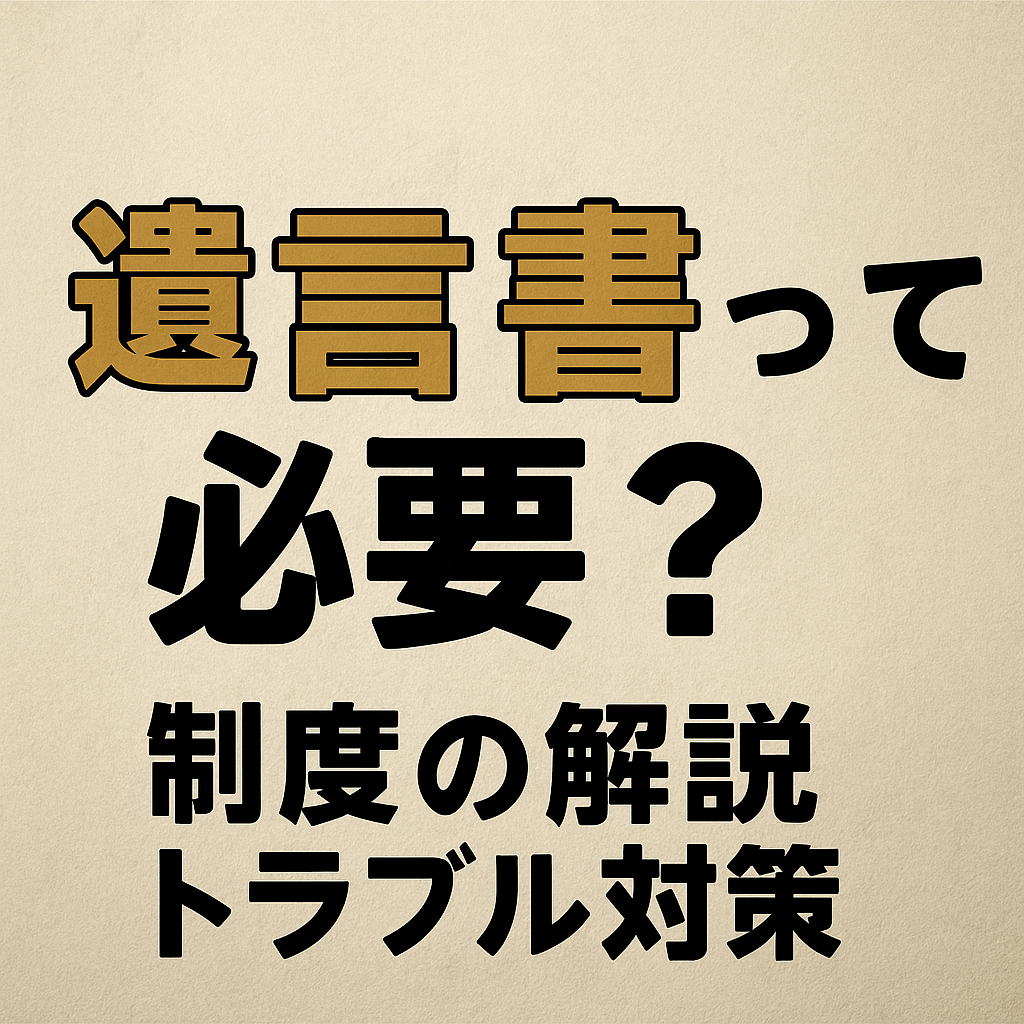こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに:遺言書は“将来の安心”を生むツールです
「遺言書」と聞いて、あなたはどんな印象を持ちますか?
「まだ自分には早い」「お金持ちが書くもの」そう思う方も多いでしょう。
でも実は、遺言書は“誰にでも関係する制度”なのです。
遺言書があるかないかで、残された家族の手続きや気持ちに大きな違いが生まれます。
今回は、相続の現場で実際に見てきた司法書士の立場から、遺言書の必要性とその制度について、丁寧にわかりやすく解説します。
第1章:遺言書がないとどうなるのか?
遺言書がない場合、財産は民法に従って分けられます。
これを「法定相続」と呼びます。
たとえば、夫が亡くなった場合、妻と子がいると「1/2ずつ」と法律で決まっています。
しかし、すべての家庭がこの割合で納得できるとは限りません。
「家は妻が住むからすべて相続したい」という希望があっても、遺言がないとその希望は実現できません。
また、法定相続人の中に連絡が取れない人や疎遠な人がいると、手続きがストップすることもあります。
結果として、手続きが何年も進まず、不動産の名義が放置される例も少なくありません。
第2章:トラブルは「お金」だけじゃない
相続のトラブルは「争族」とも呼ばれます。
金額が小さくても、人間関係がこじれる例はたくさんあります。
特に、兄弟姉妹間の相続では、感情がぶつかることも多いです。
「親は自分に世話をしてほしいと言っていた」
「いや、自分も十分に支えてきた」
こうした主張がぶつかると、たとえ100万円でも争いに発展します。
遺言書があれば、亡くなった人の意思を明確に残せます。
それが、残された家族への最後のメッセージになるのです。
第3章:遺言書には2つの種類がある
日本で一般的に使われる遺言書には、大きく分けて2種類あります。
普通方式では3つありますが、今回は実務でも多く使われている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を紹介します。
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
全文を自分で手書きする遺言です。
費用がかからず手軽に作れますが、形式ミスが多く無効になるリスクもあります。
令和2年からは、法務局で「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。
法務局で預ければ、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
自筆証書遺言で書く場合は、できれば法務局の保管制度を活用することをオススメします。
保管制度を活用すると、家庭裁判所での検認手続が不要となり、面倒な手続きが一つ減ります。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証役場で作成する正式な遺言書です。
証人2名の立ち会いが必要ですが、内容の確認と保管が制度的に保証されます。
費用はかかりますが、確実に執行されやすく、法的な安心度が高いです。
第4章:どんな人に遺言書が必要なのか?
「遺言書が必要なのは、お金持ちだけ」
この誤解は、多くの人を損させています。
以下のような方には、特に遺言書が強くおすすめされます。
-
子どもがいないご夫婦
-
再婚して、前妻・前夫との子がいる方
-
内縁関係のパートナーがいる方
-
親と疎遠な子がいる方
-
障がいのあるお子さんがいる方
-
一人暮らしの方(“おひとりさま”)
これらはすべて、法律だけでは対応しきれない家族のかたちです。
遺言書がなければ、「自分の意思」が反映されないまま手続きが進みます。
第5章:遺言書作成のポイント
遺言書はただ書けばいいというものではありません。
次のような点に注意しましょう。
-
書式や記載内容が民法のルールに合っているか
-
財産の内容が明確になっているか
-
相続人の名前が正確に書かれているか(本籍や続柄も)
-
遺言執行者の指定があるか
また、内容に偏りがあると、相続人の“遺留分”に抵触する可能性があります。
このようなケースでは、事前に専門家の確認が重要です。
第6章:実際にあった事例から学ぶ(事例は守秘義務もあり脚色しています)
江戸川区のあるご家庭では、夫が突然亡くなり、妻と二人の子が相続人になりました。
夫は不動産を持っていましたが、遺言書がなかったため、遺産分割協議に1年以上かかってしまいました。
しかも、ひとりの子が海外に住んでおり、印鑑証明の取得に手間取りました。
結果、登記の申請が遅れ、相続登記の義務化の罰則対象になる直前まで放置されてしまったのです。
もし遺言書があれば、配偶者に単独で不動産を相続させることも可能でした。
家族の手間とストレスは、大幅に減らせたはずです。
第7章:司法書士に相談するメリット
遺言書の作成は、自分だけでもできます。
しかし、「法的に有効か」「想定通りに執行されるか」を確認するには、専門家のサポートが有効です。
司法書士は、遺言書の内容チェック、登記手続き、保管アドバイスなどをトータルで支援できます。
また、家族構成を整理し、必要に応じて家系図や財産目録を作成することで、より実効性のある遺言書を残すことができます。
おわりに:今すぐ始める、家族への“思いやり”
遺言書は、あなたの意思を未来に届ける“手紙”のようなものです。
家族への思いやりを、形にして残せる制度です。
「まだ早い」と思っている今こそ、始めどきです。
遺言書があることで、家族は“迷いなく前に進める”のです。
最後に:もっと知りたい方へ
このブログを読んで「私も遺言書を書いた方がいいかも…」と感じた方へ。
ぜひ、無料で読める【きりがや事務所の相続メルマガ】にご登録ください。
司法書士・行政書士としての実体験をもとに、「今すぐできる相続・終活の準備」をわかりやすくお届けしています。
登録はこちら
電子書籍でさらに詳しく学ぶ:がんばらない相続手続き
相続で悩んでいる場合は、電子書籍『がんばらない相続手続き:効率よく進める3つの方法』をお読みください。
基礎的な相続手続きについて詳しく解説しています。
今すぐ手続きを始めて、安心した未来を手に入れましょう!