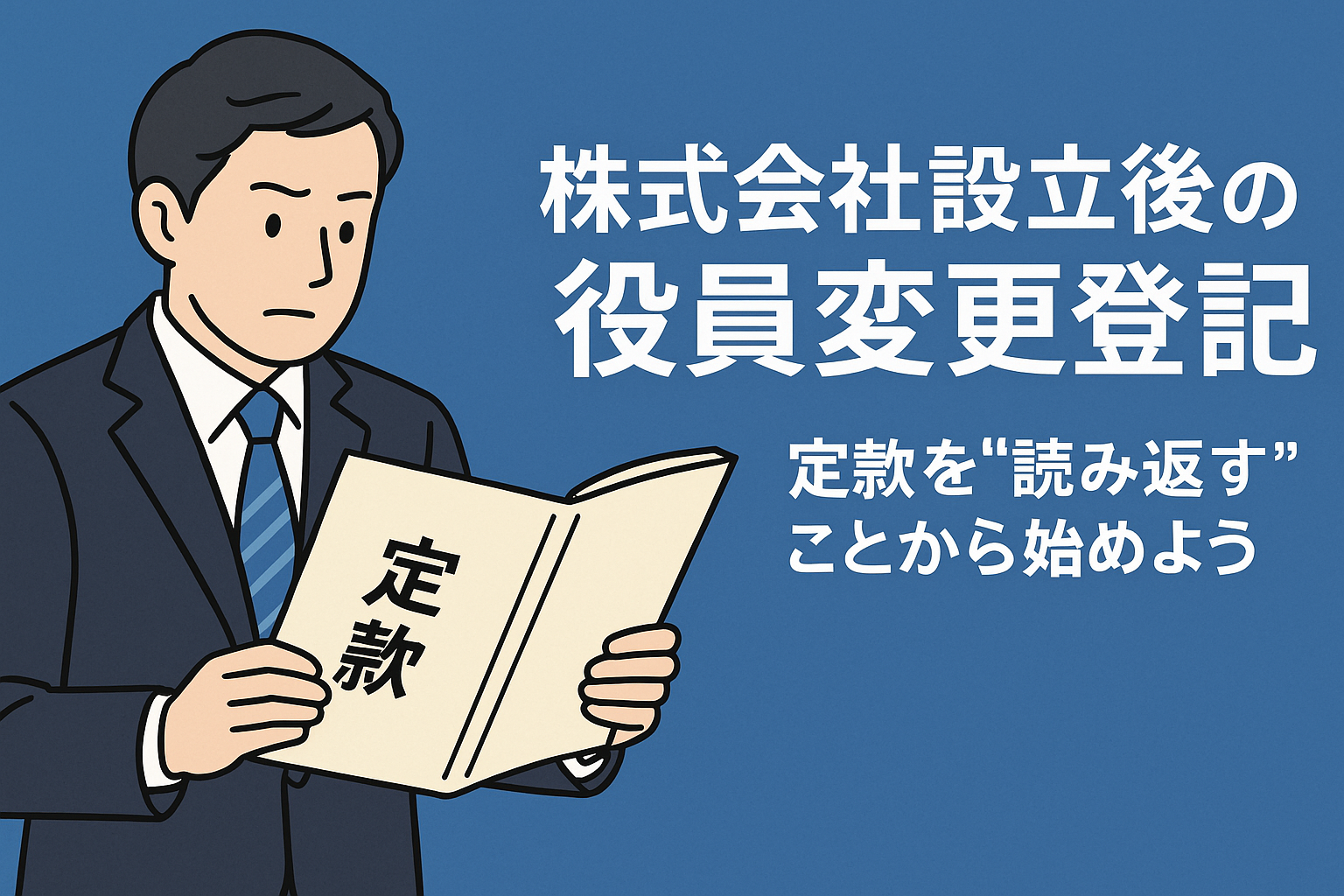東京都江戸川区船堀、「相続」「会社設立を軸とした企業法務」に特化した事務所をしている司法書士・行政書士桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに:設立して終わり、ではありません
株式会社を設立した直後は、ようやく登記が完了して一安心という方も多いでしょう。
しかし、実は設立後こそ定款をじっくり読むタイミングなのです。
定款には、会社運営に関わる「ルールの原点」が書かれています。
この内容を理解していないと、後に役員変更登記で慌てることになります。
役員変更登記は“定款どおり”に行う必要がある
株式会社では、取締役や代表取締役の任期が来たら、再任または交代の登記を行います。
このとき登記の根拠となるのが、定款に記載された役員の任期です。
たとえば、
-
「取締役の任期は2年」
-
「監査役の任期は4年」
と定款に明記されている場合、その期間が満了するたびに登記が必要になります。
ただ、多くの会社は任期を10年にしているため、10年後に役員構成が同じであっても、必ず役員変更登記が必要です。
任期を過ぎても登記を怠ると、法務局から指摘を受けたり、過料の対象となることもあります。
実際、「設立から5年以上登記していなかった」というケースは珍しくありません。
定款でチェックすべきポイント①:役員の任期
まず確認すべきは「第○条 取締役の任期」の部分です。
多くの設立時の定款では、取締役の任期を定款で定めています。
ただし「公開会社でない株式会社(譲渡制限会社)」の場合、定款で最長10年まで延ばすことができます。
中小企業では「同じメンバーで長く経営を続けたい」と考える方が多く、任期を10年にしておくと、登記手続きの頻度を減らすことができます。
ただ、10年をきちんと覚えていない経営者が多いです。
設立当初から専門家に任せてしまうと、そのあたりを意識しないことがあるので、専門家から書類を返却されたときは必ず定款をみて、次はいつ役員変更登記をしなければならないのかを意識してください。
設立後に「任期が短くて登記ばかり」と気づいても、定款変更には株主総会決議と登記が必要です。
最初にどんなサイクルで登記するかを意識しておくことが大切です。
定款でチェックすべきポイント②:取締役会の有無
次に確認してほしいのが「取締役会を設置するかどうか」です。
中小企業では、取締役会を設けず、代表取締役1名だけの体制が一般的です。
取締役会を設置していると、役員変更登記の際に議事録や承認手続きが複雑になります。
逆に取締役会非設置会社であれば、株主総会と代表取締役の決定だけで済むことが多く、登記の手間も軽減されます。
「設立時に何となく決めた」という方は、定款を開いて確認してみましょう。
個人的にはスモールビジネスでの会社設立であれば、取締役会は置かなくてもいいです。
取締役会を置く場合、最低4名(取締役3名、監査役1名)が必要になります。
よほどすぐにでも上場したい会社でなければ、まずは取締役会を置かなくてもいいでしょう。
定款でチェックすべきポイント③:公告方法・事業年度
意外と忘れがちなのが、「公告方法」と「事業年度」です。
公告方法は官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかが定められています。
変更が必要な場合、これも登記が伴います。
設立当初はホームページを用意する煩雑さから「官報」で問題ありません。
いきなり電子公告とかにすると、減資とかするときの電子公告の煩雑さが伴い、費用も余計にかかってしまいます。
会社の成長具合に合わせて公告方法も見直しましょう。
また事業年度も、定款に定められた期間に合わせて決算を行い、役員の任期満了や再任の時期にも影響します。
事業年度末=株主総会の開催タイミング=役員改選のタイミングとなるため、定款を確認して管理スケジュールを立てておくと安心です。
定款を“読む”ことは会社を守ること
定款は設立時に司法書士が作成し、法務局に提出した公的なルールブックです。
しかし設立後に読み返す経営者は、実は多くありません。
登記のトラブルや遅延の原因の多くが、「定款の内容を把握していなかった」ことにあります。
-
任期が切れていたのに気づかなかった
-
代表者交代に必要な決議方法を知らなかった
-
定款にない事業を始めてしまった
こうしたケースを防ぐためにも、設立から数年経った今こそ、改めて定款を見直してみてください。
まとめ:定款を味方につけて、会社運営をスムーズに
会社を守るためには、法律上のルールを理解することが大切です。
定款はその第一歩であり、経営判断の“よりどころ”になります。
とくに役員変更登記は「いつ」「どうやって」行うかを定款が決めています。
放置すれば過料のリスクがありますが、逆に定款を理解すれば手続きはスムーズです。
司法書士・行政書士きりがや事務所では、定款の見直し・任期管理・役員変更登記のサポートを行っています。
「うちの定款、最近見ていないな」と思ったら、今すぐファイルを開いて、会社を守る第一歩を踏み出しましょう。