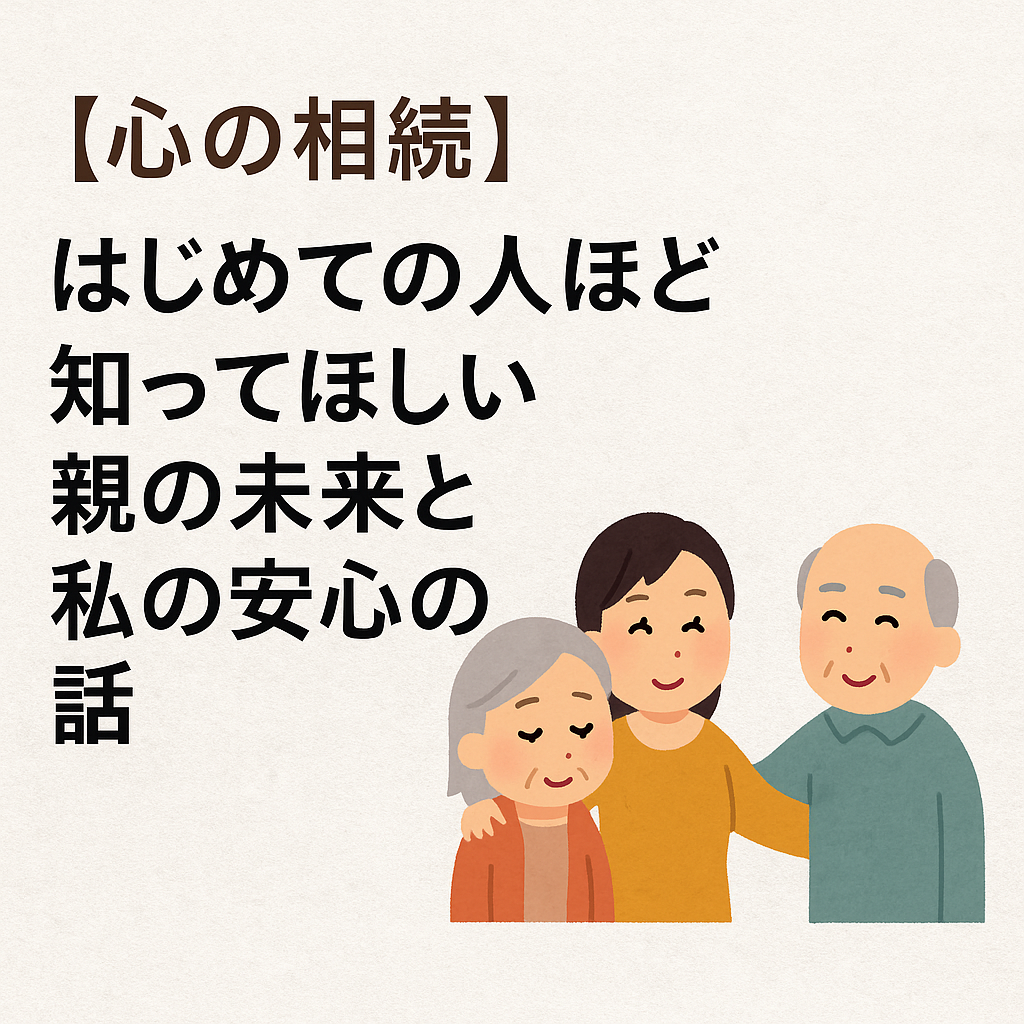こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
メルマガの登録はこちら
目次
【はじめに】「相続」はもっと先の話だと思っていた
「うちはそんな財産ないし」「相続なんてもっと先でいいでしょ」
そう思っていませんか?
ある事例(脚色しています)で紹介します。
親が入院して、いろいろな手続きを兄弟と分担したとき、“お金の問題”よりも、“家族の気持ちのすれ違い”の方が辛かったんです。
書類がない、通帳が見つからない。
あれこれ聞こうにも、親も弱っていてはっきりしない。
それなのに兄弟からは「何も準備してなかったの?」と責められる。
これは、まさに【心の相続】の問題です。
【気づき】財産の有無よりも、“想い”を引き継ぐことの難しさ
相続って、法的な問題やお金の分配だけではありません。
- 実家をどうするか
- 親の希望はどこにあるのか
- 誰が面倒を見るか
- 兄弟姉妹とどう関わるか
こうした“人の気持ち”が、相続の場面で一気に表面化します。
相続とは、実は「家族の関係性そのもの」が問われる出来事なのです。
【現実】認知症になってからでは遅い
「親のこと、そろそろ考えなきゃ」と思っていても、実際に行動する人はほとんどいません。
しかし、日本人の【現実】認知症になってからでは遅い
「親のこと、そろそろ考えなきゃ」と思っていても、実際に行動する人はほとんどいません。
認知症になる確率は年齢が上がるにつれて高くなり、65歳以上では約16%が認知症と推計されています。
具体的には、70代後半で10%超、80代前半で約22%、80代後半では約44%と上昇し、90歳以上ではさらに高くなります。
2025年には、高齢者の5人に1人、国民の17人に1人が認知症になると予測されています。
でも、現実には
- 認知症になったあとでは「任意後見」も「家族信託」もできません
- 急に入院してしまえば、口座は凍結され、支払いに困ることもあります
- 遺言がなければ、兄弟で揉める可能性は高くなります
つまり、“元気なうち”にこそ準備が必要なんです。
でも、法律の話って難しいし、親にも切り出しづらいですよね。
【提案】“法制度”を使って、気持ちをラクにする方法がある
実は、「相続」や「介護」の準備って、もっとやさしくできるんです。
たとえば──
【任意後見制度】
元気なうちに「もしものとき、誰に任せるか」を契約で決められる制度。
【家族信託】
親の財産管理を家族がサポートできる、柔軟な仕組み。
【遺言書】
“争族”を防ぐ最もシンプルで強力な手段。特に一人っ子家庭におすすめ。
これらを使えば、“親の希望”と“子の負担”のバランスが取りやすくなります。
【本音】私たちは「お金の相続」よりも「心のもつれ」がつらい
親の預金がどうとか、不動産の評価がどうとかよりも、
「兄弟で話が合わない」
「親の想いがわからない」
「“なんで私ばっかり”ってモヤモヤする」
そんな気持ちのズレが、家族を傷つけていきます。
相続は、“人と人との橋渡し”でもあります。
だからこそ、法律の力を借りて、気持ちを整理することが大切です。
【まとめ】“今だからこそ”できることから始めてみませんか?
- 「相続の準備=財産が多い人だけのもの」ではありません
- 「親のことはまだ早い」と思っても、元気な今だからできることがある
- 「心の相続」は、気持ちの整理と家族の安心をつくること
このブログでは伝えきれない、【任意後見】や【家族信託】の基本と【私たちに何ができるのか】をまとめた有料noteを公開しています。
▼詳しくはこちら▼
📘note記事『任意後見と家族信託の使い分け』はこちら