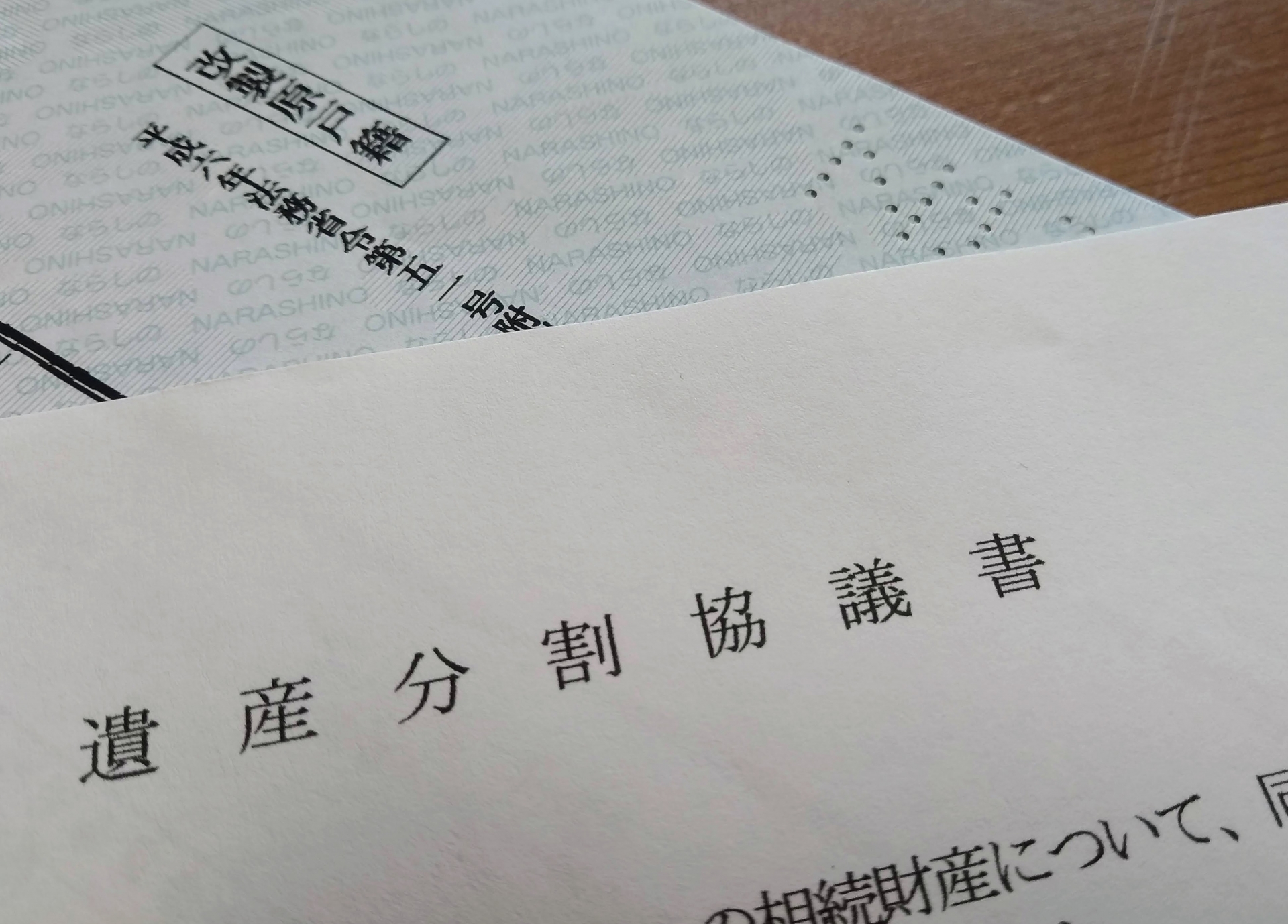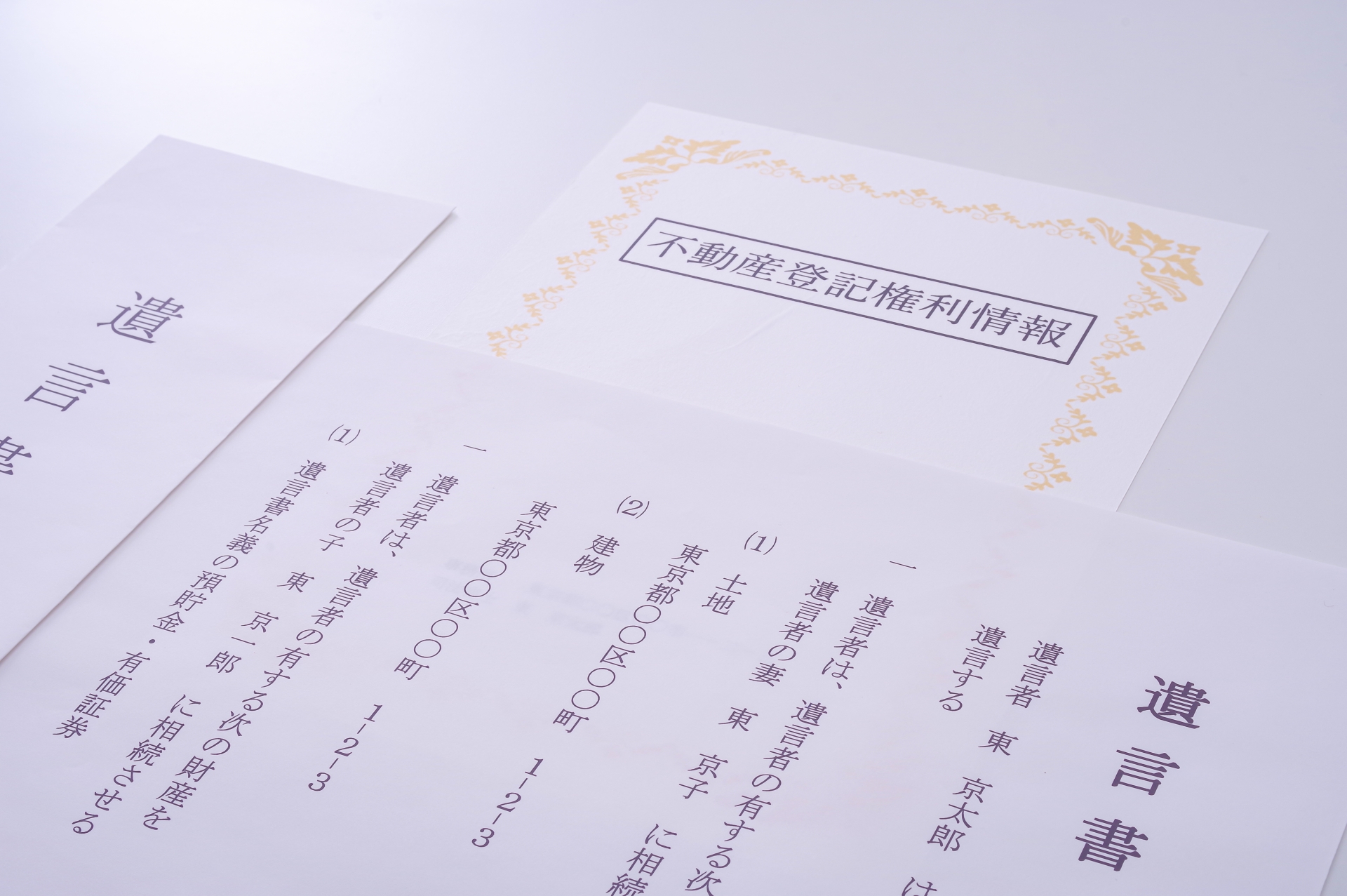東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「配偶者居住権」という制度ができたことは知っていますが、そもそもどのような制度なのですか?登記もあると聞いていますが…
「配偶者居住権」聞いたことがある方はいるでしょうか。
そこで、今回は令和2年4月1日から登場した「配偶者居住権」について、書いていきます。

配偶者居住権とはなにか?
配偶者居住権については、配偶者に認められた制度であることをまずは知ってください。
今まで長い間住んでいた家に住んでいたいという要望はあるでしょう。
そうすると、遺産分割協議で不動産の所有権を配偶者名義にすれば問題解決します。
しかし、生活資金を遺産分割協議で確保できるかは不透明な部分はあります。
もし、他の相続人が不動産を取得した場合、配偶者はその相続人間と賃貸借契約を締結する必要があります。
ただ、相続人が賃貸借契約を締結するとは限らないため、配偶者は住む家がなくなってしまうというデメリットもあります。
そのような時代的な背景から、配偶者居住権は登場しました。
また、被相続人名義の不動産を配偶者が相続し、相続登記をしたとしても、また配偶者が亡くなったときに相続登記をする必要があり、面倒になるというのもあります。
配偶者居住権とは、配偶者の一方が亡くなったあと、残された配偶者が、亡くなった配偶者所有の建物にそのまま住み続けることができる権利です。
配偶者居住権の制度は、高齢化社会を背景にして誕生した制度です。
民法の条文では1028条となります。
(配偶者居住権)
第1028条
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
配偶者居住権の成立要件
まず前提として、名義人の配偶者が、その名義人の有する建物に、名義人の相続開始のときに住んでいることが必要です。
配偶者は法律上の婚姻関係にあったものをいい、事実婚は含まれません。
そして、配偶者居住権は遺産分割(協議、調停、審判)、遺贈、死因贈与によって取得します。
なので、遺産分割協議で、建物の所有権は長男が、配偶者居住権は配偶者が取得するという内容で成立します。
被相続人の遺言において、配偶者居住権を遺贈することができます。
特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定)であると無効になると解されているようです。
ただ、無効になるかの解釈については合理的に解釈すれば有効にしてもいいのではないかという意見もあるため、遺言で配偶者居住権を取得させたい場合は注意したほうがいいです。
配偶者居住権の効力
配偶者居住権が成立すると、配偶者は居住建物を無償で使用収益することができます。
あとは、配偶者居住権の存続期間は原則として相続発生時から配偶者が亡くなるときまでとなっています。
あと、建物所有者(相続人)は配偶者に対し、配偶者居住権の登記を備える義務があります。
配偶者居住権の登記は、配偶者と建物所有者との共同申請となります。
おそらく、まずは被相続人から建物所有者への相続登記をし、連件で配偶者居住権の登記をすることが多いでしょう。
配偶者居住権の登記について
登記を備えれば、配偶者居住権を第三者に対抗することが可能となります。
賃借権の場合、建物の占有が対抗要件となりますが、配偶者居住権の対抗要件は登記のみというところに注意です。
配偶者居住権の登記の添付書面としては、
・登記原因証明情報
・登記識別情報通知
・印鑑証明書(義務者のもの)
・代理権限証書
となります。
登記原因証明情報としては、被相続人の相続を証する情報としての戸籍(除籍)の謄本若しくは全部事項証明書や住民票の除票の写しなどの他遺産分割協議書(調停調書や審判書)、遺言書及び死因贈与契約若しくは、配偶者居住権に必要な情報を盛り込んだ報告的な登記原因証明情報を提供することになります。
登録免許税は不動産の価格(評価証明書に記載されている金額)の1000分の2となります。

まとめ
配偶者居住権はこれからの高齢化社会においては必要になる制度です。
色々組み合わせることで、私は空き家対策にもなると思っています。
今後「配偶者居住権」は注目される制度と言えそうです。
今回は
『配偶者居住権 制度趣旨と要件、登記について江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらから
参考書籍
| Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務 | ||||
|