こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続手続きの中で「相続登記」は非常に重要なプロセスの一つです。
しかし、初めて相続手続きに直面した方にとって、固定資産税評価額や路線価といった専門用語は少し難解に感じるかもしれません。
特に、相続登記に必要な「登録免許税」と、相続税を計算するための「相続財産の評価額」では、それぞれ異なる評価基準が用いられます。
この違いを理解しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができ、後々のトラブルを避けることが可能です。
今回は「固定資産税評価額」と「路線価」の違いを紹介します。
最後までぜひ御覧ください。

固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは、不動産に対して毎年自治体が算定する評価額です。
この評価額は、不動産の課税標準額として使われるものであり、固定資産税の納税通知書に記載されています。
相続登記を行う際には、この固定資産税評価額を基に、登録免許税の計算を行います。
具体的には、相続登記における登録免許税は、「固定資産税評価額 × 税率」で算出されます。
税率は0.4%です。
この固定資産税評価額が正確に反映されていない場合、誤った金額を支払ってしまうことになるため、事前にしっかり確認することが大切です。
路線価とは?
一方で、路線価とは、国税庁が毎年公表する評価額で、特定の道路に面した土地の1平方メートルあたりの金額です。
路線価は、相続税の計算に用いられるもので、土地の時価を基準にした評価額と言えます。
路線価は地域によって異なり、特に都心部では実際の取引価格に近いことが多いため、相続税を計算する際にはこの評価額が重要な指標となります。
例えば、都内にある不動産の場合、路線価が非常に高額になることが多く、その分、相続税の負担も増える可能性があります。
そのため、路線価をしっかりと把握し、相続税の申告を行うことが重要です。
固定資産税評価額と路線価の違い
ここで重要なのは、固定資産税評価額と路線価は、それぞれ異なる目的で使用されるということです。
固定資産税評価額は主に相続登記や固定資産税の算定に使われる一方、路線価は相続税の評価基準となります。
これらを混同してしまうと、手続きがスムーズに進まないだけでなく、誤った金額での申告や支払いが発生するリスクもあります。
相続登記を進める際には、まず固定資産税評価額を確認し、登録免許税を正確に計算しましょう。
また、相続税の申告が必要な場合は、路線価を基に評価額を算出し、適切に申告することが求められます。
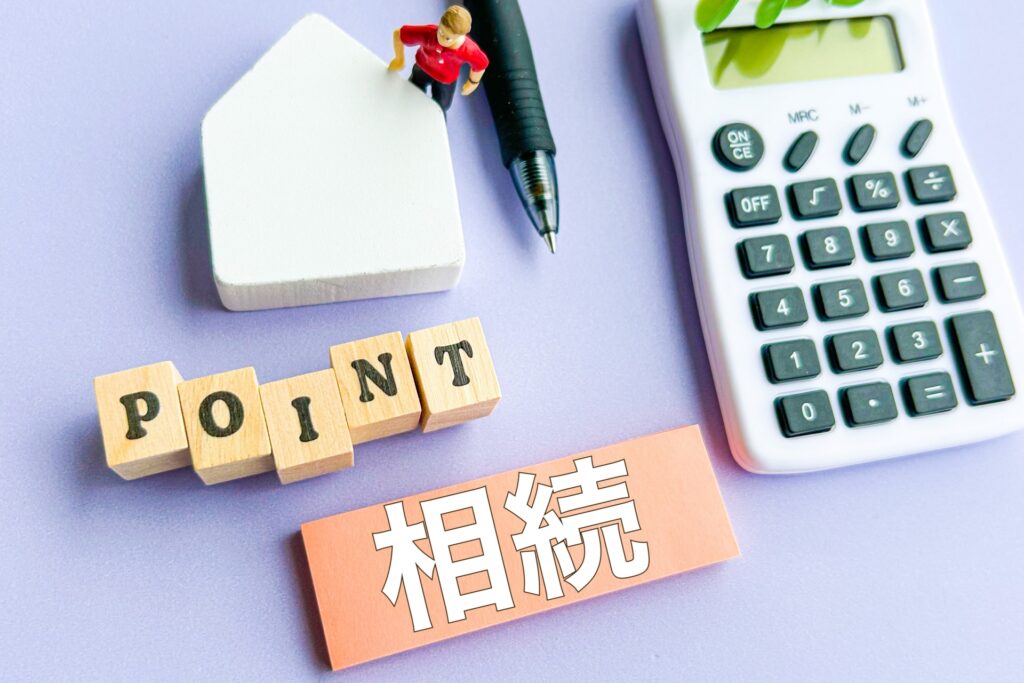
まとめ
相続手続きは複雑であり、固定資産税評価額や路線価といった評価基準の違いを理解していないと、後々のトラブルに繋がることがあります。
しかし、これらの基準を正確に把握しておけば、相続登記や相続税の申告をスムーズに進めることができ、結果として相続手続き全体を効率的に進めることが可能です。
相続登記や相続税の手続きを行う際には、まずは固定資産税評価額と路線価をしっかり確認し、それぞれの役割を理解した上で進めましょう。
これにより、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続を完了させることができるはずです。
この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『相続登記の登録免許税と相続税の評価基準の違いを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら




