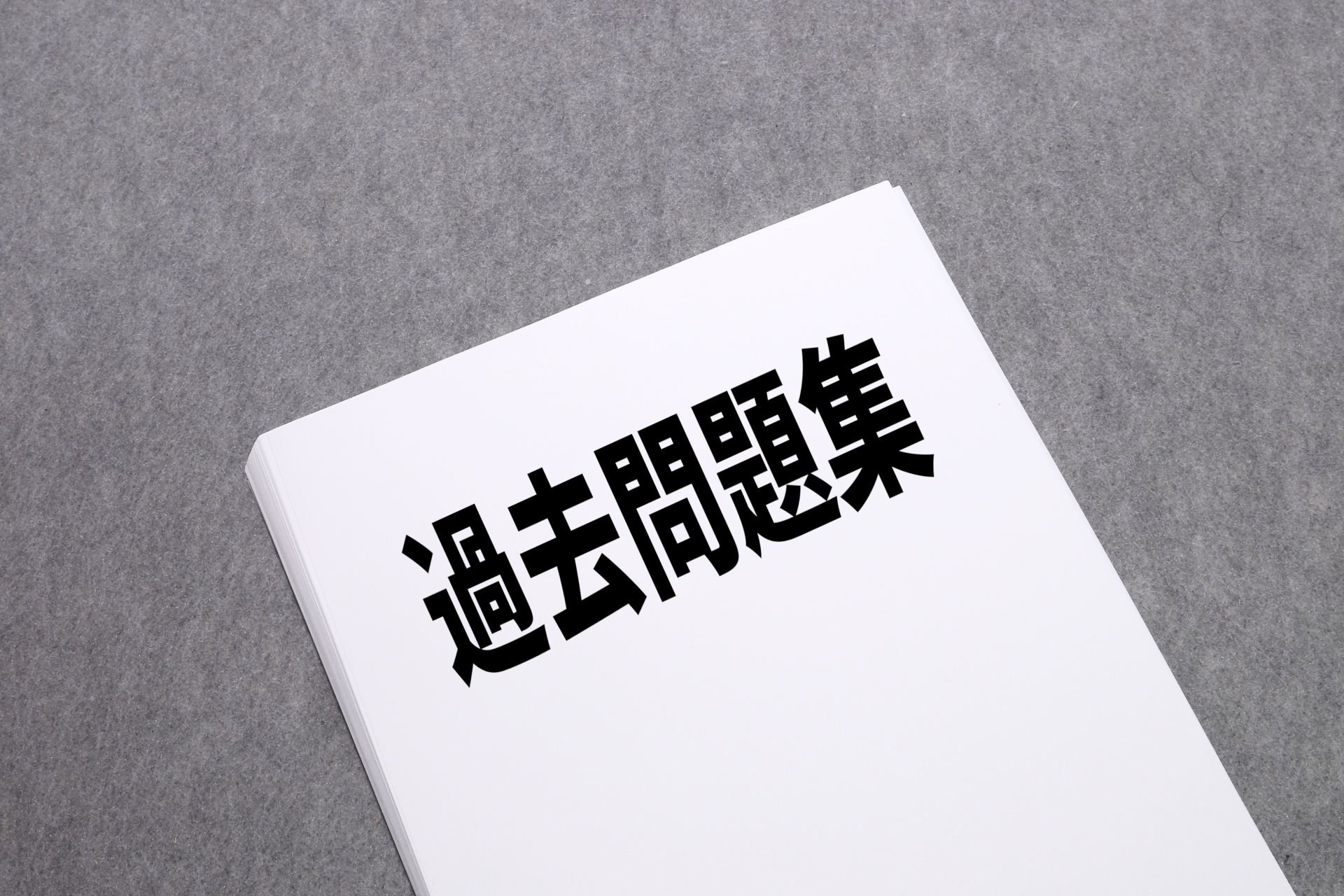東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザーの司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「資格合格逆算メソッド」。
合格(=受験日)点を取るために、逆算して今何をすべきかを考えるメソッドです。
各種資格試験では、何点取れば合格できるのかの基準は公表もしくは予備校のサイトでも紹介されています。
そこで、今回は、常に合格点を取るための勉強法を意識することの重要性を書いていきます。
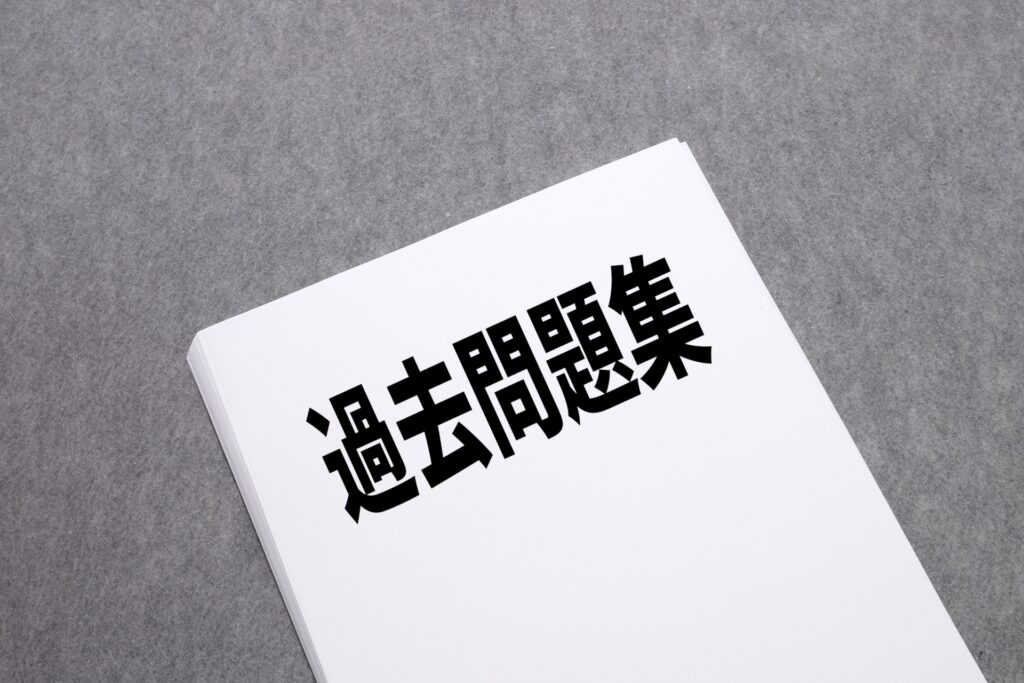
資格試験 満点は目指さない 完璧主義を捨てる
どの国家資格試験でもそうですが、満点を取らないと合格できないという試験はありません。
運転免許を取得する際の学科試験でさえ、本来運転をするためには必要な知識を得るためには満点をとらないといけません。
しかし、運転免許の学科試験でさえ、100点中90点取れれば合格できます。
なので、まず大事なのは、資格試験の範囲を逸脱した勉強をすると合格は遠のくということを意識してください。
そのうえで、常に合格するためには9割目指すことを意識して勉強してください。
ある意味割り切りが必要なのです。
割り切り勉強法 過去問を大事にすること
本試験では、どうしても数問範囲外の問題は出てしまいます。
そこで得点できるかどうかで差は正直出ません。
勘で正解できればもうけものです。
実際に差が出るのは過去問の応用問題が出たとき。
暗記では対応できないが、過去問から予想して解ける問題が出たときに差が出る問題でいかに拾えるかが勝負の分かれ目となります。
だいたい全受験生の正答率で60%位の問題でしょうか。
正直、ここ数年の過去問と全く同じ問題は資格試験では出ません。
むしろその周辺知識で一捻りした問題が出題されやすいのです。
むしろ、試験委員も正答率が高くなく、過去問の周辺知識で解けそうな問題はまた出題されることもあります。
なので、過去問の積み重ねがまずは合格への第一歩です。
過去問は何回回せばいいのか?
よく受験生の間で、過去問は3回回せばいいとか、暗記できれば過去問は卒業とかよく耳にします。
過去問は、試験の範囲を示す重要な資料でもあります。
過去問を表面的に捉えるのではなく、類似する制度、改正法だとこういう聞かれ方をするとか違った視線からの検討も大事になります。
過去問を暗記するような勉強はせず、類似制度だとどうかとか一歩進んだ過去問の勉強をしてください。
過去問だけでどうしても足りないというのであれば、問題集を活用するか、答案練習会を活用してください。
過去問のインプットだけでは足りない?アウトプットとしても活用
過去問の勉強はインプットの側面もありますが、アウトプットでも重要な役割をします。
正解にたどり着くにはどういう選択肢の切り方をするとか、本番さながらに解くといいでしょう。
本番では過去問の解説までの知識は不要です。
むしろ解説は細かく書いていることが多いので、必要最低限の知識を読みつつ、テキストを再度読み直すなどしてください。
どうしても同じようなところで間違えるのであれば、間違えノートを作るなど弱点を克服するなどしてください。
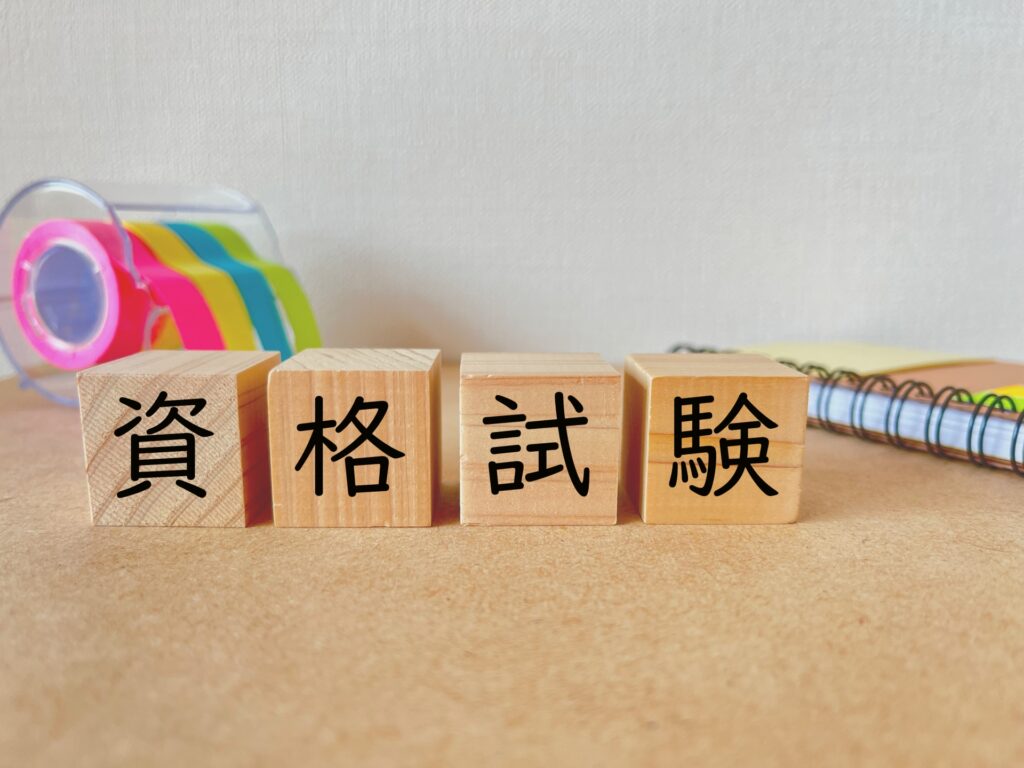
まとめ
合格点を取る勉強法。
過去問と友達になるくらいまでしっかり勉強することが第一歩。
まずは敵をしっかり知ることが合格への第一歩となります。
今回は
『【資格合格逆算メソッド】資格合格の第一歩: 過去問と友達になり、敵を知る攻略法』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください