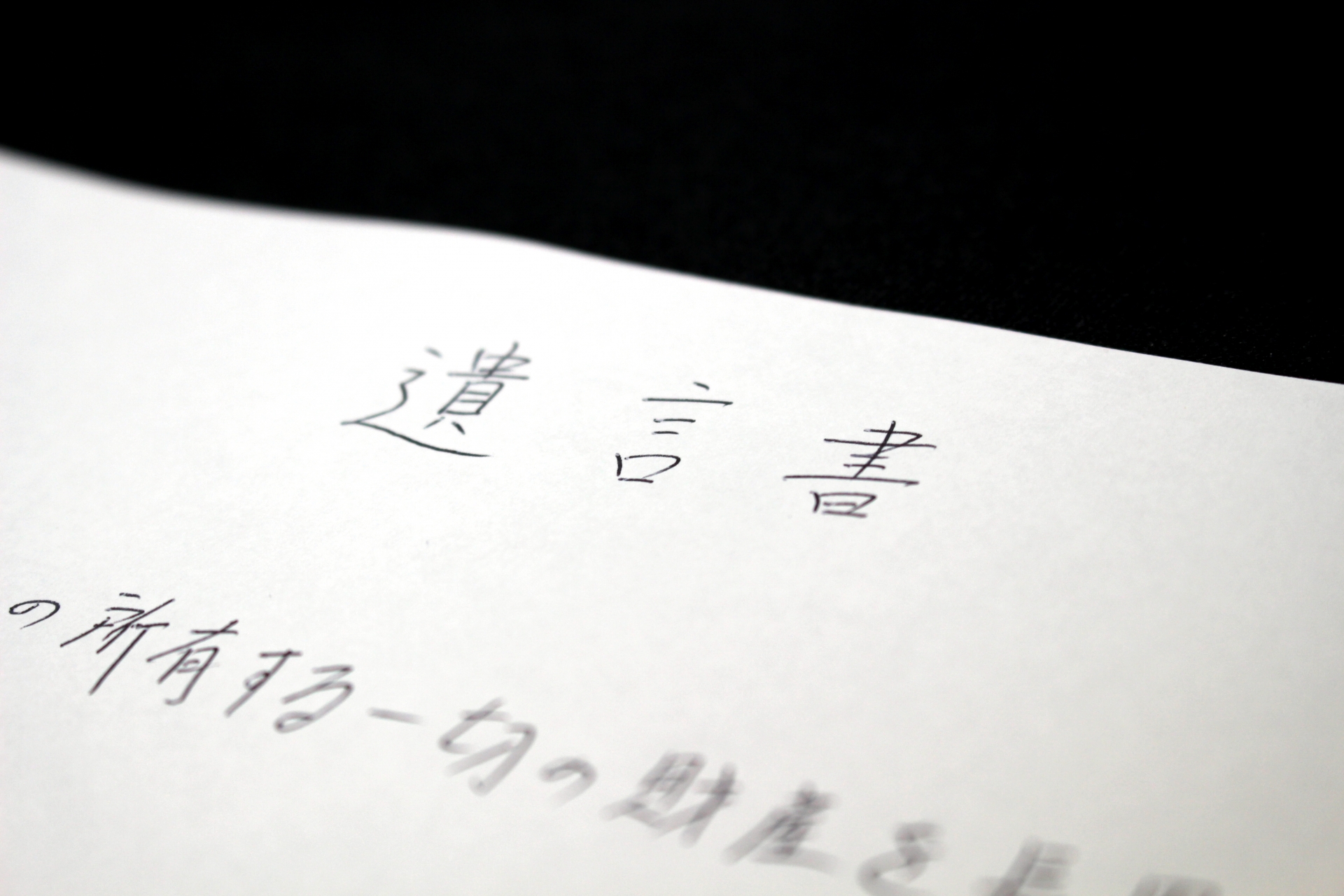東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近は民法改正が頻繁に行われているため、いつの段階で法律が変わったのか分からなくなっている方も多いでしょう。
相続法の改正もその一つ。
今回は改めて、自筆証書遺言の方式の緩和について触れていきます。
今後利用価値が増えそうな気がするので、参考にしていただけると幸いです。
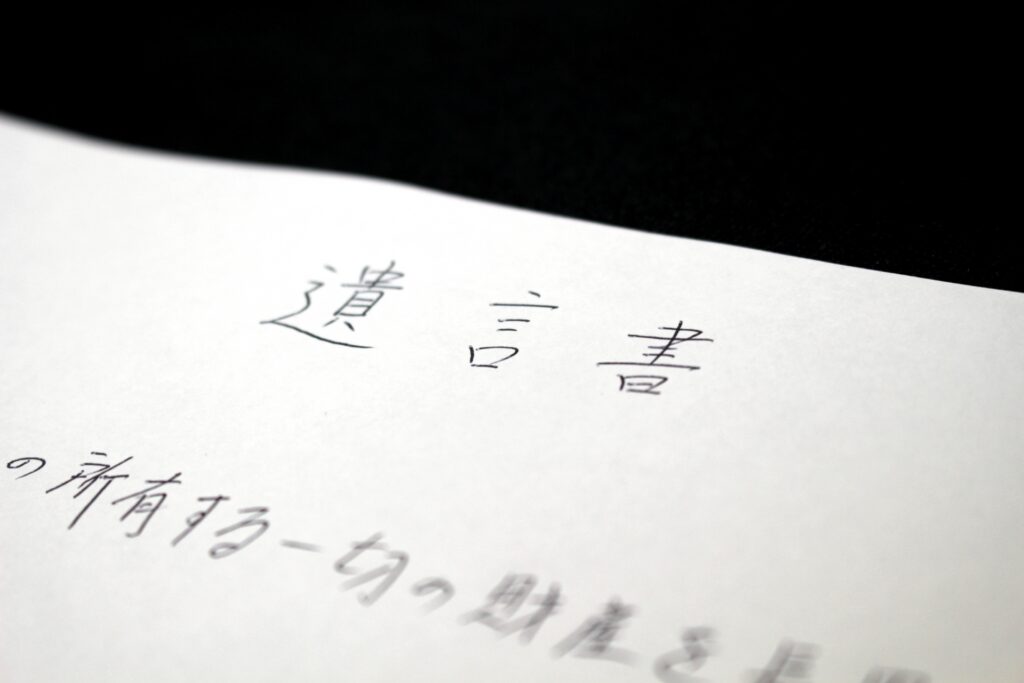
自筆証書遺言の方式の緩和について
以前までは、財産目録も含めて、全て自書することが必要でした。
なので、遺言を書くことについてハードルが高く、さらに民法の規定に従って記載しないとせっかく書いた遺言が無効になってしまうというリスクもありました。
そこで、自筆証書遺言を更に使いやすくしようと改正がされました。
原則、本文は自書する必要がありますが、財産目録部分についてはパソコンなどで作成してもいいという扱いに変わりました。
財産目録をパソコンで作成してもいいですし、不動産の場合は登記事項証明書、預金通帳のコピーとかでもいいことになります。
ただし、財産目録や不動産の登記事項証明書や通帳の写しには、偽造防止の観点から、本人の署名と捺印が必要になります。
毎葉に署名押印を要するのは、偽造防止の観点からなので、必ず自書と捺印を忘れないようにしてください。
印鑑は実印でも認印でもいいですが、できれば実印で押印したほうがいいでしょう。
なお、遺言書を書き間違えた場合、書いた方が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。
書き損じた場合は再度書き直すことをおすすめします。
自筆証書遺言を法務局で預けるメリットとは?
公正証書遺言だとハードルが高いので、自筆証書遺言で書きたいというかたもこれから増えてくるでしょう。
しかし、自筆証書遺言の場合、自宅とかで保管するとなくしてしまうということもあります。
なので、自筆証書遺言で遺言書を書きたい場合は、法務局で預かる制度を利用することを前提に作成するといいでしょう。
法務局に保管をする場合、用紙も決まっていて、余白なども決められています。
なので、それにそって、自筆で遺言を書きましょう。
なお、法務局で遺言を保管する際は、自分で管轄の法務局に行かなければなりません。
代理は認められないので注意です。
なお、遺言者が亡くなったあと、自筆証書遺言が法務局に保管されていることを通知してくれる制度があることをご存知でしょうか?
遺言者の死亡後、遺言者が遺言書の保管の申請をする際に、遺言者の死亡時に遺言者が指定する者に対し遺言書を保管している旨を通知することの申出をした場合には、遺言書保管官は、遺言者の死亡の事実を確認したときは、遺言書を保管している旨を遺言者が指定した者に通知することができる制度があります。
なので、遺言書保管をするのと同時に、遺言執行者などを通知者にする申出はぜひしておくといいです。

まとめ
自筆証書遺言を取り巻く環境は変化しています。
公正証書遺言を書きたいが、まだハードルが高いとか、遺言書を書き直すことが想定されている場合は、自筆証書遺言から始めるのがいいです。
今回は
『自筆用証書遺言のことを考える 要件緩和で利用価値あり?江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら