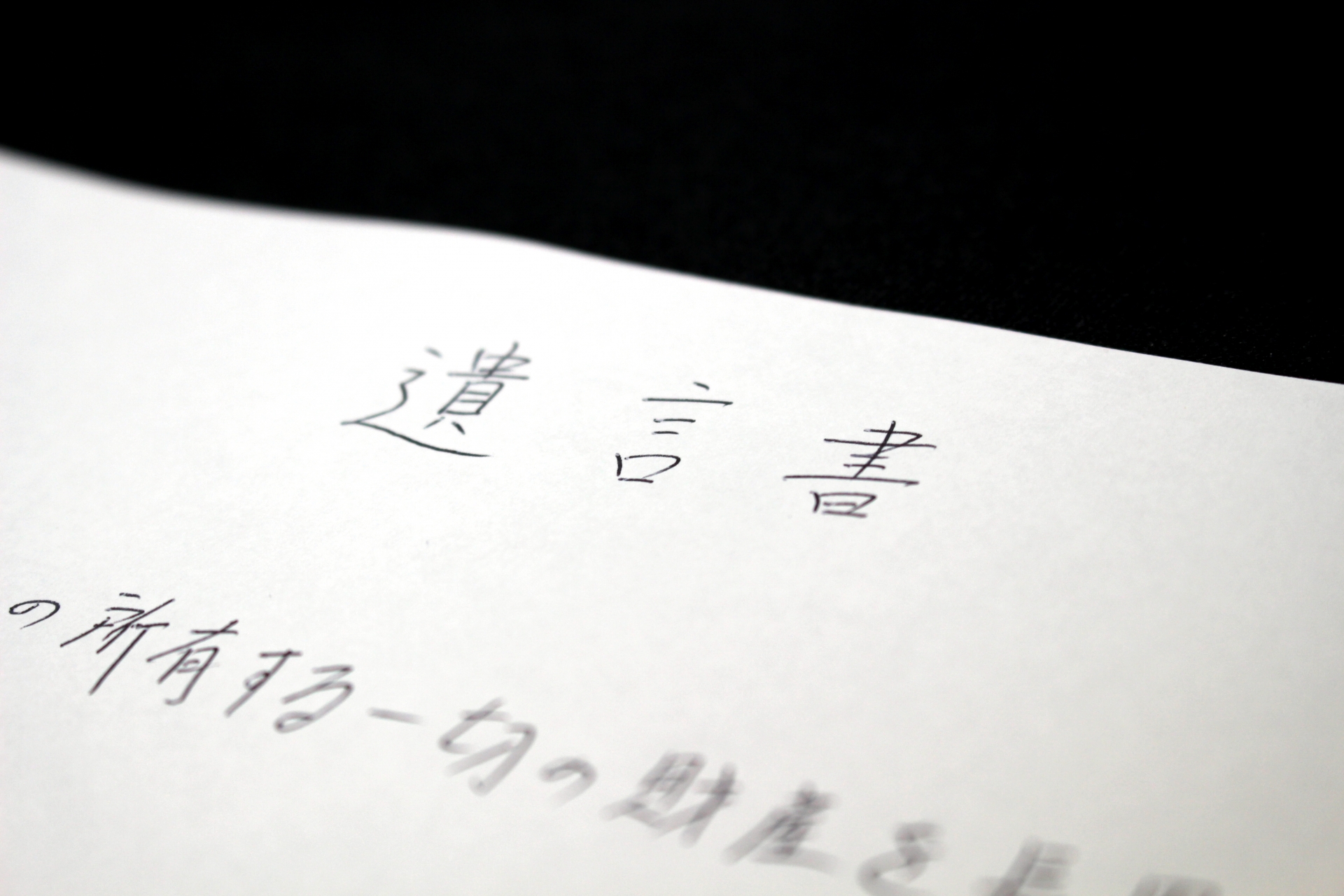自筆証書遺言を法務局に保管できる制度があることを知っていましたか?司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 小さい会社の企業法務・相続遺言専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
高齢化社会が進み、そろそろ遺言書でも書こうと思っている人もいるでしょう。
でも、まだ元気なので、いきなり公正証書遺言だとハードルが高い。
なので、まずは自筆証書遺言から作ろうかと思っている人もいるでしょう。
自筆証書遺言で気をつけないといけないことは何か、今回は紹介します。
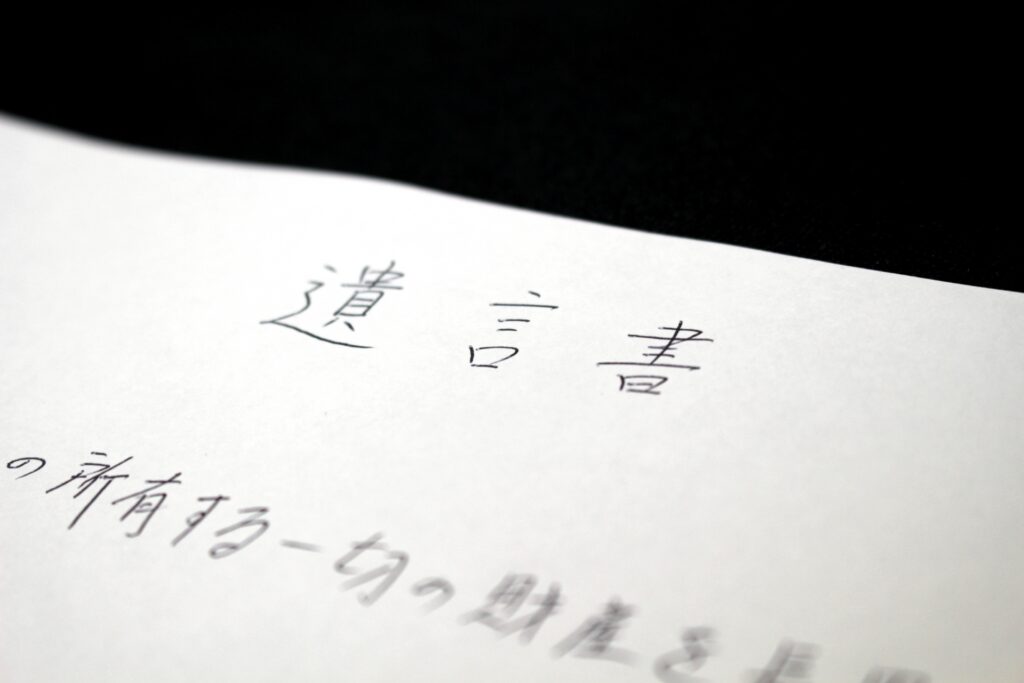
自筆証書遺言を法務局に保管できる制度があることを知っていましたか?司法書士が解説します
自筆証書遺言とはなにか?
遺言書の記載方法の一つで、すぐにでも作成することができるのが「自筆証書遺言」。
法律が改正される前までは、全て自筆で書かないと効力が発生しませんでした。
しかし、これだと、自筆証書遺言の使い勝手が悪いということで、財産目録の部分は自書で記載しなくて良くなりました。
なので、預貯金通帳のコピーとか不動産全部事項証明書とかを利用することもできますし、財産目録をパソコンで作成することもできるようになりました。
ここの改正が自筆証書遺言では大きい部分です。
とはいっても自筆証書遺言は自分の手で書くことが必要なため、まだハードルが高いのが現状。
さらに、法律に従って書かないと遺言書そのものが無効になってしまうというリスクがあります。
なので、自筆証書遺言を書くのは元気なうちに書くのが一番です。
なお、財産目録が数葉に渡る場合は、すべてのページに遺言者の署名押印が必要になるので注意してください。
自筆証書遺言を法務局に預ける方法もある
自筆証書遺言のデメリットの一つとして、紛失しやすいというのがあります。
せっかく遺言書を書いたのになくしてしまっては元も子もありません。
そこで、自筆証書遺言を法務局に預ける制度ができました。
費用はかかってしまいますが、自筆証書遺言を保管することによって、紛失のリスクはかなり減るでしょう。
ちなみに自筆証書遺言は遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認作業が必要となります。
しかし、自筆証書遺言を法務局に預かった場合には、家庭裁判所の検認は不要となります。
ただ、自筆証書遺言を家庭裁判所に預けるときにも注意が必要です。
自筆証書遺言を書く際の用紙がA4と決まっており、さらに上下左右余白を設ける必要があります。
余白は用紙の上部と右部は5ミリ以上、下部は10ミリ以上、左側は20ミリ以上と決まっています。
要件を満たさないと、せっかく自筆証書遺言を書いたのに家庭裁判所では預かってくれないということになりますので注意です。
さらに、自筆証書遺言を法務局に預けたとしても内容そのものが有効か無効かまでは判断しません。

まとめ
自筆証書遺言は元気なうちに書くこと、財産目録以外は自筆で書くこと、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができたということを是非知ってください。
また、自筆証書遺言を書くときは用紙は自由ですが、法務局に預けることを前提として書くときは用紙と余白は決まっていることを知っておいてください。
今回は
『自筆証書遺言を法務局に保管できる制度があることを知っていましたか?司法書士が解説します』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらから