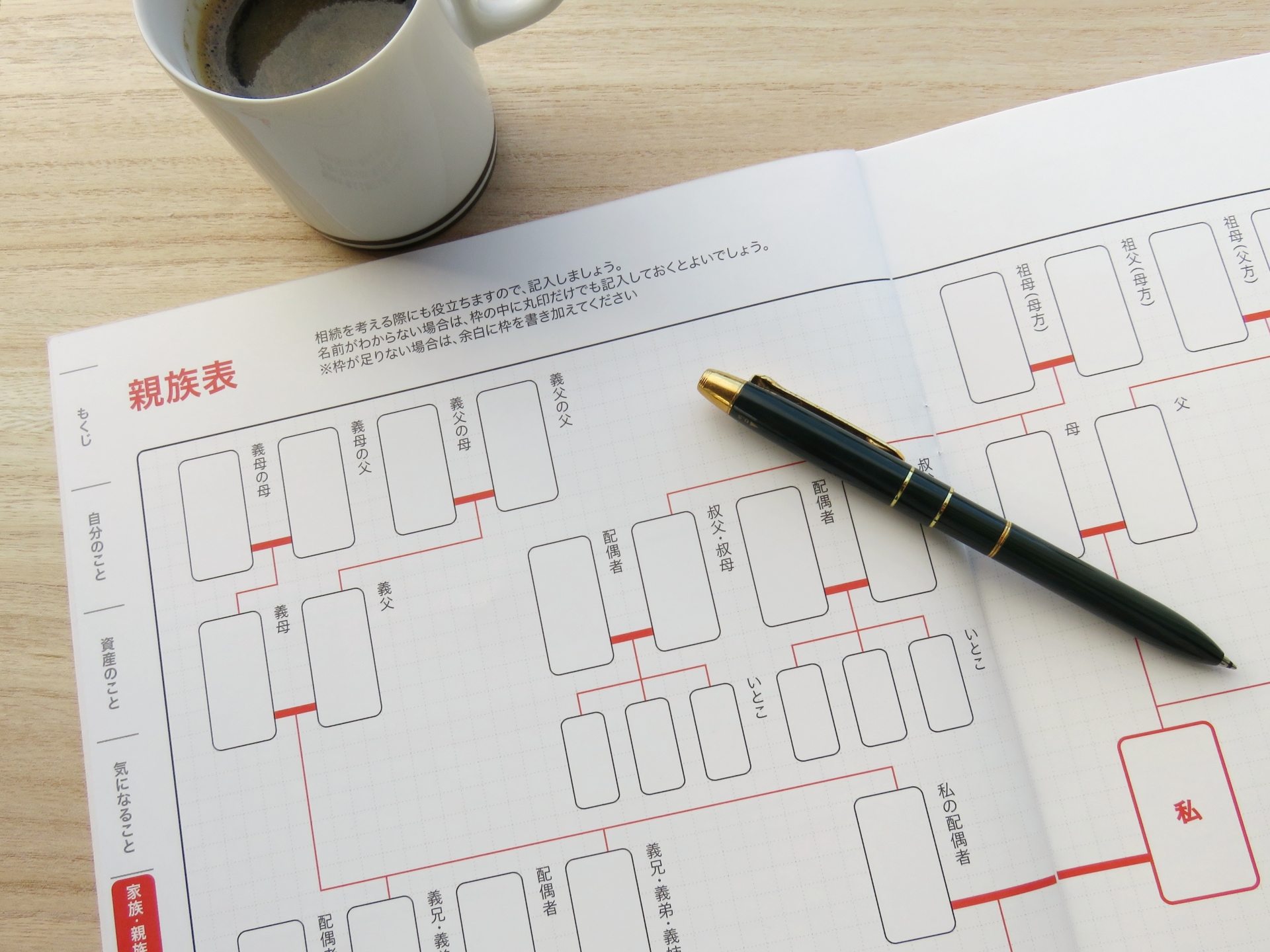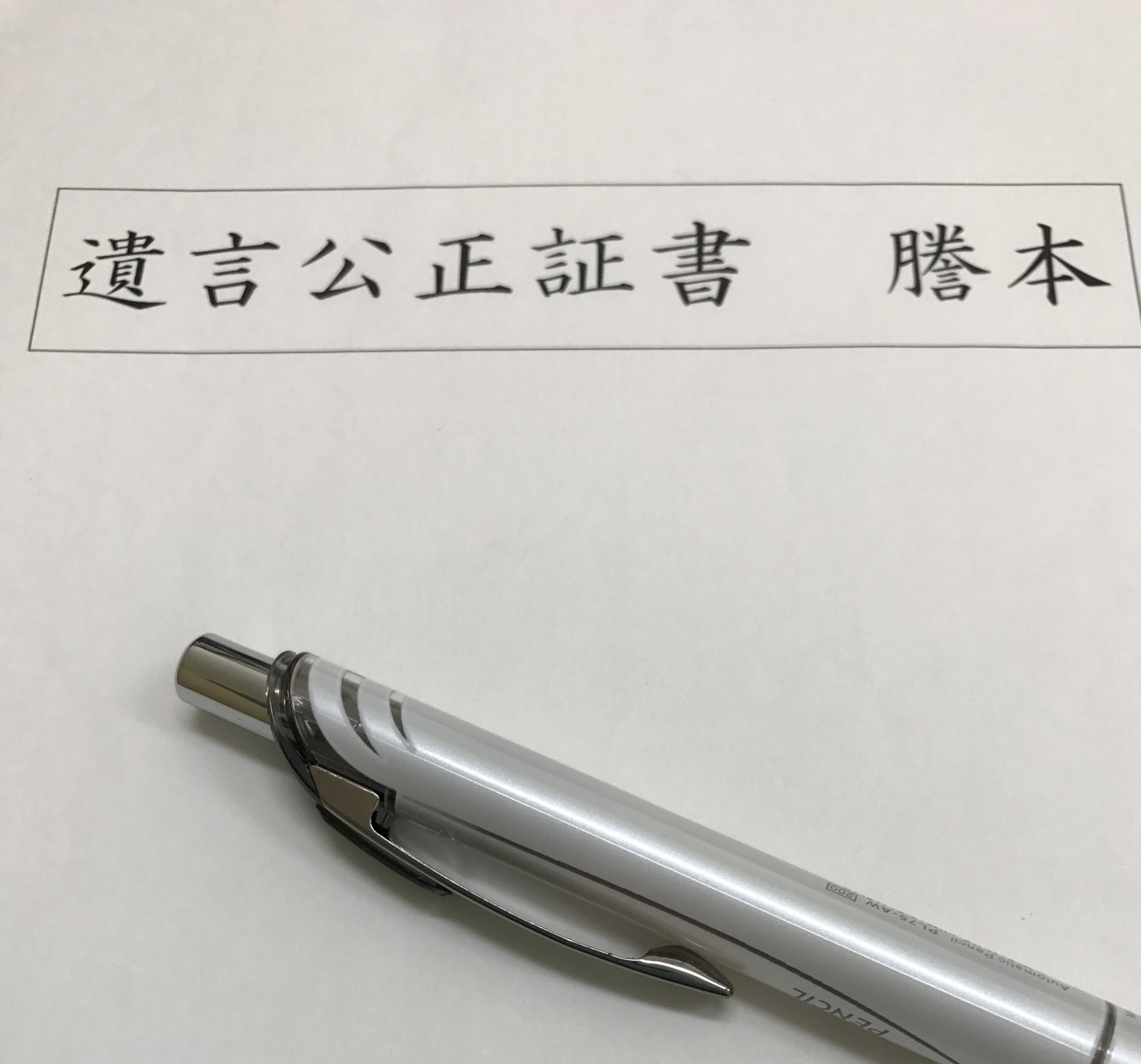東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、相続に関連する書籍が多く発売されています。
ただ、気になることはほとんどが相続開始「後」にフォーカスされている点。
相続に関する書籍は、相続開始「前」には読まれない傾向にあるようです。
ただ、私は、相続開始「前」にある程度のことをしておかないといざとなったときに、トラブルのもとになると感じています。
今回は書籍にほとんど書かれていない「家系図」と相続の関係性について触れていきます。
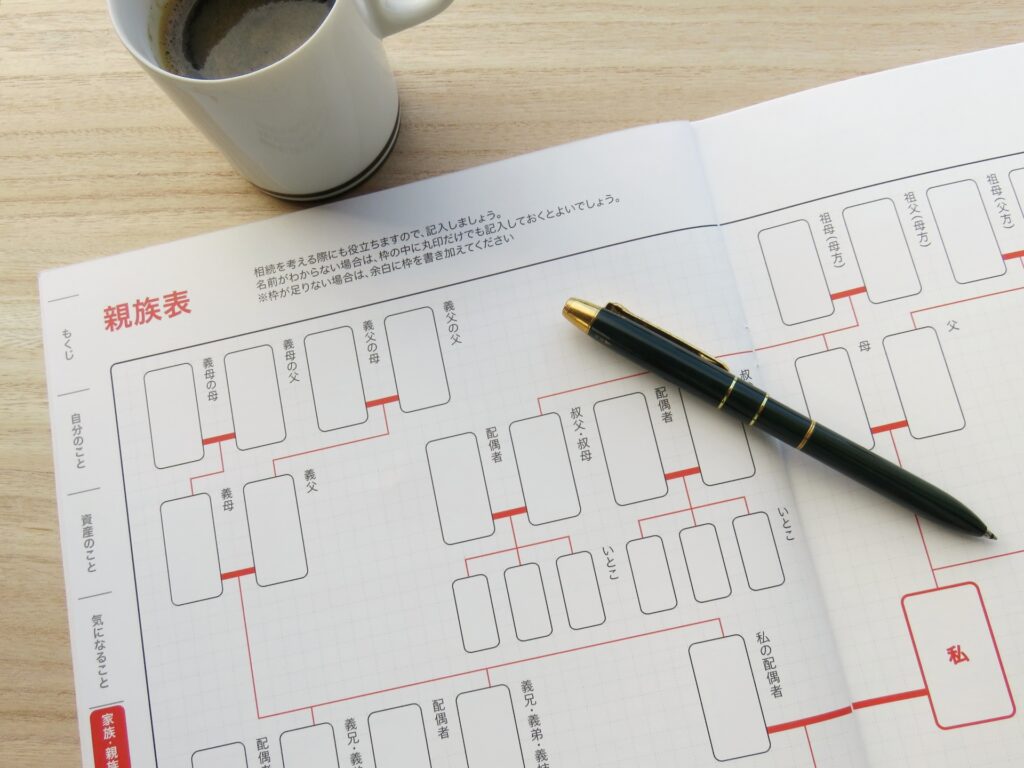
「家系図」ってそもそも何?
家系図は文字通り、自分の先祖をたどっていく行為。
現状の戸籍は、明治19年式の戸籍までは取得することは可能です。
となると生まれは江戸末期頃という人も出てきます。
相続に関しては、そこまで追う必要はありませんが、自分のルーツを知りたい方は、そこまで追うことはとりあえずは可能です。
となると、ごく一般の方だと、戸籍でたどり着けることができるのは江戸末期生まれ(慶応生まれ)くらい。
自分から見て4代くらいまでは追うことが可能です。
戸籍は明治5年式のものもありますが、現状は取得できず、明治19年式のものまで取れれば、相続準備対策の家系図の準備としては十分です。
もし、それ以上遡りたい方は、菩提寺の過去帳か宗門人別帳で探すことになります。
自分のルーツを知りたい方はぜひやってみてください。
なぜ「簡易家系図」を作ると相続対策となるのか?
私は相続対策の一環として「簡易家系図」の作成を推奨しています。
自分にとっての相続人を知ることは、自分が亡くなったときに誰にどれほどの財産がいくのか(法定相続分どおり)が分かるからです。
養子にいっても、実子であれば原則あなたの相続人になります。
さらに、再婚して、再婚前の間に子供がいれば、前婚の配偶者は相続人にならなくても、その子供は相続人となります。
となると、自分が亡くなったときに、後妻やその子供と前妻の子供が相続人となります。
全く面識がないと、相続人間のお話し合いがなかなかまとまらず、相続手続きに時間がかかることが予想されます。
場合によっては遺産分割の調停なり裁判まで発展することもありえます。
そのようなことを事前に知っておくだけでも重要で、先に連絡をとったり、対応が可能になるのです。
いくら相続に関する一般書籍がでても、ここを知らないと遺言書も書けないですし、財産の分け方とかあなたの思いとかも伝えることができないのです。

まとめ(今日の気づき)
遺言書を書くと言っても、いきなり書くのはハードルが高い。
自分の歴史を知る「簡易家系図」から始めてみる。
「簡易家系図」から誰が相続人になるのかを知る
今回は
『「簡易家系図」から相続を考える まずは相続準備のハードルを下げる 江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関する最新ブログはこちら
参考書籍
 | わたしの家系図物語 渡辺 宗貴 時事通信出版局 2019年03月26日頃 売り上げランキング :
|