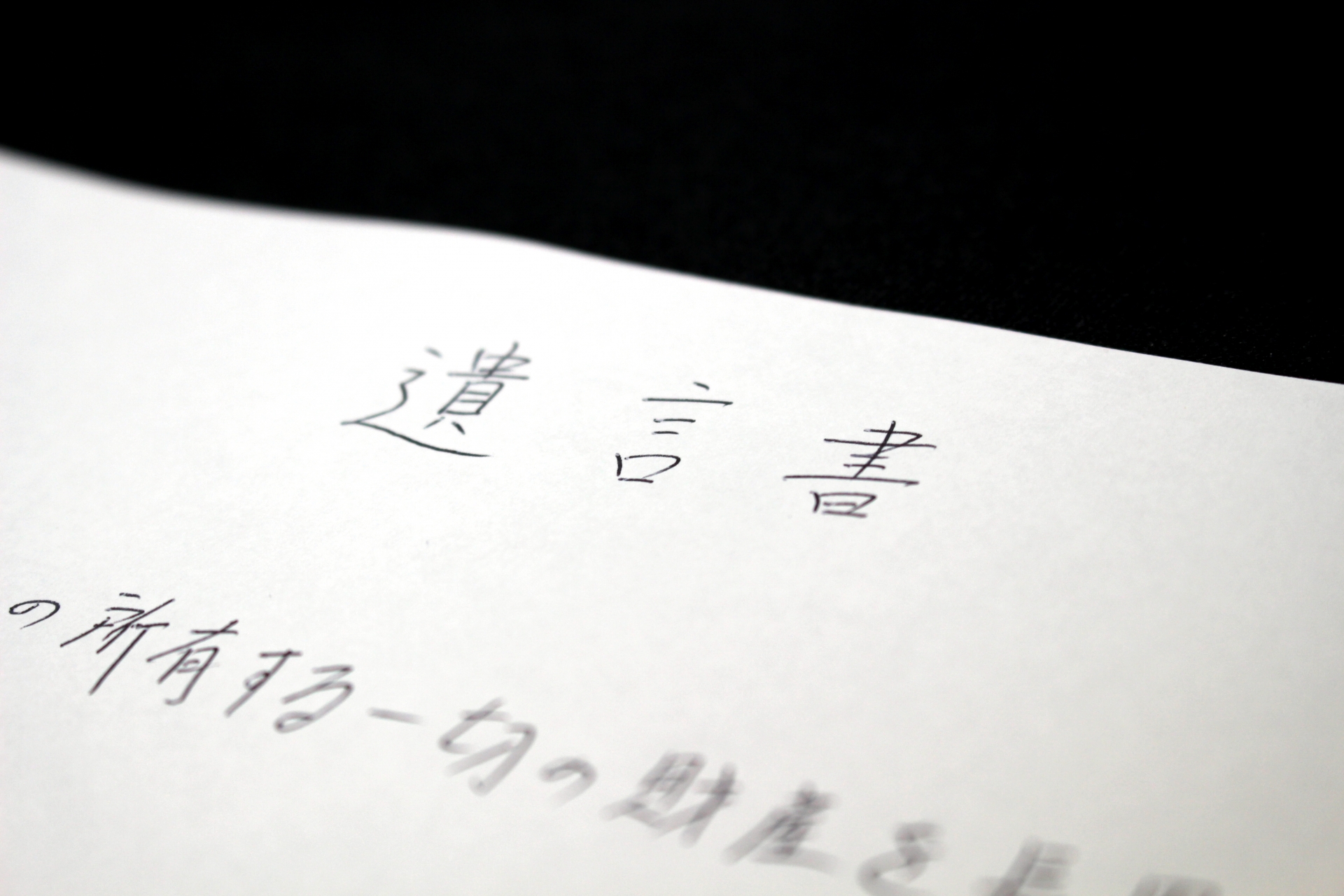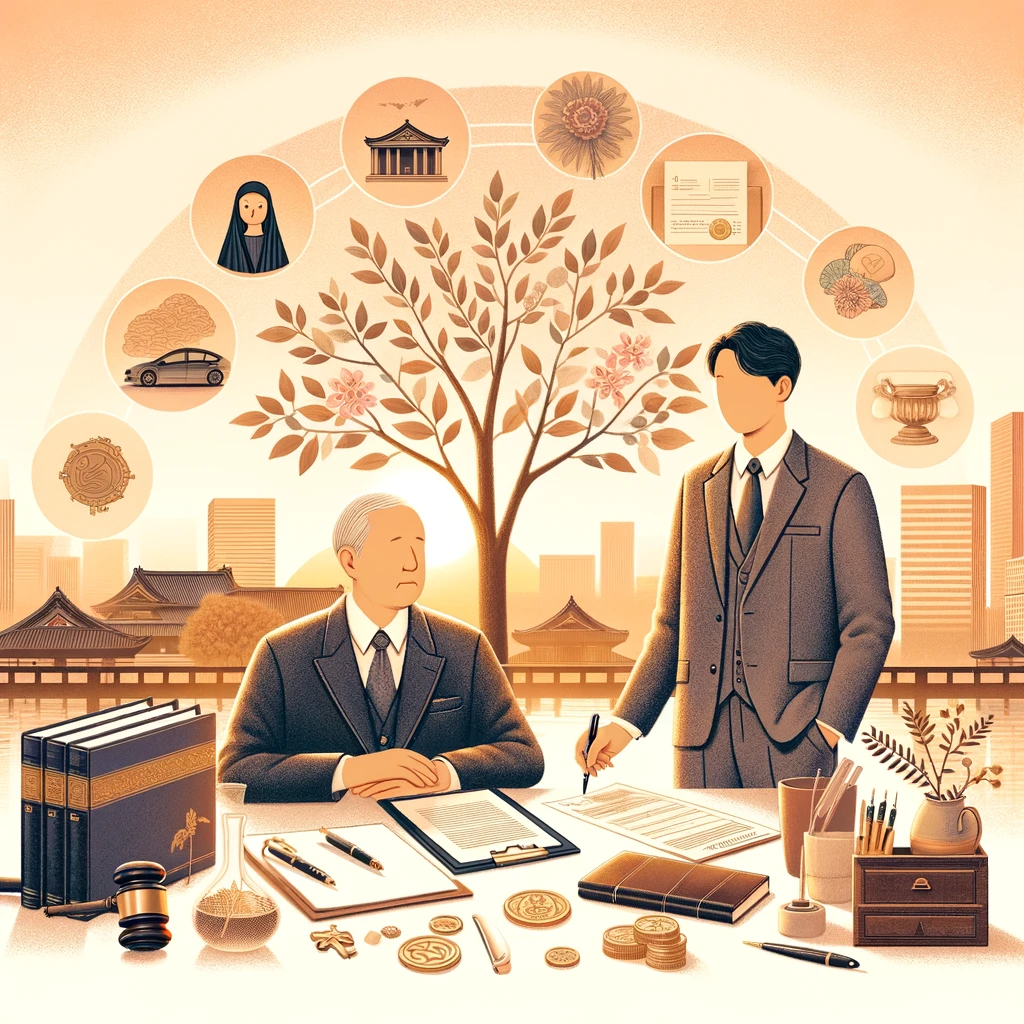東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
高齢化社会が進み、遺言を残しておくことの重要性は聞いたことがある人は多いでしょう。
ところで遺言書を書く際に意識しなければならないことは「誰が相続人か」ということ。
相続人は誰になるのかというところを今回は紹介します。
そこから「簡易家系図」を書いていきましょう!
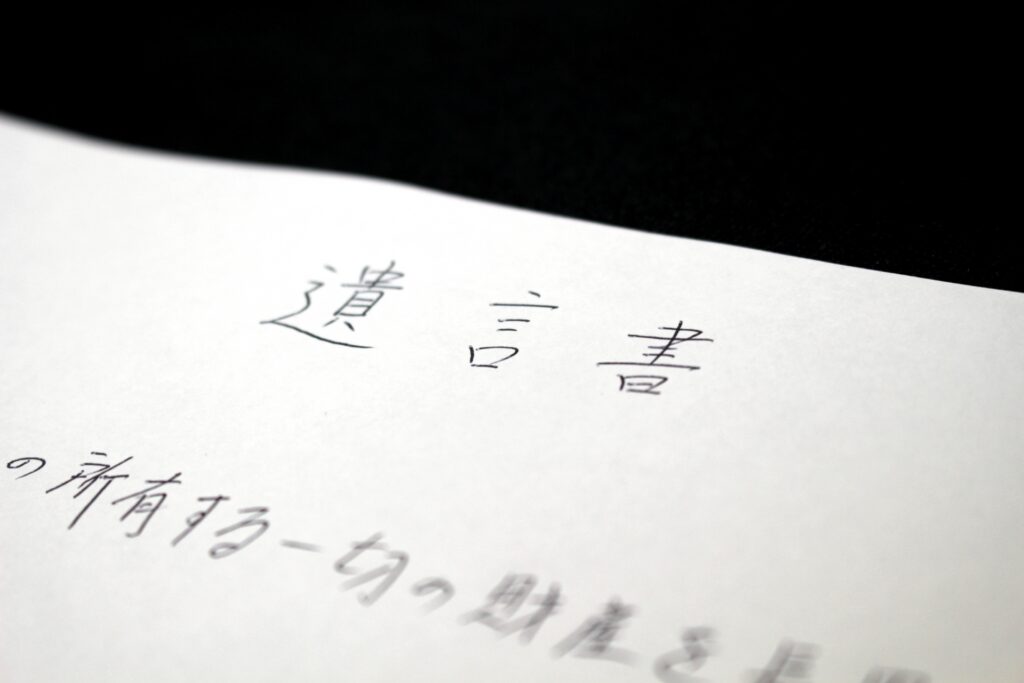
「簡易家系図」を作るに当たり まずは誰が相続人になるのかを知ること
令和の新時代、核家族化も進み、家族関係も複雑になりつつあります。
昔のように子供や兄弟姉妹がたくさんいるときも相続は面倒です。
さらに、この時代は離婚もあり、より家族関係が複雑になっているような気がします。
思いもよらない方が相続人となったりすることもしばしば。
まずは、あなたから見た推定相続人を遺言書を書く前に調べておきましょう。
推定相続人は誰かをしっかり把握しておきましょう 配偶者
まずは、配偶者。
これは優先的に相続人となります。
とはいっても、最近は事実婚なり、内縁の配偶者もいます。
ただ、事実婚や内縁の配偶者は相続人にはなりません。
あくまでも法定婚で戸籍に入っている配偶者が相続人となります。
当然ですが、離婚した配偶者は相続人にはなりません。
もし、事実婚や内縁の配偶者に財産を引き継いでもらいたい場合は、遺言なり生前贈与などの対策が必要です。
推定相続人は誰かをしっかり把握しておきましょう 子
第一順位として子供が相続人となります。
子供が自分よりも前に亡くなっている場合は孫が代襲して相続人となります。
子供の相続分は人数の頭割りとなります。
そこで注意なのは、前婚の配偶者は相続人となりませんが、子供は相続人となること。
ということは、今前婚の子供と疎遠であると、相続開始後思わぬ事態も想定されます。
なので、前婚の子にも遺留分があるので、遺言書を書くときはその子供にも配慮しておかないと、相続開始時に揉めてしまいます。
推定相続人は誰かをしっかり把握しておきましょう 直系尊属 兄弟姉妹
子供がいない場合は直系尊属、自分の親や祖父母が相続人となります。
そして、子も直系尊属がいないときに兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹の相続人が意外とややこしい。
兄弟姉妹には遺留分がないので、そのあたりは気が楽なのです。
しかし、すでに兄弟姉妹がなくなっている場合は甥や姪に代襲相続されます。
なので、自分も知らない人があなたの相続財産を承継することもあります。
兄弟姉妹に相続分が行くような場合には、遺言書を書くことは必須で、付言事項でその思いをしっかり書いていくことが重要になります。
簡易家系図をつくる
これは以前のブログでも書きましたが、簡単な家系図を書いてから遺言書を書くことをおすすめします。
誰が相続人であるかわかるだけでなく、その人に自分の財産を託したい思いもわかるからです。
その思いをしっかりと付言事項で書くことが重要です。
家系図といっても先祖代々まで書く必要はなく、自分の祖父母あたりまで遡れれば十分です。

まとめ
簡易家系図を書くことで相続人が誰であるかがわかるので、遺言書も書きやすくなります。
誰が相続人かわからない状態で遺言書を書いてしまうとあなたの財産を託したい人に十分行き渡らない可能性もあります。
相続開始後の無用なトラブルを避けるため、ぜひ遺言書を活用しましょう。
今回は
『「簡易家系図」を使ってスムーズな相続を実現する方法を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらから