債権法改正 保証に関する改正部分は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2020年4月1日、民法の債権法分野の改正が行われました。
私達の生活にも影響を及ぼす今回の民法の債権法改正。
今回は「保証」の改正について書きます。
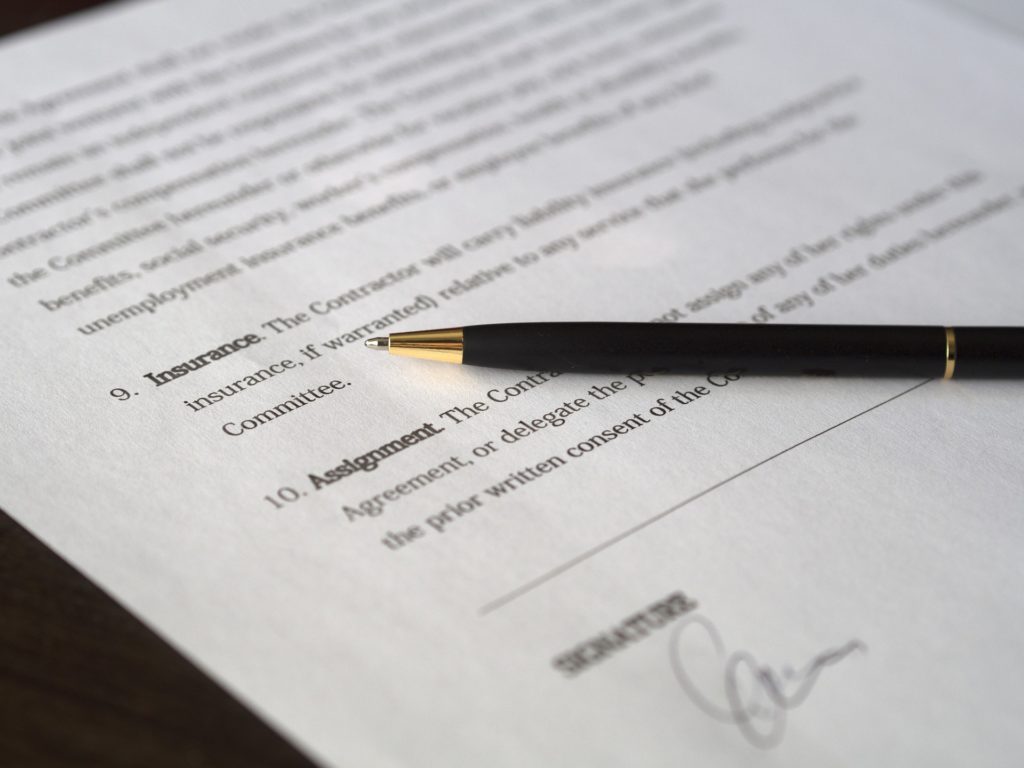
債権法改正 保証に関する改正部分は?
「保証」って何?
保証っていう言葉を多くの方は聞いたことがあるかと思います。
保証するには契約が必要です。
主債務者がお金を払えなくなったときに、主債務者に変わって保証人が支払う必要があるのが保証です。
ただ、多くの場合は「連帯保証」で保証人の財産があるかどうかに関わらず、債権者は保証人に債務の支払いを請求できたり、財産の差し押さえができたりします。
なので、保証契約を締結する際は、主債務者に安易に頼まれたからという理由だけで行うのはリスクが高いのです。
保証に関しては、2つの大きな改正があります。
その1 根保証契約について
根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。
怖いのは、締結時にどのくらいの金額を負担するのか分からないので、将来予想もしなかった債務を負担しなければならなくなるリスクもあります。
なので、今回個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払う上限額「極度額」を定めなければ契約そのものが無効になります。
こちらは書面により明確な金額で極度額を定めなければならないので、これに反した場合は、根保証契約自体無効になります。
あとは、個人が保証人となる根保証契約については、破産や主債務者または保証人が亡くなったときはその後に発生する主債務は保証の対象外となることが明確化されました。
いずれにしても、根保証契約を結ぶ場合は、いくらまでを上限に債務を負担するのかを確認するようにしてください。
その2 公証人による保証意思確認手続の新設
保証契約を簡単に結んでしまうと、後々リスクを負ってしまうことは先程書きました。
更に怖いのは、主債務者が事業用の融資を受ける場合に、その事業に関係していないあなたが保証人になってしまうこと。
そこで、その事業に関係のない個人が事業用融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認を経る必要があります。
なお、個人であっても、以下の場合には公証人の保証意思の確認を経る必要はありません。
これらの者は、事業と深い関係を有する方々だからです。
- 主債務者が法人である場合 その法人の理事や取締役、議決権の過半数を有する株主等
- 主債務者が個人である場合 主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
もし、あなたの知り合いで事業の融資を受ける際に、友人が保証人となる場合には、公証役場で保証意思の確認を経てからでないと金融機関からの融資はできないことになります。
実務ではかなり影響が出てきそうな部分です。
まとめ
今回は民法債権法改正の「保証」について書きました。
なお、今回は、法務省から公表されているものを参考にブログを書きました。
2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります(法務省パンフレットより)
今回は
『債権法改正 保証に関する改正部分は?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
賃貸借等の改正に関するブログはこちらから
2020年4月1日 民法債権法・相続法改正があります!(賃貸借・配偶者居住権を中心に) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
| Q&A改正債権法と保証実務 |
||||
|


