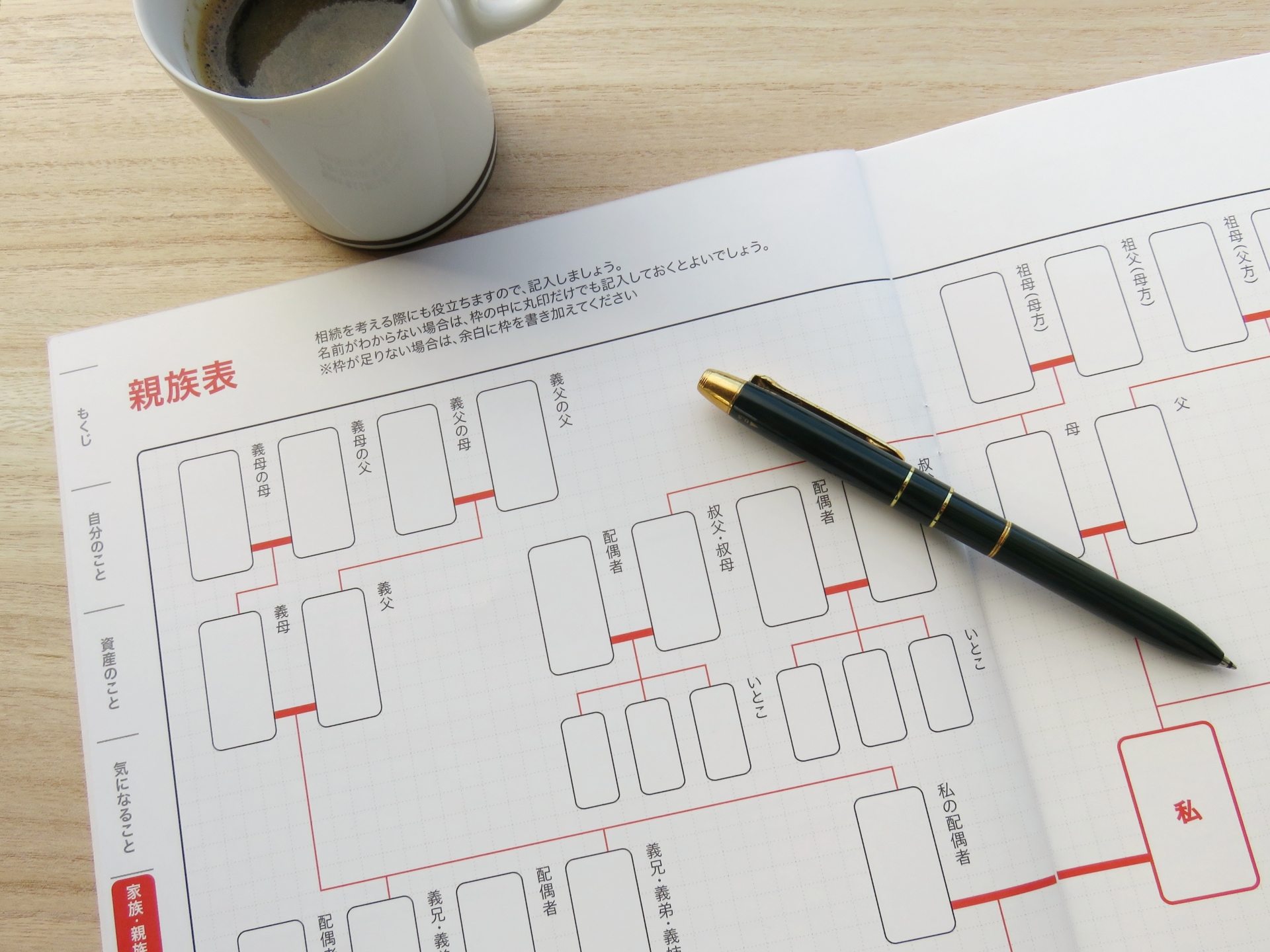東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
親子で考える「生前相続対策」。
なかなか子供が相続対策のことを話しても親はなかなか聞く耳を持たないのが現実です。
今回は親子で考える「相続対策」の一つ、相続税の概略について考えていきましょう。

相続税の計算や申告は自分でもできるのか?
よく「相続については費用をかけたくないから自分ですべてやりたい」という方がいます。
登記にしても預貯金の手続きにしても、相続税の申告にしても全部自分でする方を見かけます。
しかし、登記申請でも不備があったり、相続税の申告に至っても不備があり、あとが大変だったということも耳にします。
相続税の計算や申告は自分でもできます。
しかし、計算違いや申告ミスがあり、結局は自分ですると時間も費用もかかり疲弊する…
というのであれば始めから専門家を入れたほうがいいのです。
費用もかからないし自分でもできると思っている人ほど失敗している事例を多く見かけます。
なので、相続税のことも含めて、生前対策は親子と専門家と二人三脚で取り組むべきです。
生前対策の一環として相続税の計算方法を知っておく
相続の生前対策で、まずは相続人は誰になるのかを知っておく。
これがスタートラインです。
さらに、親の財産が多そうな場合、あらかじめ相続税のことを気にすることが重要です。
相続税全体像を知っておくことで「遺言」を作成するときに財産をどう分けるのかを考える切っかけにもなるからです。
さて、相続税の計算方法ですが、大まかに3段階に分けます。
1 課税遺産の総額を計算
生前対策の場合は、現状ある不動産や預貯金などのプラス財産、借金やローンなどのマイナス財産をピックアップします。
その時に役立つのが「エンディングノート」です。
エンディングノートにすべての財産を書き出すことで、課税遺産が何になるかをイメージできます。
さらに保険金や退職金などの「みなし相続財産」も計算に入れてください。
なお、仏壇の購入費用は非課税扱いとなります。
2 相続税の総額を算出
1でざっくり出した遺産総額から基礎控除を差し引きます。
基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
その段階でマイナスになれば相続税は現状はかからないと思っていいです。
ただし、相続税は現状かからなくても生前相続対策はしてください。
ざっくり出した遺産総額から基礎控除を引いた額が「仮の遺産総額」となります。
その仮の遺産総額を法定相続分で取得したものと仮定して、各相続人の相続税額を求めます。
その合計が生前対策時の相続税の総額となります。
なので、相続人が誰になるのかが非常に重要になるので、生前対策ではまずは相続人の調査が肝になります。
3 各相続人の納税額を算出
2で求めた総額をもとに各相続人が取得する財産を計算します。
その時に利用できる控除があれば控除額を差し引いて、各々の納税額を算出します。
生前対策から専門家の活用を!
先程のところの繰り返しになります。
「遺言書」の作成段階の前に、その地点での相続税がどうなるのかを知っておくことが大事になります。
自分でも相続税の計算はできますが、複雑で間違えてしまうこともあります。
なので、生前対策の段階から相続税がでそうだと思ったら税理士をいれて対策を取ることも大事です。
司法書士・行政書士は「遺言」のサポート、税理士は「税務」のサポートをすることができるので、ぜひ専門家を活用してください。
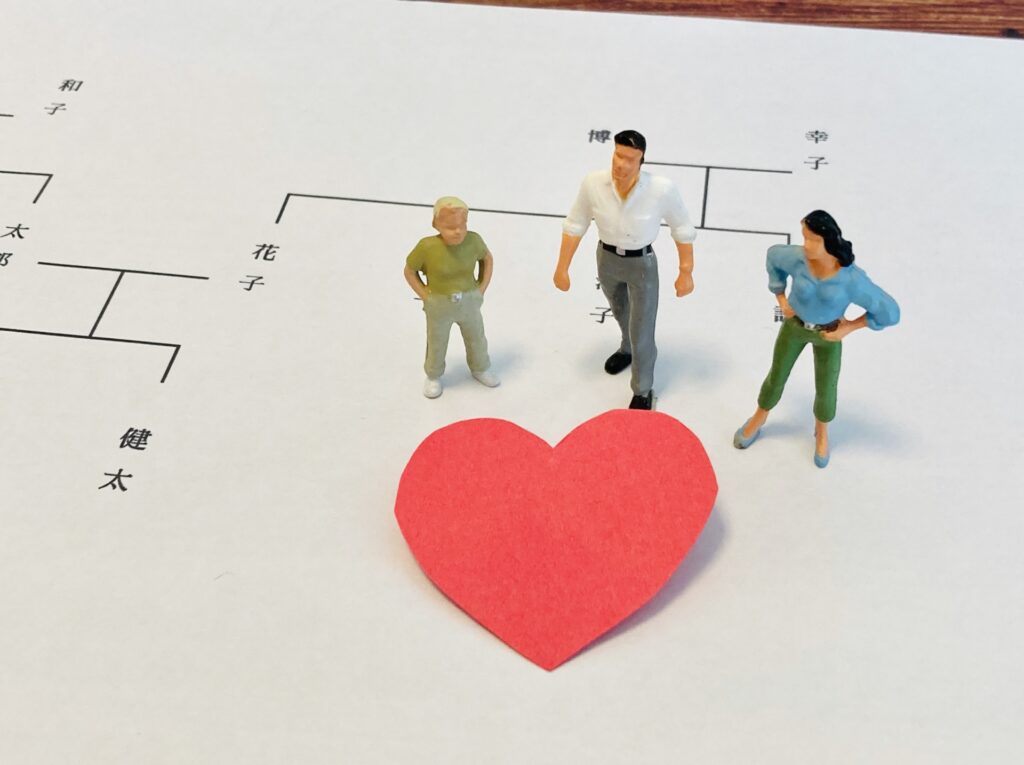
まとめ
生前対策で大事なのは、相続開始後の問題をいかに減らせることができるか。
事前に相続人は誰で、相続税はどうなるのかを知ることで対策の幅が広がります。
まずは、親子でしっかり「生前の相続対策」を考えていきましょう。
今回は
『親子で共に考える生前相続対策:相続税対策の基本』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら