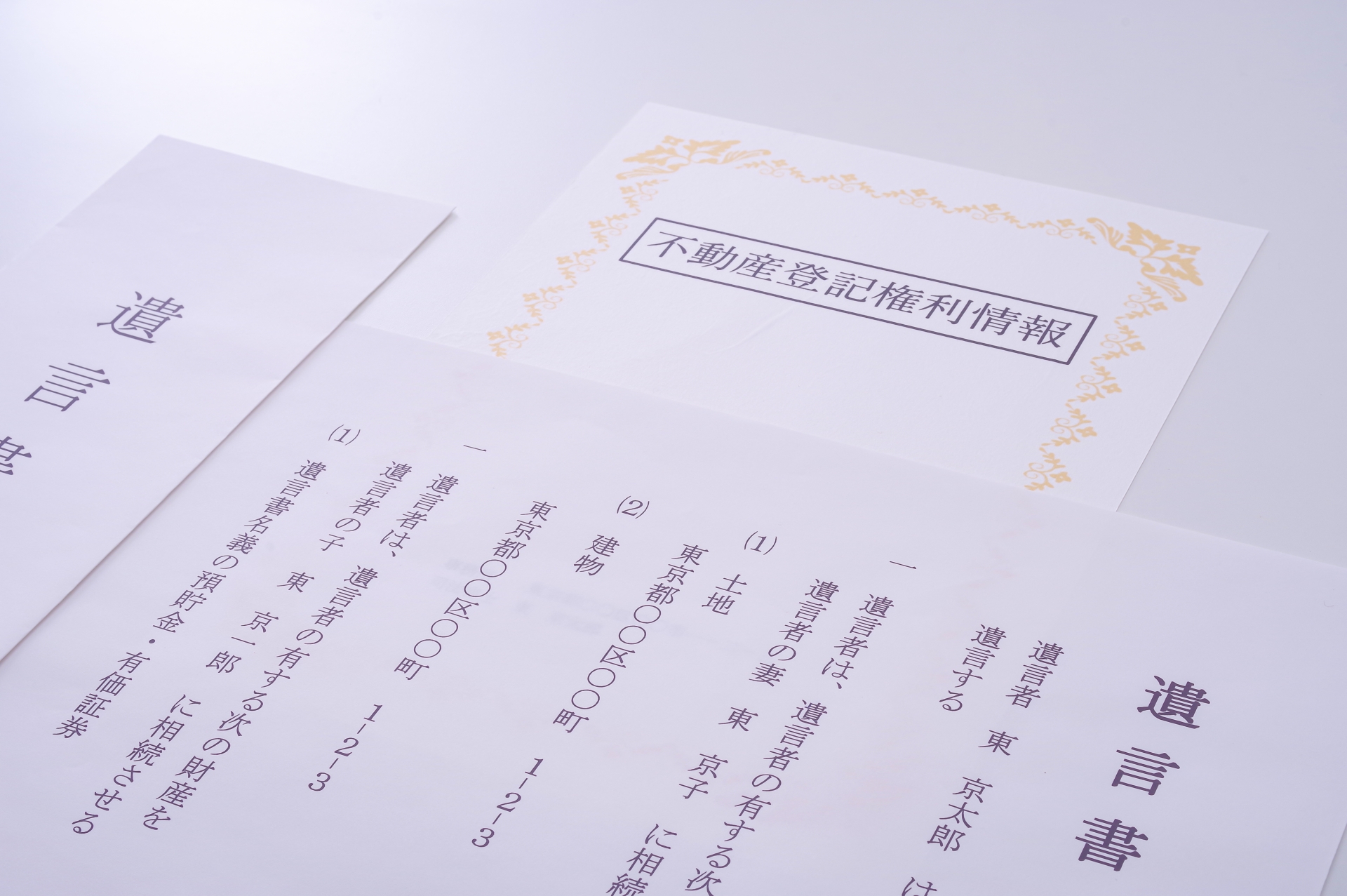東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
遺言書を書くことは、その後の相続人間の揉めごとを少なくするというメリットがあります。
とはいっても遺言書は万能ではないことは事実。
遺言書がもとで争いになることがあります。
では、どんな場合、遺言書で揉めてしまうのかを書いていきます。
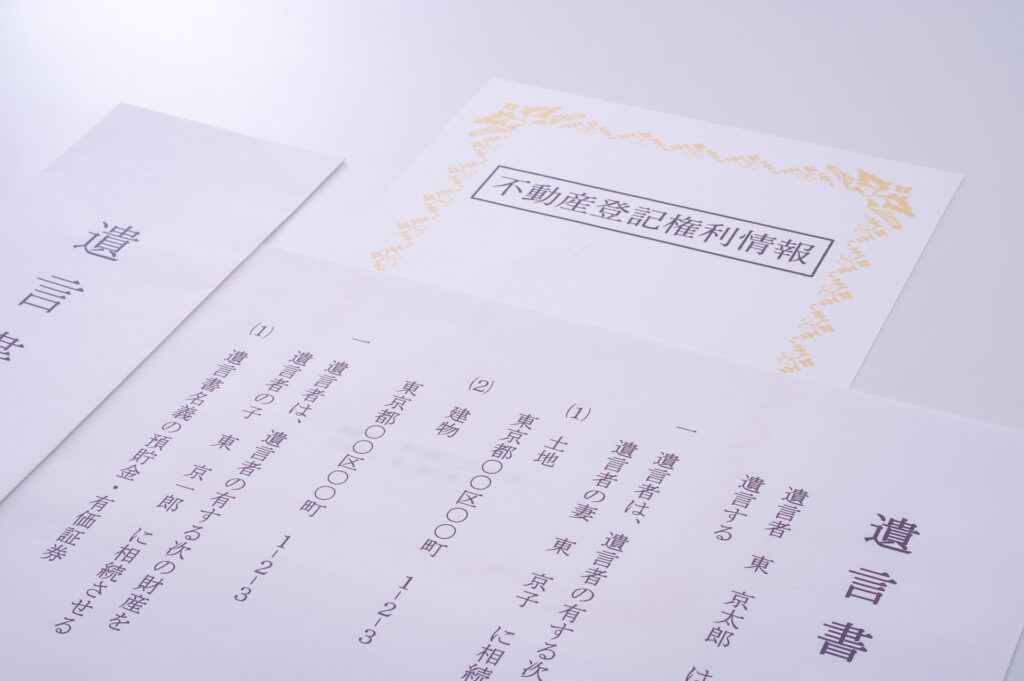
遺言書で揉めてしまう要因 遺言能力があるかどうか
せっかく「遺言書」を書いたのに揉めてしまうことはあるのでしょうか?
実際に「遺言書」の有効・無効を争う裁判も起きています。
なぜ、「遺言書」で揉めてしまうのでしょうか?
一番揉めてしまう要因は、遺言者が遺言能力があるかどうか。
遺言は遺言能力があれば、することができます。
認知症の場合であっても、事理弁識能力が一時的に回復していれば遺言書を書くことができます。
ということは、認知症の人が一時的に遺言能力を回復した場合に書いた遺言書だと揉めるというリスクは非常に高いことになります。
後見人とか面倒を見ている親族が近くにいる人に有利な遺言書の記載になるリスクは高いです。
自筆証書遺言の場合は、間違いなく認知症の人が遺言能力できるまで回復したときに書いた場合は揉めます。
公正証書遺言でも揉めてしまうのか?
公正証書遺言の場合、公証人作成で証人が2名いるから揉めないのではないかと思っている方。
実は「公正証書遺言」でも裁判沙汰になることがあります。
公正証書遺言で揉める場合の一例として、遺言者が認知症で判断能力が一時的に回復した場合に作成した場合があります。
つまり、内容もさることながら、遺言そのものが効力がないという争い。
遺言者が自分の行為の意味や遺言の結果を理解しているか、そしてその遺言が自分の自由な意思に基づいているかが問われます。
遺言そのものがないとなると遺産分割協議で相続人が話し合って財産を分けないといけないことになり、問題解決まで時間がかかります。
公証人が立ち会ってしっかりと本人確認をしていること、証人2人が立ち会っていることなどから考えても無効にするのは至難の業。
なので、遺言の無効を主張する者が証拠をしっかり収集する必要があり、それが結構面倒なのです。
裁判例でも、公正証書遺言が無効になるかどうかは、諸事情で判断している傾向があるようです。
公正証書遺言を作ろうとしている遺言者の年齢が高いだけで無効になることは殆ど無いでしょう。
とはいっても、高齢者の遺言書の作成は、色々問題があることは意識してください。
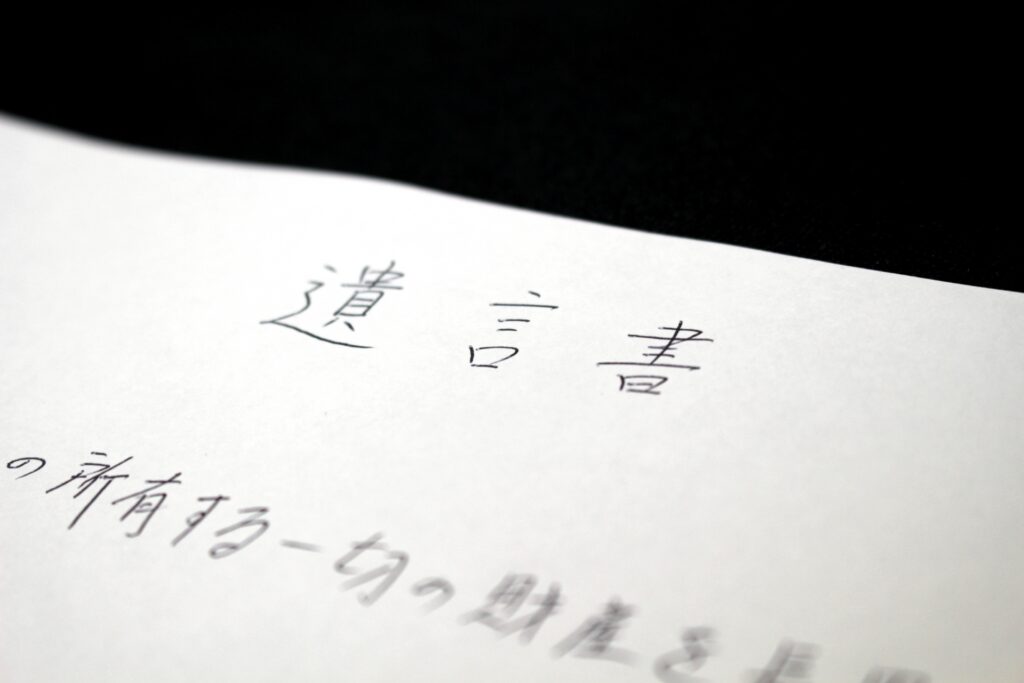
まとめ
認知症になっても遺言書作成は一応は可能だが揉めてしまうことが多いことは意識してください。
あらかじめ揉めそうなことが分かったら、遺言書だけでなく、家族信託や任意後見とかも活用することをおすすめします。
そのうえで元気な状態で生前対策を行うことが何より大事になります。
今回は
『相続争いを未然に防ぐ:遺言書作成時の遺言能力を巡る注意点を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらから