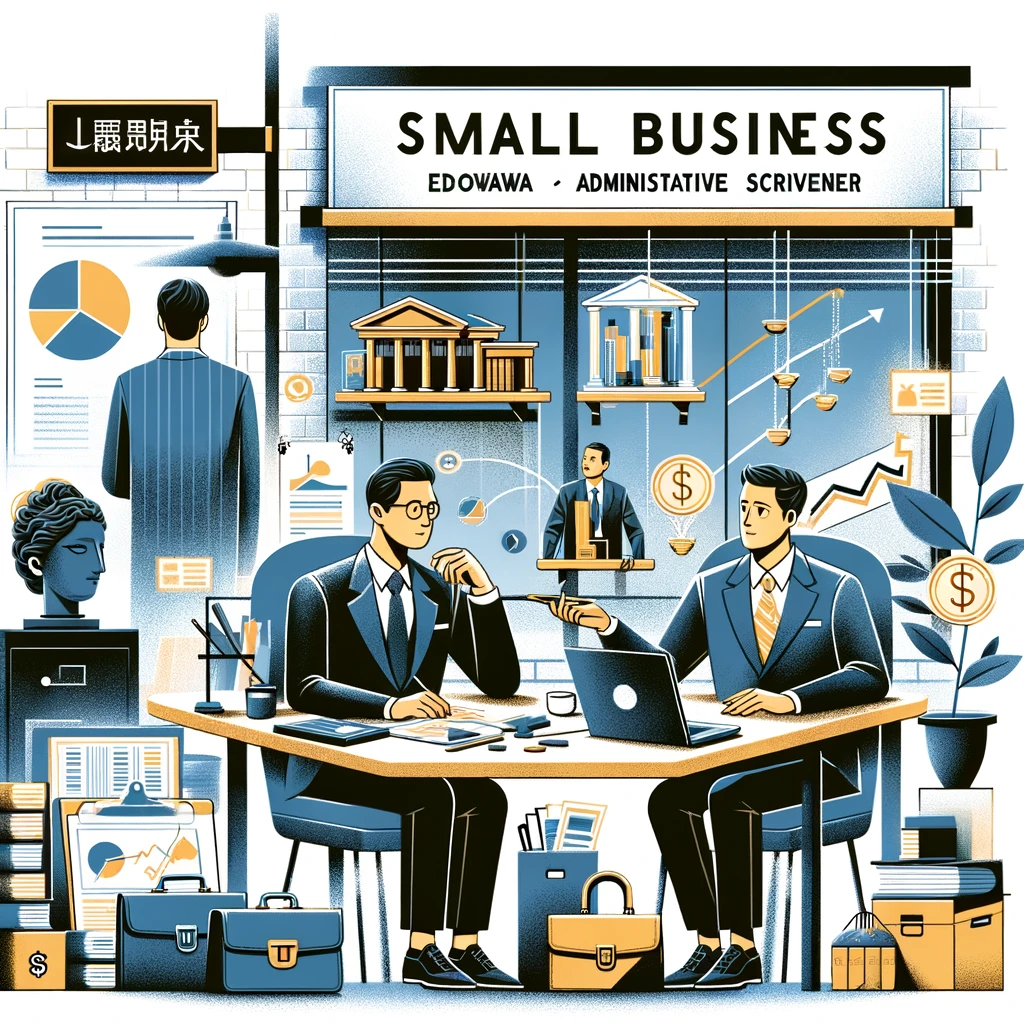はじめに
私の業務の柱の一つに「相続」「事業承継」「小さな会社の企業法務」の分野があります。
ひとり会社の場合「相続」と「事業承継」は綿密な関係にあります。
今回は、「事業承継対策」のうち非上場株式等の贈与税・相続税の猶予制度の概略について紹介します。
なお、ブログの著者は司法書士・行政書士のため、今回の内容は税務の問題が大きいです。
より具体的な詳細は、税理士などの専門家にご相談ください。

目次
「納税猶予制度」の概略を簡単に紹介
納税猶予制度とは、特定の条件を満たす場合に、税金の支払いを一時的に先延ばしにすることができる制度です。
この制度は主に、事業承継の際に重要となります。
特に、非上場の株式などの場合に適用されることが多いです。
例えば、ある会社の経営者が後継者に会社の株式を贈与または相続させる場合、通常はその株式に対して贈与税や相続税が発生します。
しかし、納税猶予制度を利用すると、これらの税金の支払いを猶予(延期)できます。
これにより、後継者は大きな財務的負担なしに経営権を引き継ぐことができます。
ただし、この制度を利用するためには、特定の条件を満たす必要があります。
たとえば、非上場会社の株式であること、一定の雇用を維持すること、事業を継続することなどが条件に含まれる場合があります。
また、一定期間後には税金を支払わなければならないこともあります。
この制度は、事業のスムーズな承継を促進し、経営者の死亡や引退に伴う財務的な困難を軽減するために非常に有用です。
事業承継における「特例認定承継会社』とは?
この後の文章で「特例認定承継会社」という言葉がでてくるので、ここで紹介しておきます。
「特例認定承継会社」とは、事業承継において特定の税制上の優遇措置を受けることができる会社のことを指します。
この特例認定を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
これらの要件には、例えば、会社の規模、業種、経営状況などが含まれる場合があります。
特例認定を受けた承継会社は、事業承継に際して発生する贈与税や相続税の納税猶予や免除の特例を受けることができます。
これにより、経営者が会社の株式を後継者に引き継ぐ際の財務負担を軽減し、事業のスムーズな承継を実現することが可能となります。
特例認定承継会社の認定を受けるためには、通常、事前に事業承継計画を作成し、都道府県知事などの公的機関に申請し、承認を受ける必要があります。
この計画には、事業承継の方法、経営計画、雇用維持計画などが含まれることが多いです。
非上場株式等の贈与税の納税猶予制度(一般措置)
まずは非上場株式等の納税猶予制度の紹介です。
今回は一般措置についてです。
会社の後継者に株式を贈与して経営権を渡すのは大事なこと。
しかし生前贈与で立ちはだかるのは「贈与税」。
受贈者が贈与税を負担するのはかなり負担が重く、事業承継対策の足かせとなっていました。
そこで後継者(受贈者)が、前経営者(贈与者)から贈与により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を全部または一定数以上取得し、その会社の経営を承継する場合には、その非上場株式等(発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分)に係る贈与税の全額について、納税が猶予される制度です。
ただし、雇用確保要件(承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要)や事業継続が困難になったときのリスクが残ります。
非上場株式等の相続税の納税猶予制度(一般措置)
次に非上場株式等の相続税の納税猶予制度の一般措置について紹介します。
後継者(経営承継相続人)が、前経営者(被相続人)から相続等により、都道府県知事の認定を受ける非上場株式等を取得し、その会社の経営を承継する場合には、その非上場株式等(相続開始前から所有していたものを含めて発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税について、納税が猶予されます。
納税猶予制度の特例(特例措置)
特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与または相続等により特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その非上場株式等のに係る贈与税または相続税の全額について、納税が猶予されます。
また、特例後継者については、特例認定承継会社の代表者以外の者からの贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、納税猶予の対象となります。
国税庁のホームページより特例措置と一般措置の比較の表を紹介します。
| 事前の計画策定等 | 特例承継計画の提出 (平成30年4月1日から令和6年3月31日まで) |
不要 |
| 適用期限 | 次の期間の相続等・贈与 【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】 |
なし |
| 対象株数(議決権に制限のない株式等に限る) | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 100% | 相続等: 80%、贈与:100% |
| 承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 弾力化 ※雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。 |
承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
| 事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 | なし (猶予税額を納付) |
| 相続時精算課税の適用 | 60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与 (租税特別措置法第70条の2の8等) |
60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 (相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6) |
贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度の関係
前経営者の死亡の日まで贈与税の納税猶予の適用を受けていた非上場株式等については、相続開始によって、納税が猶予されていた贈与税額が免除されます。
この非上場株式等はすでに贈与を受けていますが、相続税の計算上、被相続人(前経営者)から相続または遺贈によて取得したものとみなされ、相続税の課税対象(相続財産に算入される価格は贈与時の価格)となります。
そのとき、都道府県知事の確認を受けた場合には、相続人は非上場株式等(相続時点では非上場株式等に該当する必要はない)の相続税の納税猶予を適用することができます。

まとめ
今回は、非上場株式等の贈与税・相続税の猶予制度について紹介しました。
税務の専門的な部分が絡むことなので、事業承継始める地点で税理士と相談することをおすすめします。
今回は
『経営者のための税務戦略:非上場会社株式の贈与・相続税猶予制度を解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください