東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の業務の柱の一つに「相続」「事業承継」「小さな会社の企業法務」の分野があります。
ひとり会社の場合「相続」と「事業承継」は綿密な関係にあります。
今回は、「事業承継対策」を中心に紹介します。
なお、ブログの著者は司法書士・行政書士のため、より細かく税務の内容を知りたければ、税理士などの専門家にご相談ください。
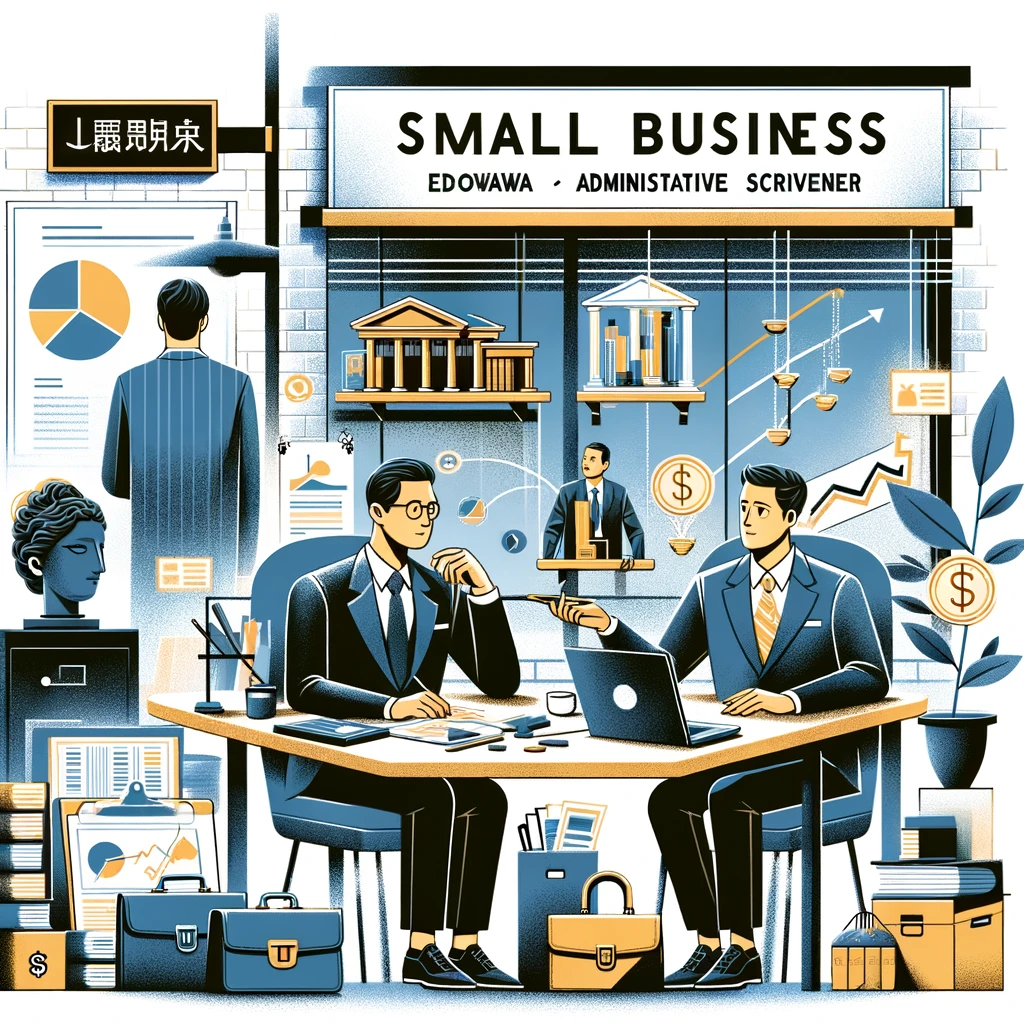
事業承継対策 なぜ必要なのか?
改めて、なぜ事業承継対策が必要なのかを書きます。
中小零細企業では、経営者の死亡によって会社経営は困難になります。
特にひとり会社の場合は、ますます会社経営は厳しくなります。
そこで、会社そのものを次世代に継がせるのかどうかを早めに判断することが必要です。
事業承継対策は「経営」の引き継ぎだけでなく、中小零細企業では「相続」も絡むので、大手企業のような「会社の引き継ぎ」よりややこしくなることを意識してください。
事業承継対策の具体的方法
事業承継対策の具体的方法として、今回は「株価の引き下げ」「株式数対策」「納税資金対策」の3つに焦点を絞ります。
事業承継対策の具体的方法:株価の引き下げ
なぜ株価を引き下げるといいのか?
「株価の引き下げ」とは、会社の株式の価値を意図的に低く評価することです。
これは、相続や贈与の際に発生する税負担を軽減するために行われます。
これにより、株式の相続税評価額が低くなるため、税金の負担が軽減されるのです。
具体的に、株価の引き下げについては方法として、2通りあります。
ただ、むやみに株価を引き下げて会社の価値を下げすぎるのも問題といえます。
いくら節税対策といっても、会社の価値の側面からも判断することが重要です。
1つ目の方法としては「生前に役員退職金を支給する」があります。
退職金の支給により、会社の現金等が減るので、純資産が減ります。
また、株式の評価方法が純資産価額方式の場合、株式の相続税評価額が下がります。
役員退職金は費用計上されるため、会社の利益額が減少します。
株式の評価方法が類似業種比準方式の場合、株式の相続税評価額が下がります。
2つ目の方法としては、「無配当・低配当にする」やり方です。
「無配当・低配当にする」とは、会社が株主に対して配当を支払わないか、または非常に少ない金額の配当をすることを意味します
。この方法は、株価を意図的に低く保つために使用されることがあり、特に相続や事業承継の際に株式の評価額を低く抑えるために効果的です。
配当を少なくすることで、株式の市場価値が低く評価され、それにより相続税や贈与税の負担が軽減される可能性があります。
類似業種比準方式や配当還元方式では、配当金額を考慮して株式の評価額が計算されるので、一定期間、無配当・低配当にすることにより株価を引き下げることができます。
事業承継対策の具体的方法:株式数対策
株式数対策としては「自社株を後継者に贈与する」という方法をとります。
後継者の持ち株数を増やすことによって、後継者の経営支配権を確保することができます。
こちらは税金対策をしっかり講じておくことと、「相続対策」も考慮して行う必要があります。
非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度を活用する、「事業承継を円滑にするための遺留分の特例」として、「経営承継円滑化法」も視野に入れて対策を講じましょう。
ここは経営者自身で判断せず、弁護士や税理士などと協議して決めることをおすすめします。
事業承継対策の具体的方法:納税資金対策
納税資金対策として「生命保険の加入」を検討します。
意外と事業承継は相続税や贈与税が発生します。
そのための資金を用意することがより重要になります。
「契約者=受取人:会社、被保険者:経営者」という生命保険契約の活用により、死亡退職金の支払原資に当てることができます。
ここは保険会社ごとに商品が異なりますので、まずは付き合いのある保険代理店に相談してみてください。
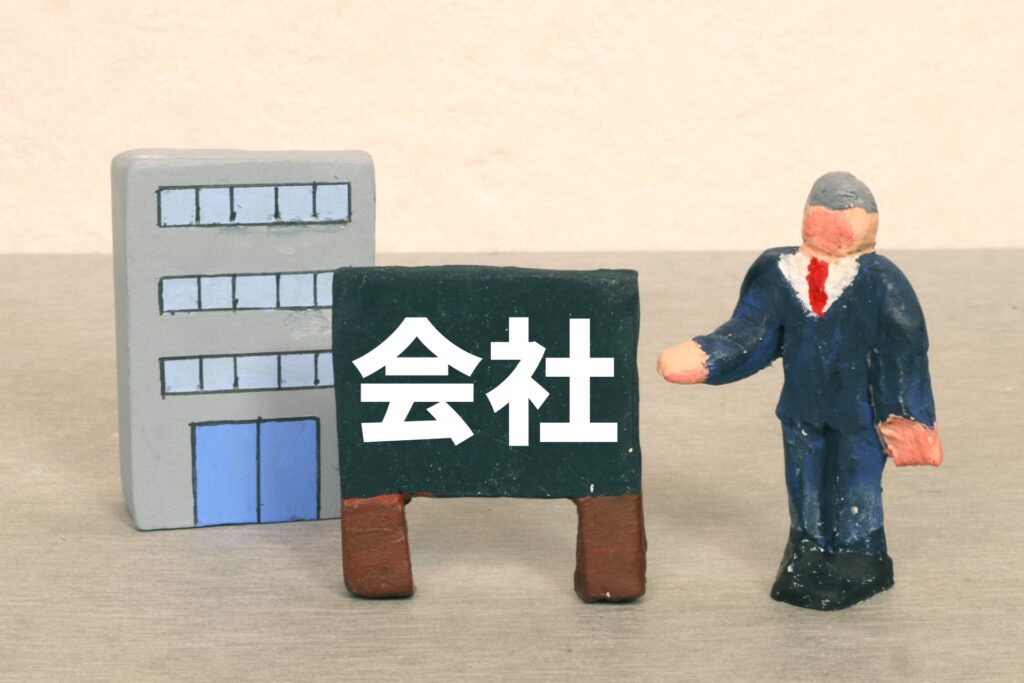
まとめ
事業承継対策は思った以上に時間がかかり、経営者の負担も大きいところです。
早めに対策を講じることが「事業承継」では大事になります。
ぜひ専門家を活用していきましょう。
今回は
『経営者必見!事業承継の実践的アプローチ(株価対策、節税)について江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください


