東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回は司法書士実務のお話。
最近、会社設立がネット上でも手軽にできるようになりました。
しかし、定款の雛形をそのまま用いると、あとあと面倒なことが起こります。
その一つが非取締役会設置会社の「代表取締役の選定」に関することです。
何が問題になるのかを紹介します。

会社設立時「代表取締役は取締役の互選で定める」とすると、後日代表取締役を選ぶ際に定款が必須です!設立後のことも考慮したほうがいい
代表取締役の選定方法について
非取締役会設置会社の定款の条項に代表取締役の定め方を記載することが多いです。
そもそも代表取締役の定め方として、
- 定款で直接定める
- 株主総会で定める
- 取締役の互選で定める
の3パターンがあります。
しかし、なぜか、非取締役会設置会社の株主総会の会社設立時の定款の雛形を見ていると、「取締役の互選」が多いです。
それが多いためか、私も設立後の会社の登記の依頼の時、定款を拝見すると「取締役の互選」がほとんどです。
取締役の互選で定めるとすると、なぜあとで面倒なことになるのかを解説します
代表取締役選定のときに添付書類が増える
非取締役会設置会社の場合、任期満了後、同じメンバーで再任されることが多いです。
そこで、取締役の任期満了とともに代表取締役も任期満了となり、新たに代表取締役を選び直す必要があります。
「取締役の互選で定める」とすると、取締役のお話し合い(取締役の過半数)で代表取締役を選ぶことになります。
その登記の申請書には、就任承諾書のほか、定款を添付しなければなりません。
定款の全文(代表取締役の選定部分の抜粋では足りない扱いです)を添付するとなると、意外と面倒なのです。
それを回避する方法は何かあるのでしょうか?
会社設立時に「取締役の互選」以外で定めることも検討
代表取締役が同じ人が続くことが想定されている場合、株主総会で代表取締役を選定することも視野に入れて定款を作成すべきです。
もしくは、
「代表取締役は株主総会で定める。ただし、取締役の互選で定めることを妨げない」
としておけば、選択的に選ぶこともでき、役員改選時の状況により、決められるので便利です。
確かに代表取締役の選定方法で、代表取締役の地位は変わりますが、そこまでこだわらないというのであれば、代表取締役の選定は選択的に定めるべきです。
ただし、株主総会で代表取締役を選ぶ場合、辞任するときに、辞任届では足りず、株主総会の承認が必要なところに注意してください。
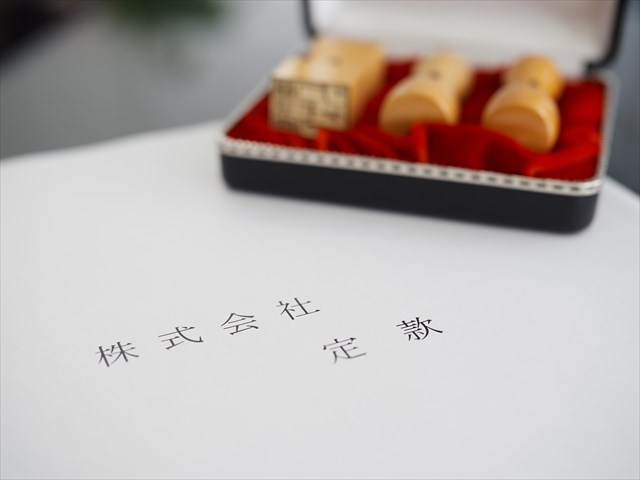
まとめ
非取締役会設置会社の場合、会社設立時に代表取締役の選定方法をどうするかは、ある程度今後のことも考慮して決める必要があります。
おそらく、自分で作った会社だから、代表取締役を辞めるのは、事業承継とか何か不都合があるときくらいしかないので、そのことも考慮して定款を作成してください。
何気なく雛形定款でやると後々不都合になります。
今回は
『会社設立時「代表取締役は取締役の互選で定める」とすると、後日代表取締役を選ぶ際に定款が必須です!設立後のことも考慮したほうがいい 司法書士が解説』
に関する内容でした。
参考ブログ
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから




