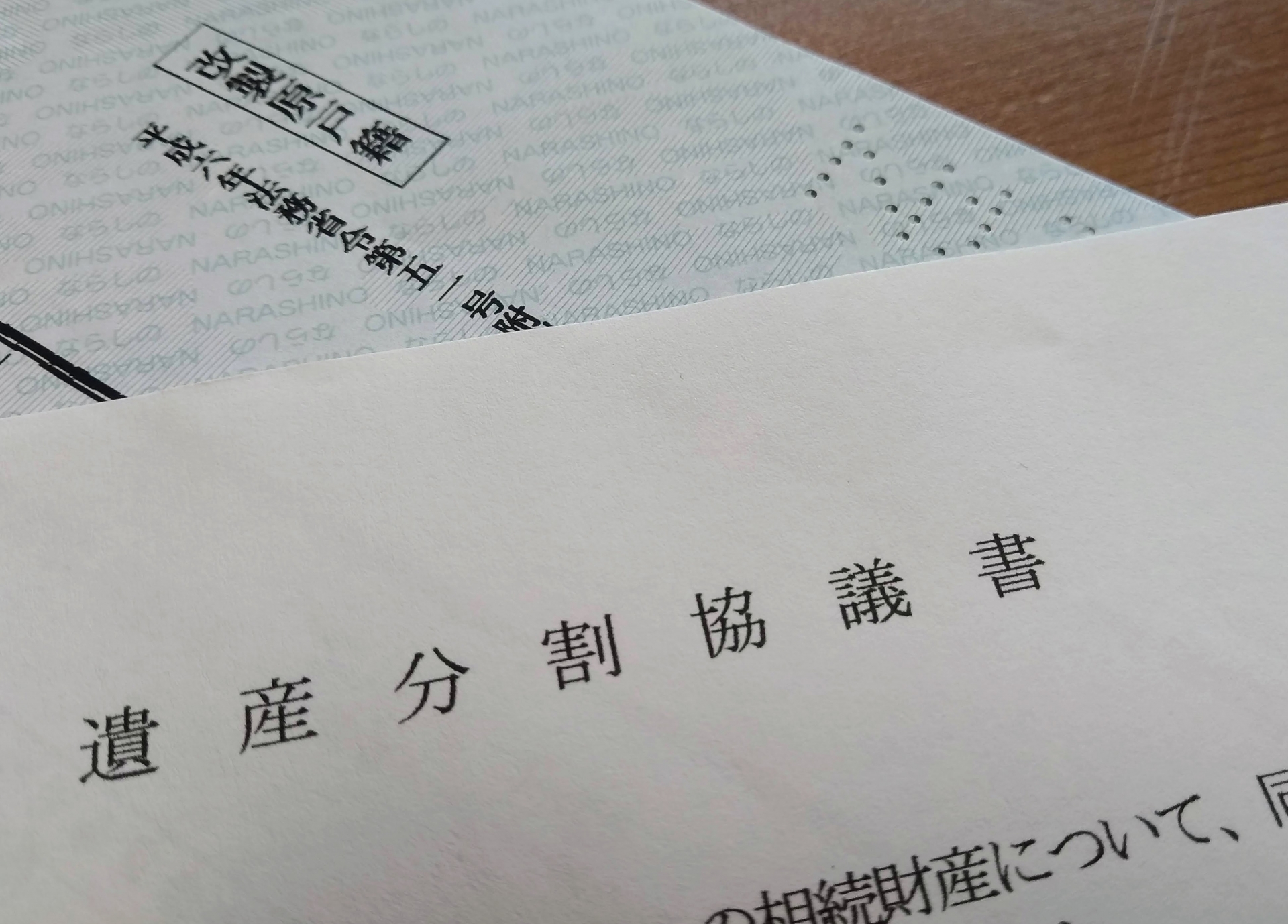こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続税対策を検討する際に、最も効果的な方法の一つは生前相続対策です。
これにより、相続財産を計画的に減らし、相続税の負担を軽減することができます。
ここでは、生前相続対策の具体的な方法と、最近の贈与税改正について詳しく解説します。
なお、具体的な対策は、必ず税理士などの専門家を介して行ってください。
今回も最後までお付き合いください。

贈与による相続財産の減少
生前に財産を子供や孫に贈与することは、相続財産を減少させる有効な手段です。
毎年110万円までは非課税で贈与できるため、計画的に贈与を行うことで相続税の負担を軽減できます。
例えば、10年間にわたり毎年110万円を贈与すると、合計1,100万円を非課税で移転できます。
ただ、注意なのは、生前贈与の相続財産の加算について改正されたこと。
2023年12月までは贈与した人が亡くなる前3年以内の贈与については相続財産として加算され、相続税の対象となりました。
しかし、2024年1月1日以後の贈与については、加算期間が順次延長され、2031年からは「死亡前7年以内」に延長されます。
延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されない形になります。
また、相続時精算課税制度に年110万円までの基礎控除の新設も始まりました。
ルール変更に注意して相続財産を減少させていかないといけません。
なお、生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」があります。
新たな贈与税対策でどちらの制度を選択すべきかについては、贈与する金額や期間によって、どちらを選択すべきかが変わってきます。
一度「相続時精算課税」を採用すると、「暦年贈与」に戻すことはできません。
ここは専門家を介して慎重に検討すべき事項です。
様々な贈与の特例の活用
住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金の贈与には非課税枠が適用されることがあります。
これらの贈与税非課税の特例をうまく活用することも検討してください。
なお、こちらも新ルールが適用になり、「結婚・子育て資金の一括贈与」は2025年3月末まで延長され、「教育資金の一括贈与」も2026年3月末まで延長になっています。
生命保険の活用
生命保険契約を活用することも、生前相続対策の一環として有効です。
生命保険金は相続税の算定の際、相続財産として扱われますが、法定相続人一人当たり500万円までは非課税となります。
この非課税枠を利用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
相続対策の専門家の活用
生前相続対策は専門知識を要する分野です。
税制改正の影響を正確に理解し、最適な対策を講じるためには、税理士などの専門家の助言を受けることが重要です。
専門家は個々の状況に応じた最適なプランを提案し、スムーズな財産移転をサポートします。

まとめ
相続財産を減らすための生前相続対策は、計画的な贈与や特定贈与、生命保険の活用など、多岐にわたります。
特に最近の贈与税改正を踏まえ、適切な対策を講じることが重要です。
これから生前の相続対策を考えている方は、専門家のアドバイスを受けながら、自身の状況に応じた最適なプランを検討してください。
詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『相続財産を減らす生前相続対策:最新の贈与税改正を踏まえて』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら