目次
はじめに:相続税の計算、把握しておくと何がいいの?
相続税計算の一歩一歩を追ってきたこのシリーズ、いかがでしたか?
前回までのブログで、相続税の総額をどうやって計算するのか、その方法を一緒に探ってきましたね。
もし見逃した方は、「あわせて読みたい」のリンクからチェックしてみてくださいね。
そのブログを読んでから今回のブログを読むとさらに相続税の概要を知ることができます。
改めまして、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
今回はその続きで、「各人が実際にどれくらいの相続税を払うことになるのか?」をざっくりと見ていきます。
具体的な詳細は税理士さんに聞くのが一番ですが、ここでは大まかな流れをつかんでください。
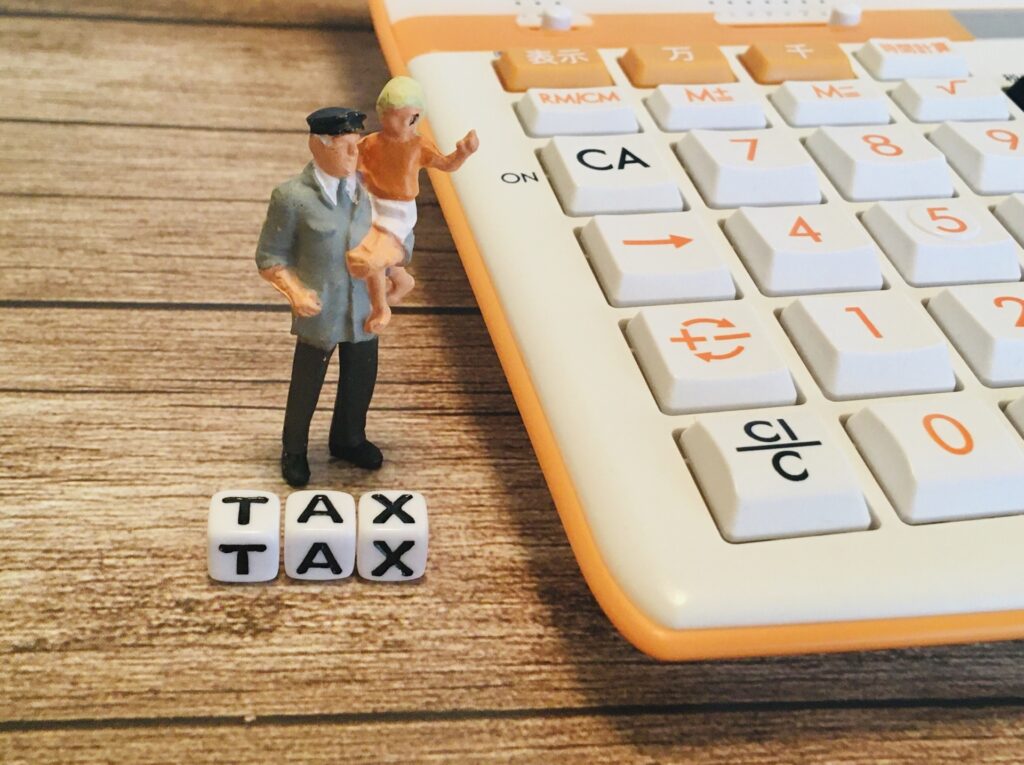
各相続人が支払う税額の計算ってどうやるの?
まず、前回までのステップで「相続税の総額」を計算しましたよね。
復習になりますが、大事なところなのでもう一度ざっくりと書きます。
ステップ1で「相続財産(みなし相続財産を含む)から非課税財産と借金や葬式代を引いた「課税価格」を出します。
ステップ2で各人の課税価格を合算し、「遺産にかかる基礎控除」をしたあとに法定相続人で分けます。それを相続税の速算表で見て、各人が支払う税額を出します。
それを合算した額が「相続税の総額」となります。
今回からはこの計算からスタートして、具体的に「各人の算出税額」をどう計算するか見ていきましょう。
まずは「各人の算出税額」を計算します。
計算式は以下のとおりです。
各人の算出税額=相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額
各人の算出税額を計算した後は?
計算が済んだら、次は税額の調整です。ここがちょっと面倒かもしれません
一緒に見ていきましょう。
相続税額の2割加算
まずは、相続税額の20%を加算するケースがあります。
これは、被相続人の配偶者や直系血族以外の人が対象です。
具体的には、兄弟姉妹や孫、祖父母などがこれに該当します。ただし、孫が子の代わりに相続する場合、この加算は適用されません。
控除はどうするの?
税額の計算には控除も重要です。贈与税控除や配偶者の税額控除、未成年者控除、障害者控除など、様々な控除があります。
これらを適用すると、税額がぐっと減ることがありますよ。
概要を解説していきますね。
贈与税額控除
生前贈与加算の対象となった人が贈与税を課された場合には、その贈与税額を相続税額から控除します。
配偶者の税額控除
配偶者の軽減される税額は、以下の計算式で求められます。
配偶者の税額軽減額
=相続税の総額×次の(1)(2)のいずれか小さい方の額/課税価格の合計額(1)課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
※ただし1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円
(2)配偶者の相続税の課税価格
この計算式は、配偶者の取得した財産が1億6,000万円以下または配偶者の法定相続分相当額以下の場合には、相続税がかからないことを意味しています。
未成年者控除
控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
※18歳に達するまでの年数が1年未満のときは1年として計算します。
障害者控除
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
※85歳に達するまでの年数が1年未満のときは1年として計算します
※特別障害者の場合は「10万円」の部分が「20万円」になります。
相次相続控除
10年以内に2階以上の相続があった場合、一定の税額を控除することができます。
外国税額控除
外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課された場合、二重課税を排除するため、税額を控除することができます。
相続時精算課税制度による贈与税額控除
相続時精算課税制度を適用し、贈与税を支払っている場合、その贈与税額を相続税から差し引きます。
既に支払った贈与税額が相続税を超過する場合には、その超過額が還付されます。

まとめ
今回は相続税の各人の納付額を紹介しました。
3回にわたり相続税の各人の納付の流れの概略を紹介しました。
簡単なようでややこしい側面が相続税にはあります。
生前相続対策で贈与税と絡めて節税を考えている方はぜひ税理士と協議したうえで対策を講じることをおすすめします。
やはり、自分の「相続財産」や「みなし相続財産」を知るためにはエンディングノートを活用したり、相続人は誰かを特定することが相続税の他委託でも大事です。
相続に関するお悩みがあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
今回は
『ステップバイステップで解説!各人の相続税納付額の計算方法を江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら
「相続税計算の基礎知識と生前対策の重要ポイントを江戸川区の司法書士・行政書士が解説」



