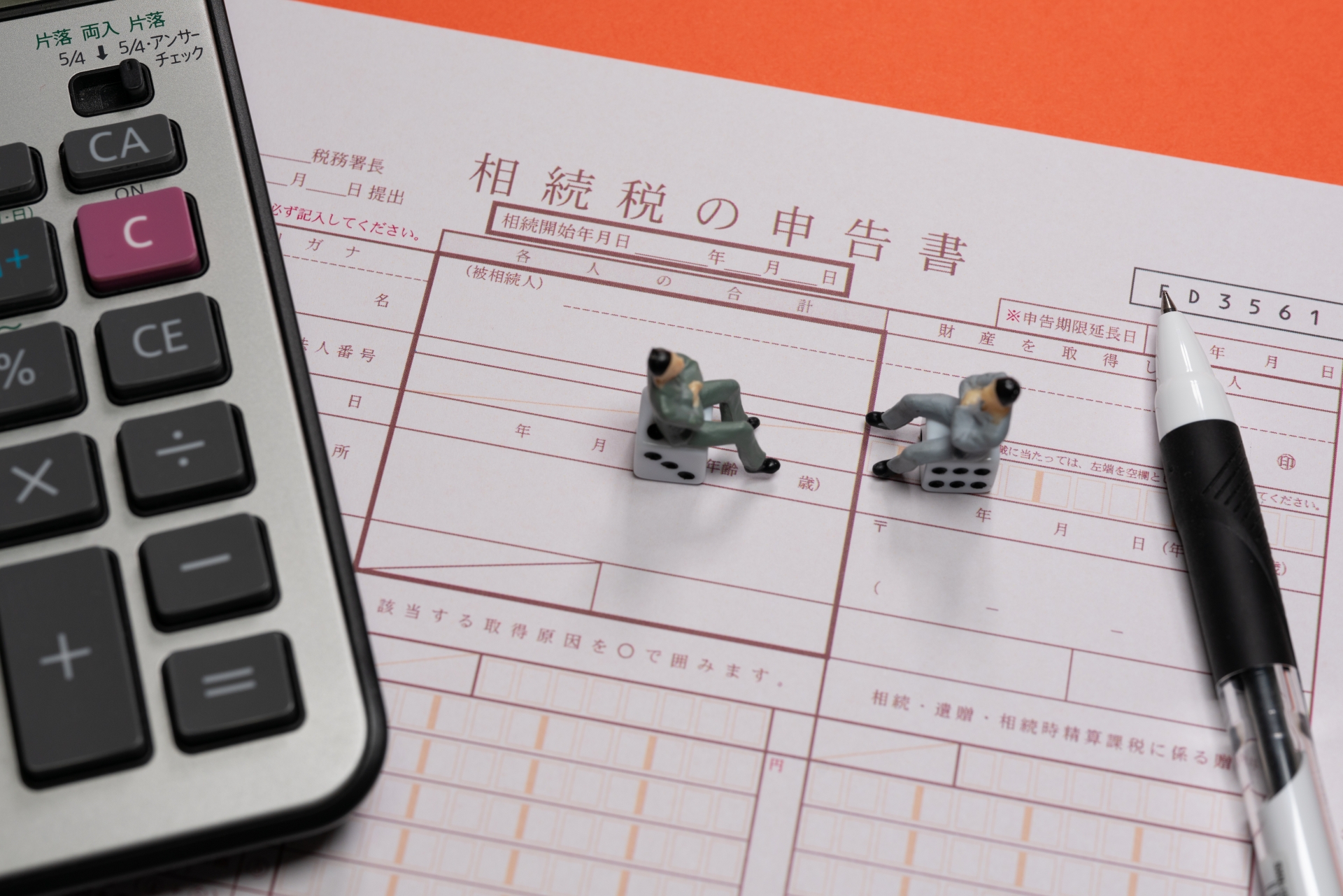目次
はじめに 相続税の申告と納付について知っておきましょう!
相続税計算の一歩一歩を追ってきたこのシリーズ、いかがでしたか?
前回までのブログで、相続税の総額をどうやって計算するのか、その方法を一緒に探ってきましたね。
もし見逃した方は、「あわせて読みたい」のリンクからチェックしてみてくださいね。
改めまして、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
今回は、それらのステップを経て、各人の相続税の納付額が確定したら、いよいよどうやって申告と納付となりますが、その方法をざっくり解説します。
税務のこと、面倒だと感じるかもしれませんが、税理士さんの力を借りながら進めていくのがベストですよ!
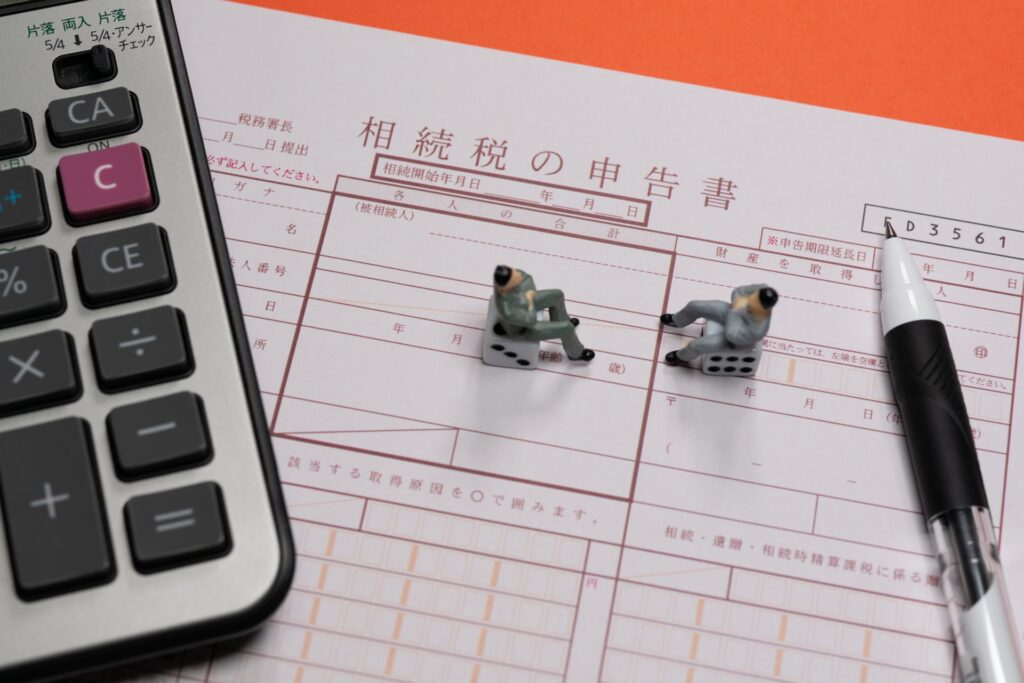
相続税の申告のポイント
まず、相続税の申告って誰がやるべきなのでしょうか?
答えは、財産を受け取る人(相続や遺贈によって財産を取得した人)です。
財産をもらったら、必ず申告しないとダメ?
この種の質問、司法書士でもよく聞かれます。
答えは以下のとおりです。
相続財産が基礎控除以下の場合は相続税の申告は不要なんです。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、納付税額が0円の場合でも申告が必要なので注意してくださいね。
提出期限ですが、相続の開始があったことを知ったときから10ヶ月以内に提出する必要があります。
遺産分割が間に合わなかったらどうするの?
この種の質問も多いです。
答えは以下のとおりです。
とりあえずは法定相続分に基づいて申告を進める必要があります。なので、相続開始があったことを知ったときから10ヶ月以内に提出してください。
提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長になります。
気をつけてほしいことは、相続税の申告期限までに遺産分割協議が行われていない場合、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価額の特例」を受けることができないこと。
この場合は、とりあえずは特例を受けない形で申告して、申告期限から3年以内に遺産分割が行われたときには、更正の請求をして特例の適用を受けることができます。
相続税、どうやって納めるの?
基本税金は、申告の締め切り日までに一括でお金を払う必要があります。
しかし、相続税は、条件によっては、延納(分割払い)や物納もできます。
相続税で注意することは、相続人の誰かが相続税を納めなかった場合、相続人全員が連帯して相続税を納める責任を負います。
「延納」について
延納とは、相続税の全部または一部を年払いで税金を少しずつ分けて払うやり方。
延納の要件は以下のとおりです。
- 金銭一括納付が困難であること
- 納付すべき相続税額が10万円を超えていること
- 延納申請書を申告書の提出期限までに提出していること
- 担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要 延納の担保は相続財産でなくてもいい)
留意すべき点は、延納税額のほか、利子税がかかること、延納できる期間は、財産の価額合計額に占める不動産等の価額に応じて定められていて、最長が20年となることです。
「物納」について
物納とは、相続税を相続財産によって納付する方法です。
物納の要件は以下のとおりです。
・
・延納によっても金銭納付が困難であること
・物納申請書を申告書の提出期限までに提出すること
物納財産の収納価格は、原則として相続税評価額となるところにも注意してください。
「延納」から「物納」への変更 物納の撤回
原則として延納から物納への変更はできません。
しかし、申告期限から10年以内である場合で、延納による納付が困難になったときは、延納から物納に変更できます。
また、物納の許可を受けたあとに金銭一括納付や延納が可能になった場合、物納の許可後1年以内に限り、物納を撤回できます。
相続税の金銭一括交付のために生前の相続対策を!
見ていただいて分かったかと思いますが、相続税の納付のための金銭は準備しておく必要があります。
いざ相続が開始したときに手元に金銭がないとなると、延納もしくは物納となり、せっかくの相続が被相続人の思い通りにならないこともあります。
このことからも「生前の相続対策」で相続税の納付のことも意識しておくことが大事です。
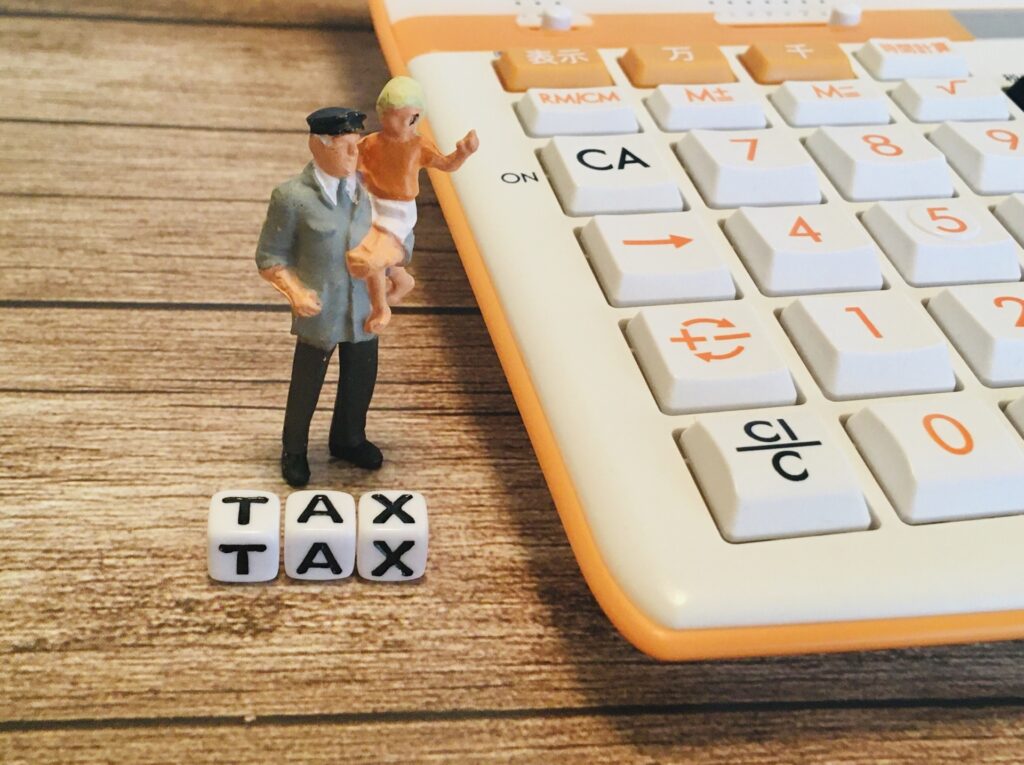
まとめ
今回、相続税の申告と納付についてざっくりとお話しました。
もし不安な点があれば、ぜひ税理士さんに相談してください。
事前に計画をしっかり立てておけば、いざという時に慌てることなく対応できますよ。
相続税の準備だけでなく、生前の対策もしっかり行って、安心して将来を迎えましょう。
相続について気になることがあれば、いつでも私たちの事務所にご相談ください。
また、国税庁のホームページもチェックして、最新の情報を得てくださいね!
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『相続税 納付額が確定したら申告と納付へ 気をつけるべきポイントは?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら
「相続税計算の基礎知識と生前対策の重要ポイントを江戸川区の司法書士・行政書士が解説」
「ステップバイステップで解説!各人の相続税納付額の計算方法を江戸川区の司法書士・行政書士が解説」