東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2024年は「相続」に注目が集まっています。
2024年1月から相続税・贈与税のルールが変わります。
今回は相続時精算課税制度を中心に紹介します。
なお、あくまでも概略のお話に留めます。
具体的に相続税対策の一環として「贈与税」を考えている場合は税理士に相談して活用してください。

2024年の贈与税の見直しで相続税の考えが変わる
2024年の税制改正で大きいのが、生前贈与の「持ち戻し」ルール。
生前贈与してから3年以内に相続が発生した場合は、その贈与はなかったことになります。
ただし、この持ち戻しのルールが2024年1月1日から7年以内に変わります。
なお、7年の延長は2024年1月1日から行われる贈与に対して段階的に行われます。
そのため、相続税対策の一環として「贈与」をするときは「持ち戻し」のことも念頭に置く必要があるのです。
相続時精算課税制度とは?
まずは贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制をとっています。
なので、ここの選択を誤ってしまうと、かえって税金を多く取られてしまうので、採用するときは慎重にする必要があります。
暦年課税制度とは、年間110万円まで非課税で、110万円を超えた部分に贈与税の税額をかけて贈与税を計算する方法です。
相続時精算課税制度は、贈与するときは最大2,500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する方法です。
相続時精算課税制度は相続開始時に贈与した金額を持ち戻して相続税を計算することになるので、相続税がどうなるのかシミュレーションして採用するかを決める必要があります。
先ほども書きましたが、一度相続時精算課税制度を採用してしまうと、二度と取り消すことができないのが怖いところ。
自分の場合はどちらがいいのかはしっかり見極める必要があります。
個人的には2023年12月31日までは「相続時精算課税制度」は使い勝手が割ると感じていました。
しかし、2024年1月1日から相続時精算課税制度を採用した場合でも、年間110万円の非課税枠が新設され、申告義務もなくなりました。
そうなると、暦年課税制度と相続時精算課税制度どちらが税金が安くなるのかをより慎重に判断する必要があるように感じます。
贈与税の対策 遺言作成時にも検討
遺言を作成するに際して、贈与税のことも考慮に入れて作成することが重要。
自分が亡くなったときに誰に財産を渡したいか、事前に財産を渡せるのであれば誰に渡すか、生前対策がより大事になります。
贈与税をうまく活用しつつ、遺言も作成する、生前対策として検討してみてください。
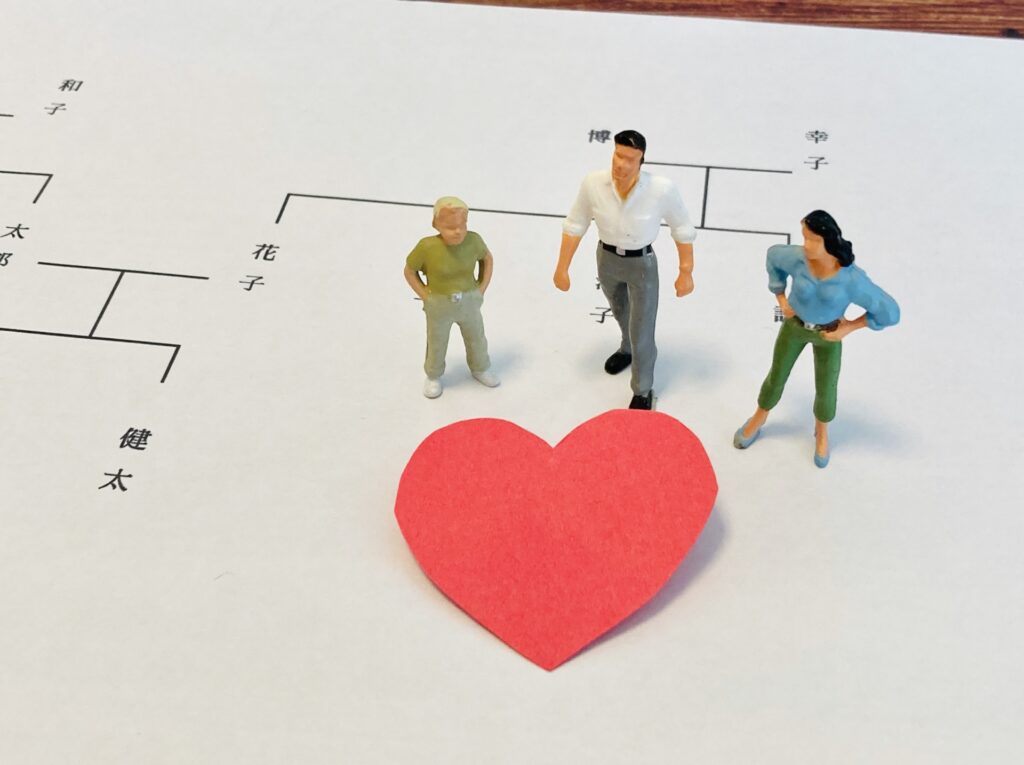
まとめ
相続の生前対策として「贈与税」の検討も重要になります。
ただ、自分で贈与税のシミュレーションをするのは難しい。
なので、税理士に相談して判断することが生前の相続対策としては有用です。
親子で考えて相続対策をしていきましょう。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『親と子の生前相続対策:遺言作成と贈与税について2024年税制改正がもたらす影響とは』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら




