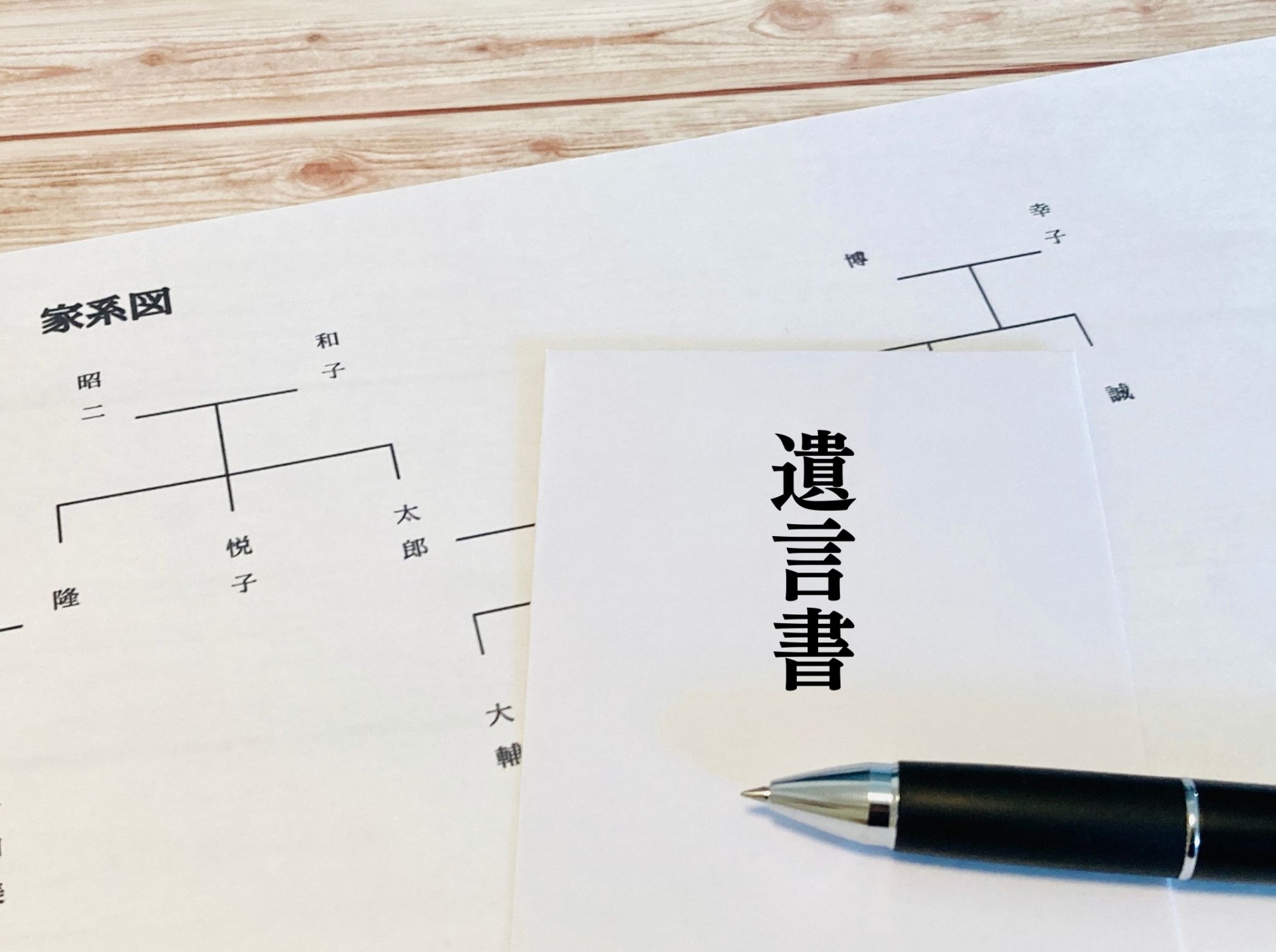東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続対策で事前に「遺言書」を書きましょうとよく言われます。
よくこんな質問を受けます。
財産の渡し方以外にも遺言書に自分の思いを書くことはできませんか?
今回は「付言事項」について紹介しながら、どのような遺言書を書いていけばいいのかを紹介します。
争いの元となる遺言書をかくと後々相続人が疲弊してしまいます。
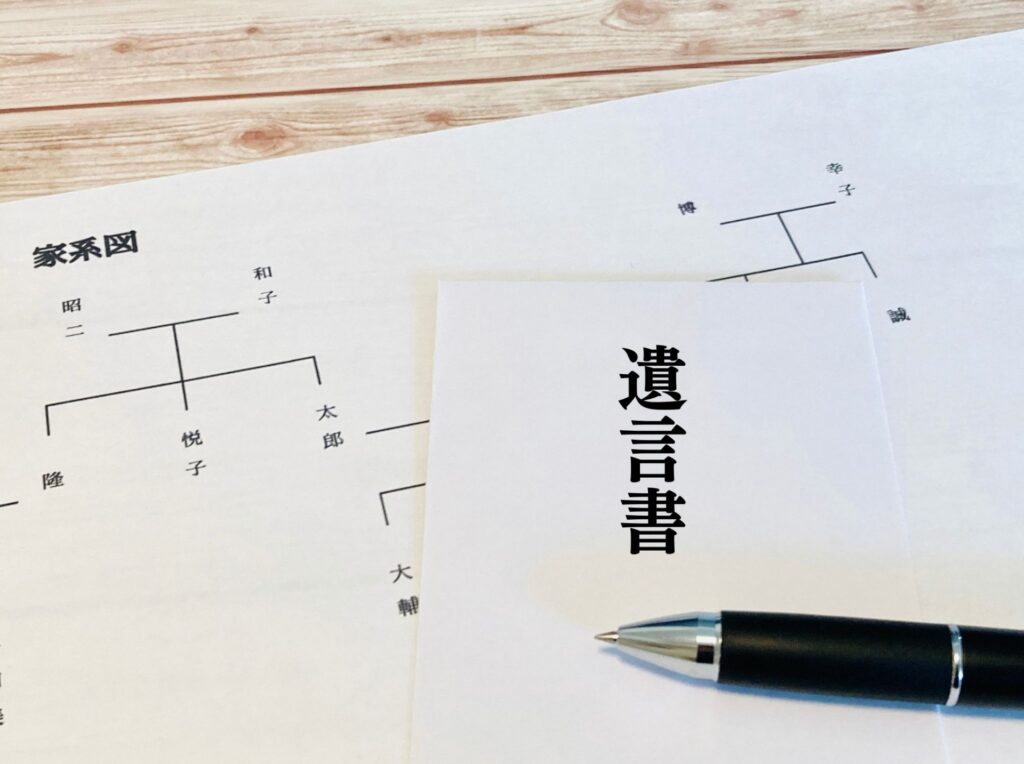
遺言書の書き方、できるだけ具体的に書く
「私が相続開始時に有している財産すべてを妻〇〇に相続させる」
これでも有効です。
一応、これでも遺言者の財産は特定しているといえるからです。
ただ、これだけだと、財産の具体性がなく乏しい感じがします。
自分の財産を総整理する意味でも、遺言書に記載する財産は具体的に誰に渡したいのかを明記することをおすすめします。
「付言事項」とはなにか?
今回のブログのテーマーである「付言事項」について紹介します。
遺言の効力が生じるのは、法律で決められた事項になります。
しかし、なぜあなたがその人に財産を託していきたいのか、あなたの思いも書きたいでしょう。
「付言事項」は、遺言事項ではなく、必ずしも遺言書に記載する必要はありません。
しかし、相続人等に対するメッセージ的意味合いが強く、相続人等の行動に影響を及ぼす効果があります。
付言事項は遺言書のどこに書いても問題はありません。
「付言事項」の記載方法は?
私の場合は、遺言事項を書いた後、最後に「付言事項」を書くことが多いです。
ただ、ものの本とかによると、遺言事項を第◯条などの条文として記載した後に「付言」として記載する例もあるようです。
いずれにしても、法的効力がある遺言書本文と区別し明確化することが重要です。
「付言事項」を書くときの注意点
先程から書いていますが、「付言事項」そのものには法的効力はありません。
何を書いても構わないし、書き方も自由です。
ただなぜ「付言事項」を書くのか、意図を明確にする必要はあります。
相続人にしてもらいたいこと、紛争を予防し、遺言者の遺言の意図を円滑に実現することを目的とすることを忘れないでください。
なので、相続人に呼びかけるように、相続人が納得いくような内容や書き方でなければ「付言事項」の意味はありません。
相続人が「遺言者がこのように思っているのだから仕方がない」「無用な争いは避けよう」などと感じるような付言事項を書く必要があることを遺言者は心がけてください。
ここは遺言者と相続人間の人間関係や経済状況、性格も考えて書くことが大事です。

まとめ
「付言事項」を書くことで相続人間の紛争を未然に防ぐ役割があります。
ただ、付言事項の書き方次第で争いの原因にもなるので、遺言者の意思だけではなく、相続人にも寄り添うような内容の「付言事項」を書いていくことを心がけてください。
今回は
『遺言書の書き方 「付言事項」財産を渡すこと以外になにか書けることはあるのか?書くときの注意点について江戸川区船堀の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら