東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続が開始したら、遺言を残していないような場合には、遺産分割協議で遺産を分けることをします。
こちらについても、今回相続に関する改正の一環として改正がされます。
改正法が施行されると問題となってくるのは、いつの時点から新しい法律が適用されるのかが重要になってきます。
今回は遺産分割の時的限界の経過措置の部分について書いていきます。
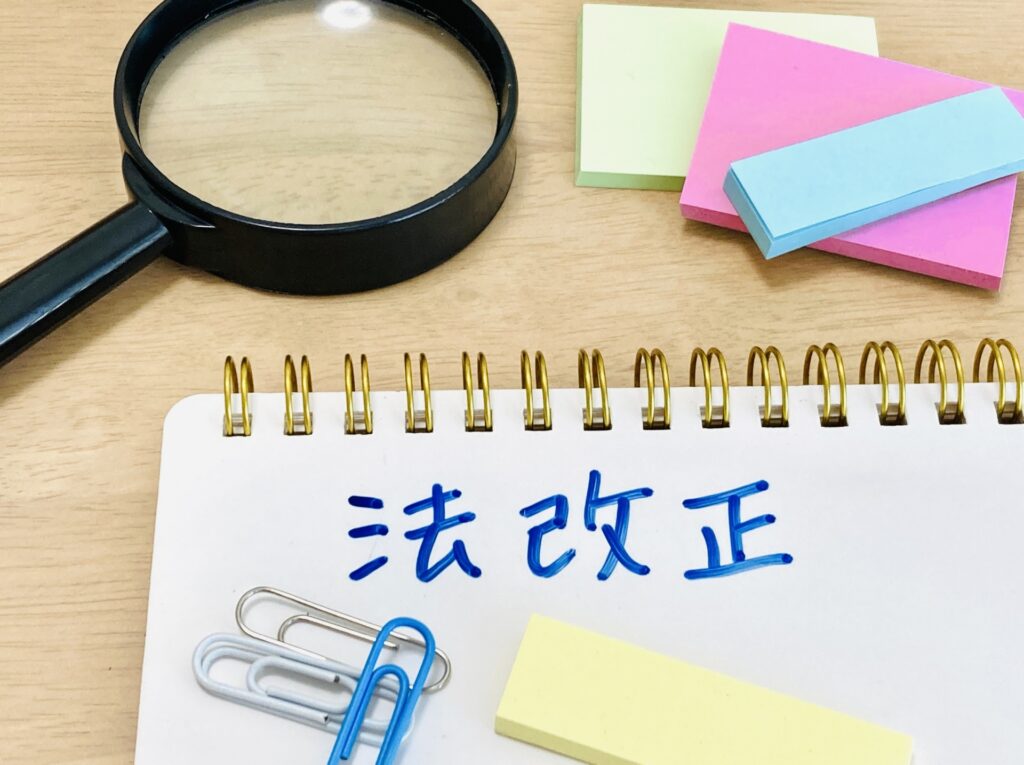
改正法の施行日前に相続が開始した場合の遺産分割の取扱い
遺産分割の時的限界に関する施行日は令和5年4月1日からとなります。
改正法の施行日前に被相続人が亡くなった場合の遺産分割についても、新法のルールを適用します。
ただし、いきなり新法のルールを適用すると混乱を生じることもあるため、経過措置により、少なくとも施行時から5年間の猶予期間を設けることになります。
相続開始時より10年を経過しても、具体的相続分により分割する場合は、以下の通りです。
1つ目は、相続開始時から10年経過時又は改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときです。
2つ目は、相続開始時から10年の期間(相続開始時からの10年の期間の満了後に改正法施行時からの5年の期間が満了する場合には、改正法施行時からの5年の期間)満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときです。
具体例で紹介
1の場合として、施行時に相続開始から既に10年が経過しているケースの場合、施行時から5年の経過時が基準となります。
つまり令和5年4月1日が基準となり、そこから5年が経過すると、具体的相続分による分割の利益が喪失します。
2の場合として、相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも前に来る場合、これも施行時から5年の経過時が基準となります。
例えば、相続開始が令和5年4月1日よりも7年前に発生した場合、令和5年4月1日より5年経過する前に10年が経過してしまいます。
この場合であっても、令和5年4月1日から5年の猶予期間があり、それ以降になると、具体的相続分による分割の利益は喪失してしまいます。
最後に相続開始時から10年を経過する時が、施行時から5年を経過する時よりも後に来るケースの場合、その場合は、相続開始時から10年の経過時が基準となります。
例えば相続開始が令和5年2月1日の場合、5年の猶予期間よりも後に、10年の経過期間がきます。
このときは、令和15年2月1日が基準日となり、それ以降は、具体的相続分による分割の利益が喪失してしまいます。

まとめ
遺産分割の時的限界については、いつ相続が開始されたかによって、具体的相続分による分割の利益喪失時が異なります。
このことを考えても、相続が開始前から相続人の特定など早めに準備されることをおすすめします。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「具体的相続分による遺産分割の字時的限界についての経過措置」江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
民法改正に関するブログはこちら



