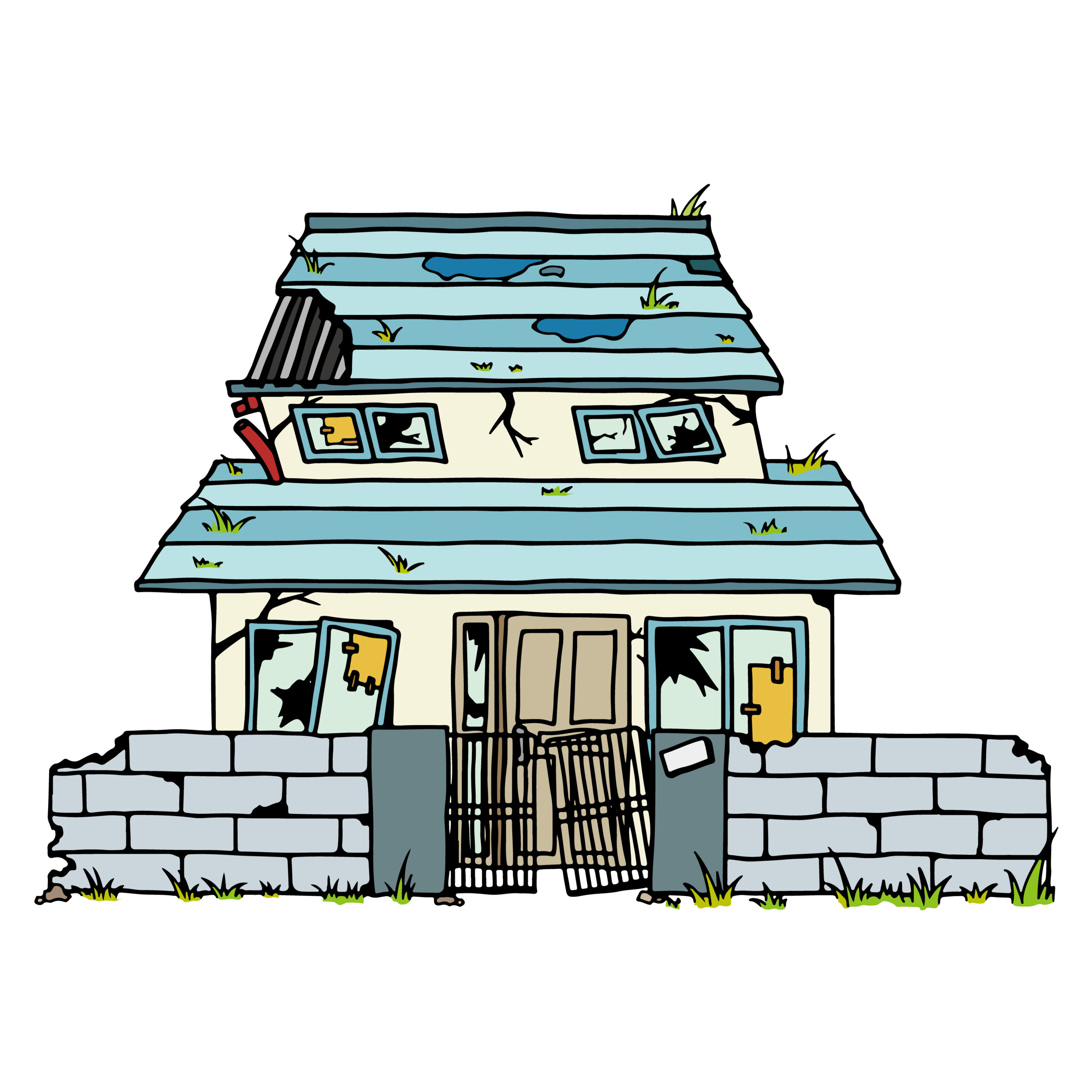東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続が開始したら、遺言を残していないような場合には、遺産分割協議で遺産を分けることをします。
こちらについても、今回相続に関する改正の一環として改正がされます。
どのように改正されるのか、今回紹介していきます。
今回も法務省の資料をもとにブログを書いていきます。

遺産分割の時的限界に関する問題の所在
具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについては、時的制限がなく、長期間放置しても具体的相続分による遺産分割を希望する相続人に不利益が生じないという問題があります。
相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくいと言われています。
さらに、相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れてしまいます。
長期間が経過すると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となります。
改正法でどう変わるのか?
今回の民法改正で以下のとおりに変わります。
原則として、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)になります。(新民法904条の3)
ただし、例外もあり、以下のような場合には、引き続き具体的相続分により分割されます。
1つ目は、10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときです。
2つ目は、10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときです。
やむを得ない事由としては、被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなどがあります。
10年経過後の法律関係はどうなるか?
遺産分割など何もしないで10年が経過した場合、どうなるのでしょうか?
10年経過により分割基準は法定相続分などになりますが、分割方法は基本的に遺産分割であって、共有物分割でないことになります。
分割基準以外の遺産分割の特徴としては、以下のとおりとなります。
裁判手続は家庭裁判所の管轄となり、遺産全体の一部分割が可能になります。
遺産の種類・性質、各相続人の状況等の一切の事情を考慮して分配されますし、配偶者居住権の設定も可能となります。
また、具体的相続分による遺産分割の合意も可能です。
10年が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したケースでは、具体的相続分による遺産分割が可能になります。
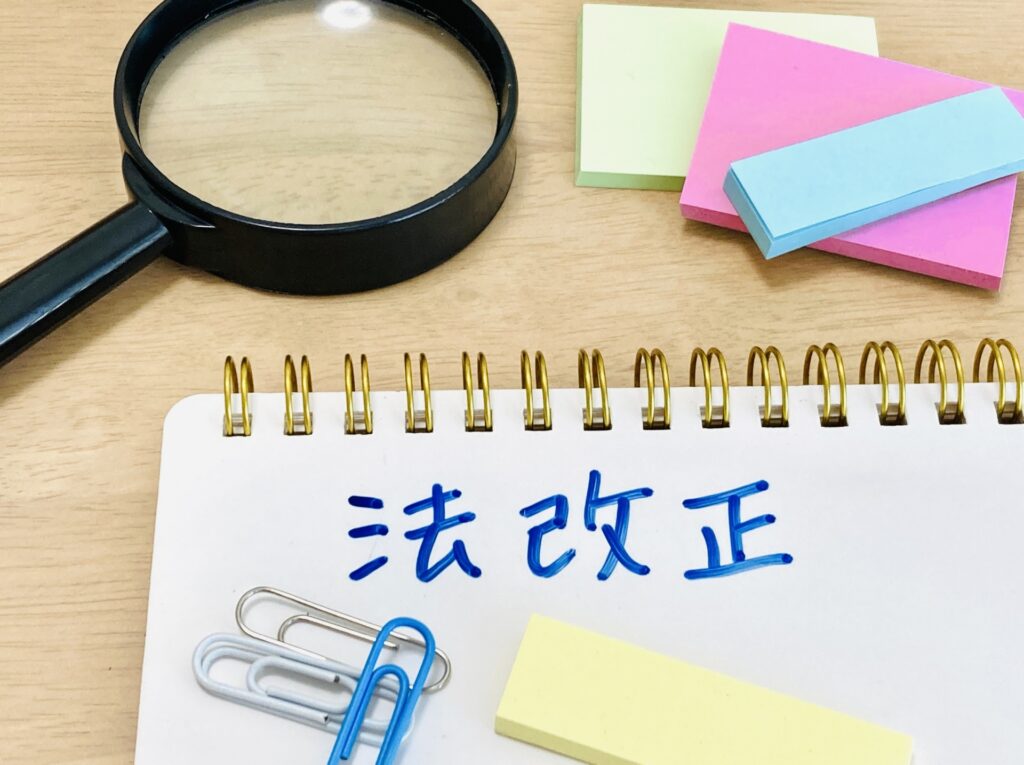
まとめ
遺産分割が長年行われなかった場合の扱いが変わることに注目すべきでしょう。
相続開始後、速やかに遺産分割協議を行うことがますます大事になってくると思われます。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「具体的相続分による遺産分割の時的限界について」江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
民法改正に関するブログはこちら