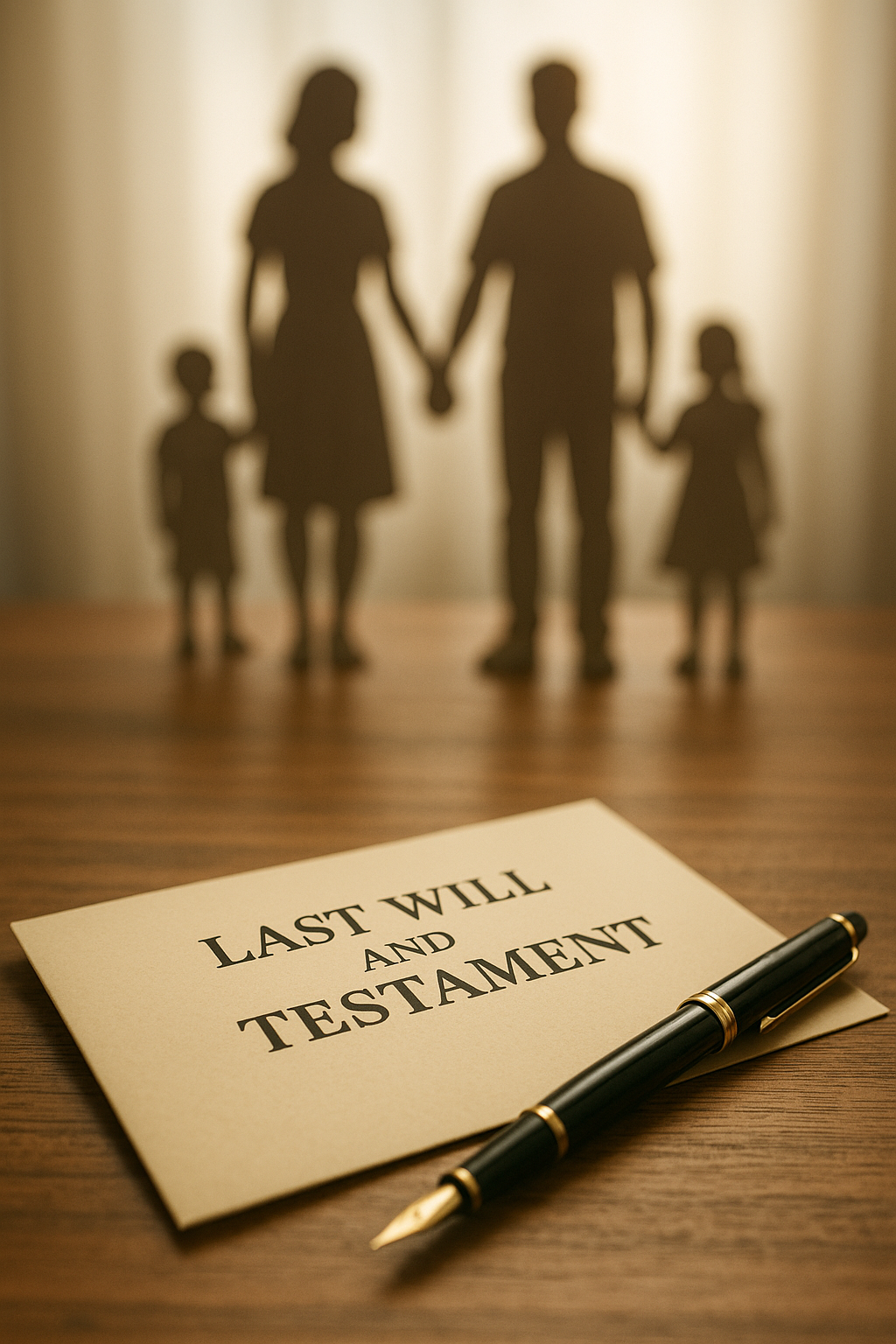こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
「遺言さえ書けば自分の財産は自由に分けられる」と思っていませんか?
実はそう単純ではなく、相続には遺留分(いりゅうぶん)というルールがあります。
今回は、司法書士の立場から
-
遺留分とは何か
-
遺言で放棄できるのか
-
放棄する場合の手続き
-
よくある誤解や相談例
をわかりやすく整理してお伝えします。
遺留分とは?
遺留分とは、法律で守られている「最低限の取り分」のことです。
対象となるのは 配偶者と子ども(直系卑属)、そして子どもがいない場合の 親(直系尊属) です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
このことから兄弟姉妹が相続人で自分の思う通りに財産を分けたい場合は遺言は必須といえます。
具体例で考えてみましょう
-
【例1】夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合
法定相続分は妻1/2、子ども2人で1/2ずつ(つまり1/4ずつ)。
遺留分はこの法定相続分の1/2なので、妻は1/4、子どもは各1/8が最低限の取り分です。 -
【例2】夫が亡くなり、妻と夫の両親が相続人の場合(子どもなし)
法定相続分は妻2/3、両親で1/3。
両親の遺留分はさらにその1/2なので、両親で1/6が最低限の取り分です。
つまり、どんなに「全財産を長男に渡す」と遺言を書いても、他の相続人が遺留分を主張すれば一定の取り分は確保できるのです。
遺言で遺留分を放棄できるのか?
結論はシンプルです。
👉 遺言に「遺留分を放棄する」と書いても効力はありません。
遺留分は法律が強く保護している権利のため、遺言で一方的に奪うことはできないのです。
では、まったく放棄できないのかというとそうではありません。
相続開始前に、相続人本人が家庭裁判所に申立てを行い、許可を得た場合に限り、遺留分を放棄することが可能です。
ただ、相続開始前に遺留分を放棄するケースはあまりないように感じます。
遺留分放棄の手続きの流れ
遺留分放棄は、次のような手順で進めます。
-
相続人本人が家庭裁判所に申立て
-
放棄したい人(例:次男)が自ら申立てます。
-
本人の意思であることが大前提です。
-
-
必要書類を提出
-
申立書
-
戸籍謄本
-
放棄の理由を記載した上申書
-
収入印紙(800円程度)や郵便切手
-
-
家庭裁判所での審理
-
裁判官が「本当に自分の意思か」「無理やりではないか」を確認します。
-
事情によっては面談が行われることもあります。
-
-
許可決定が出れば放棄成立
-
許可が下りると、以後その相続人は遺留分を主張できなくなります。
-
このように、家庭裁判所がチェックを挟むのは「家族の圧力で放棄させられること」を防ぐためです。
遺留分放棄が使われるケース
-
事業承継のため
会社や不動産を後継ぎに集中させたい場合、他の相続人に放棄してもらう。 -
財産の偏りを希望する場合
介護してくれた子どもに多く残したい、など。 -
相続争いを未然に防ぐため
将来のトラブルを避けたいという意向で、あらかじめ話し合って放棄。
ただし、放棄はあくまで本人の自由意思。
「親や兄弟に頼まれたから」という理由だけでは裁判所の許可が下りないこともあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 相続が始まってから遺留分を放棄できますか?
A. 相続開始後は、家庭裁判所の手続きによる放棄はできません。
ただし、相続人同士の話し合いで「遺留分を請求しない」と合意することは可能です。
Q2. 放棄したら他の相続権もなくなるのですか?
A. 遺留分の放棄は「最低限の取り分を請求しない」ということ。
相続権自体を失うわけではありません。
Q3. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. ありません。兄弟姉妹は法律上、遺留分の対象外です。
教科書的事例
あまり、遺留分放棄が利用されることは少ないですが、事業承継対策の一環として利用されることがあります。
ただ、実際に利用されることは少ないように感じます。
利用される例を紹介します。
あるご家庭では、父が経営する会社を長男が継ぐ予定でした。
父は「会社の株式をすべて長男に相続させたい」と遺言を作成。
しかし、そのままでは次男にも遺留分の権利があり、株式の一部を請求されると会社の経営が不安定になる恐れがありました。
そこで次男が家庭裁判所に申立てを行い、遺留分を放棄。
その結果、会社はスムーズに長男に引き継がれ、家族関係も良好に保たれました。
遺留分対策のポイント
-
まずは遺言書を作成する
-
完全な自由はないが、意思を示すことが重要。
-
-
家族と早めに話し合う
-
相続の場で初めて知るとトラブルになりやすい。
-
-
必要に応じて遺留分放棄を検討
-
ただし裁判所の許可が必要なので専門家に相談を。
-
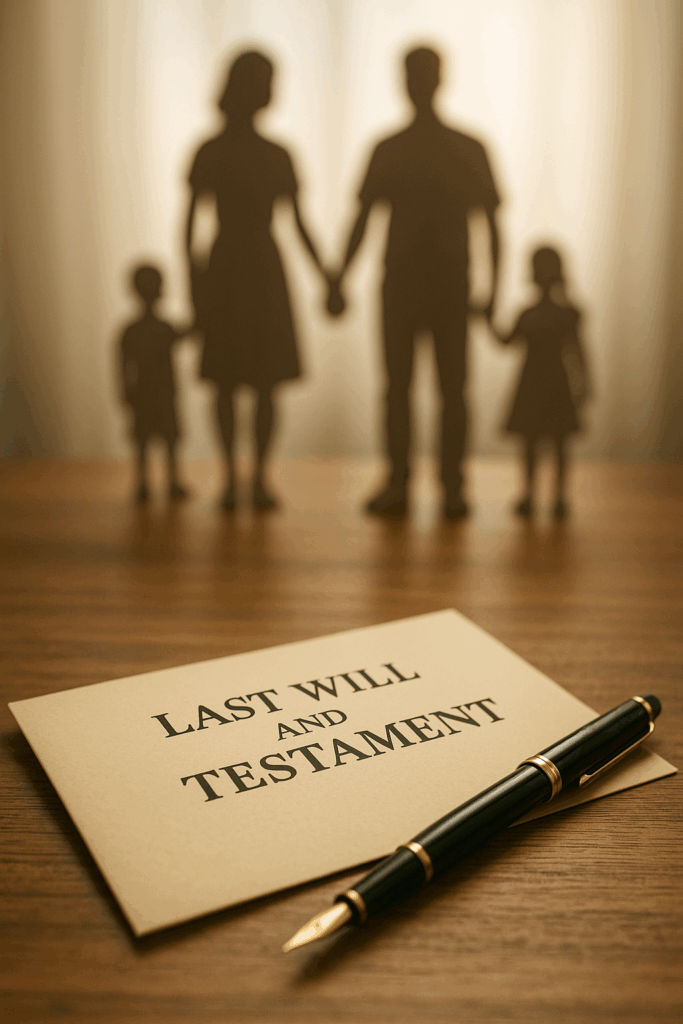
相続・事業承継に関して悩んでいるという方は、お気軽にご相談ください。
電子書籍でさらに詳しく学ぶ:がんばらない相続手続き
相続で悩んでいる場合は、電子書籍『がんばらない相続手続き:効率よく進める3つの方法』をお読みください。
基礎的な相続手続きについて詳しく解説しています。
今すぐ手続きを始めて、安心した未来を手に入れましょう!