こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
家族経営の代表者が亡くなると、相続手続きが発生します。
その際、休眠している会社があるかもしれません。
今回は休眠会社に関する詳細と対応策を説明します。
最後までぜひ御覧ください。
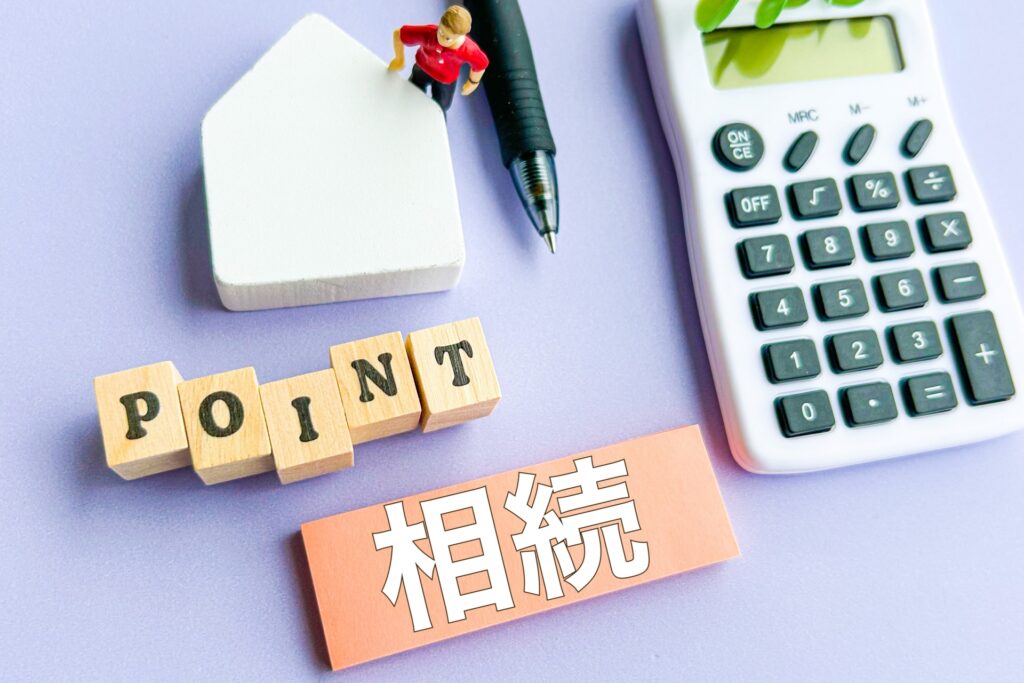
相続で発覚!休眠会社ってどんな会社?
相続手続きをしていると、「昔、会社を作ったような…」と思い出す方もいるかもしれません。
長年、事業活動を行っていない会社は「休眠会社」と呼ばれます。
相続手続きの際に存在が明らかになるケースも少なくありません。
休眠会社は、法人格を維持したまま、事業を停止している状態です。
将来的に事業再開の可能性を残しつつ、運営コストを抑えるメリットがあります。
一方、法定手続きや税務申告など、休眠状態でも一定の維持費用が発生します。
放置は危険!休眠会社にはこんなリスクも…
休眠会社を放置すると、後々トラブルに発展する可能性があります。
例えば、役員が死亡した場合、適切な手続きを行わないと、ご家族が法的責任を負うこともあります。
また、長期間放置された休眠会社は、信用度が低下し、事業再開が困難になります。
相続時に休眠会社が見つかった場合は、放置せずその後の対応を検討する必要があります。
解散?休眠継続?相続した休眠会社の対処法
相続した休眠会社をどう扱うかは、今後の事業計画や相続人の意向によります。
事業再開の見込みがない場合は、会社を解散する手続きが必要です。
ただし、すぐには会社をたたむことはできません。
法律に従って解散手続きを行い、清算結了してから会社を処分します。
一方、将来的に事業を再開する可能性がある場合は、休眠状態を継続することも可能です。
休眠状態を継続する場合でも、法定手続きや税務申告は適切に行う必要があります。
休眠会社の扱いについては、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
休眠会社を解散する手順
休眠会社を解散する場合、以下の手続きが必要です。
- 株主総会の開催:会社の解散を決議するために、株主総会を開催します。株主総会の解散決議は特別決議が必要です。
- 解散・清算人の登記:株主総会で解散が決議されたら、解散登記と清算人の選任登記を行います。
- 債権者への通知:会社が解散する旨を債権者に通知します。多くの会社で公告する方法は官報にしているので官報で行います。公告後2ヶ月間、債権者からの請求を受け付けます。
- 財産の分配:債務の整理が完了したら、残った財産を株主に分配します。
- 清算結了の登記:財産の分配が終わったら、株主総会で清算事務報告を行います。
- 最終的に、清算結了の登記を行います。これにより、法人格が消滅します。

まとめ
相続が発生した際、休眠状態の会社がある場合は適切に対応する必要があります。
家族経営の会社の場合、特に注意が必要です。
専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『休眠会社が存在する相続時の対応方法と注意点』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら




