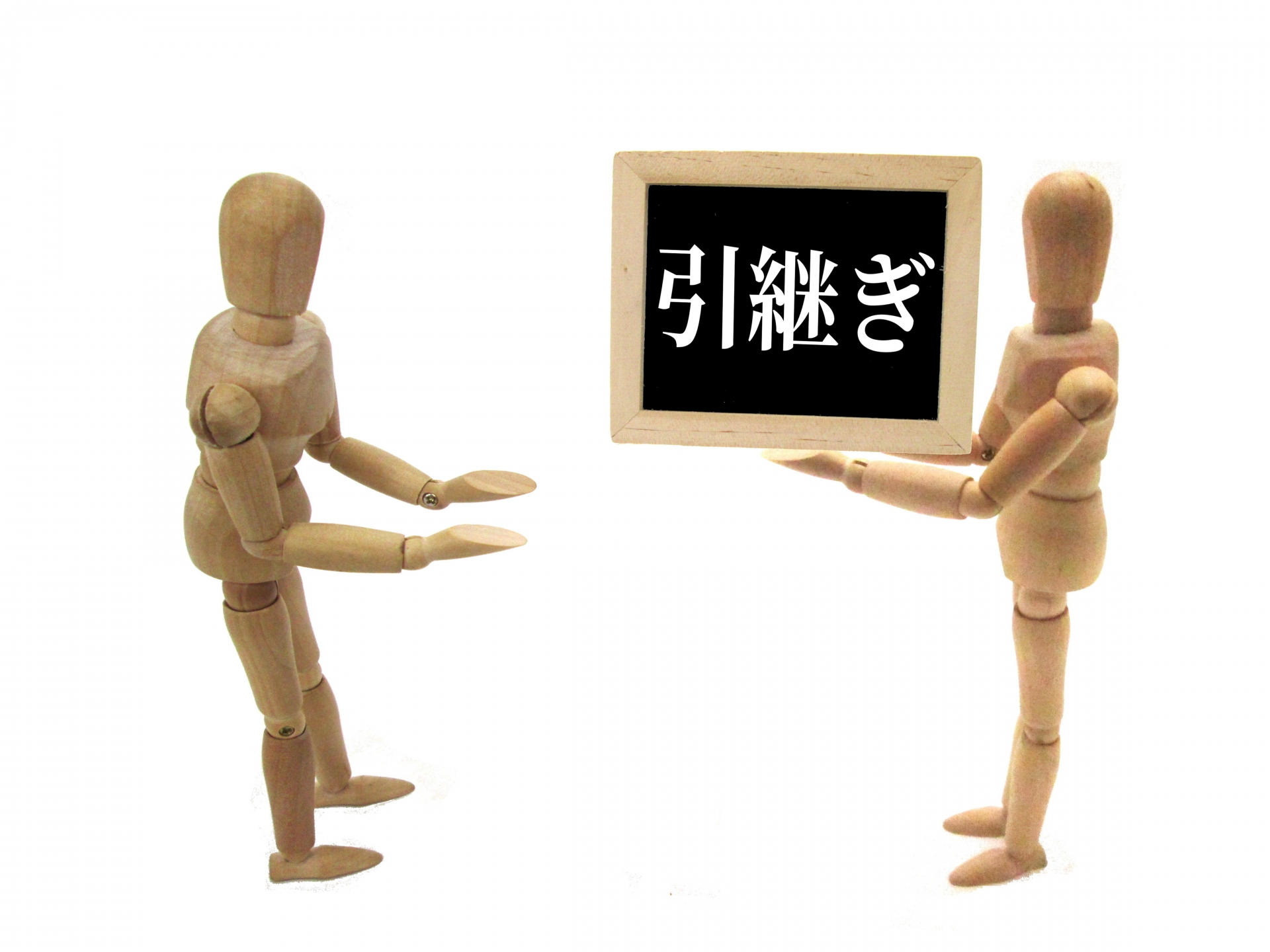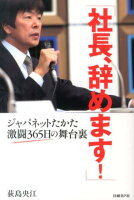東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
事業承継。
このブログでも何度も事業承継のことは触れておりますし、昨日のブログでも「事業承継」の重要性を書きました。
そもそも「事業承継」って何という声も聞こえてきます。
今回は事業承継、会社の片付けのことについて書いていきます。
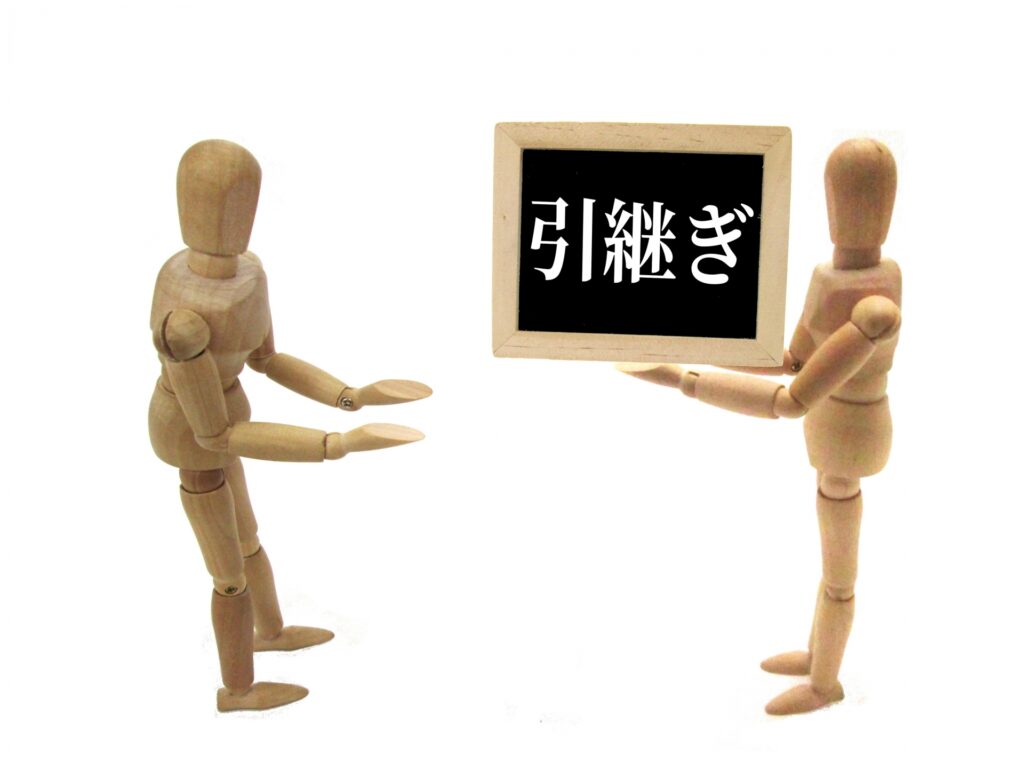
事業承継って何?
そもそも事業承継とは何でしょうか?
簡単に書くと、次の人に経営のバトンをつなげること。
会社というのは永遠に続いていくので、どこかでつなげていかないといけません。
事業承継の方法について、以下のとおりの方法があります。
・子息や従業員に継がせる
・会社自体を売却する(M&A)
・会社をたたむ=自分の代で終わらせる
簡単にはいかない事業承継の問題
まず、会社を設立してから、会社は半永久的に続くということを経営者自身把握しておく必要があります。
人間は、やがて亡くなったり、場合によっては認知症とかになったりしていつまでも同じ人が経営を続けることができません。
承継問題がうまくいかないと、従業員やお客様にも迷惑がかかってしまいます。
また、一番大きいのは経営面です。
事業承継の失敗例は大塚家具とか色々ありますが、数年前、あの有名な「赤福」でも事業承継の失敗例がありました。
「赤福」の場合、最初は息子に後を継がせていました。
ただ、株式は先代が多く所有していて、実質上先代がまだ実権を握っていました。
息子はそれなりに経営手腕を発揮していましたが、先代と息子との対立が表面化してきました。
そこで、先代は息子を社長を解任させ、先代の妻を社長にしました。
現経営者の皆様、よく考えてほしいのです。
このような身内のいざこざが起きてしまうと、会社の周りに対する評価がどうなるのかということ。
また、従業員の気持ちというものを・・・
「数字」・「ヒト」・「ルール」・「ビジネス」
経営していく上で、4つの視点がうまくかみ合い、自分の会社の企業理念とうまくマッチできるような承継をする必要があります。
事業承継というのは会社内の根が深い問題が多く潜んでいるのです。
事業承継 後継者に小計させるのに実際どのくらい時間がかかるのか?
実際、現在の社長から次の世代へバトンタッチするのに時間がかかるでしょうか?
次世代に完全に経営権を移譲できるまで、10年を目安に考えるべきでしょう。
その間に自分の会社の株式の価格の算定や相続問題を始め、会社を売る場合はその価値、後継者教育など事業承継に関してやるべきことは盛りだくさんです。
その間、自分の会社も経営していかなければならないので事業承継にかけられる時間は思った以上にありません。
なので、会社を設立した段階から、次の世代へどうつなげるのか真剣に考えて経営してほしいのです。
先程も書きましたが、同じ人間がずっと会社を経営することはできません。
会社を設立する段階から、次の世代に継がせるにはどうすればいいか考えておくといいでしょう。
▼会社を売却して事業承継する場合はこちらも検討するといいでしょう
会社や事業を譲りたい方(売り手)も、引き継ぎたい方(買い手)も【TRANBI】M&Aプラットフォーム
まとめ(今日の気づき)
事業承継の問題は時間をかけてじっくり取り組む必要がある。
会社設立当初から事業承継のことを考えておかないといけない。
今回は
『事業承継 会社の片づけ~会社を誰にどうやって継がせるか?江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続・事業承継に関するブログはこちらから