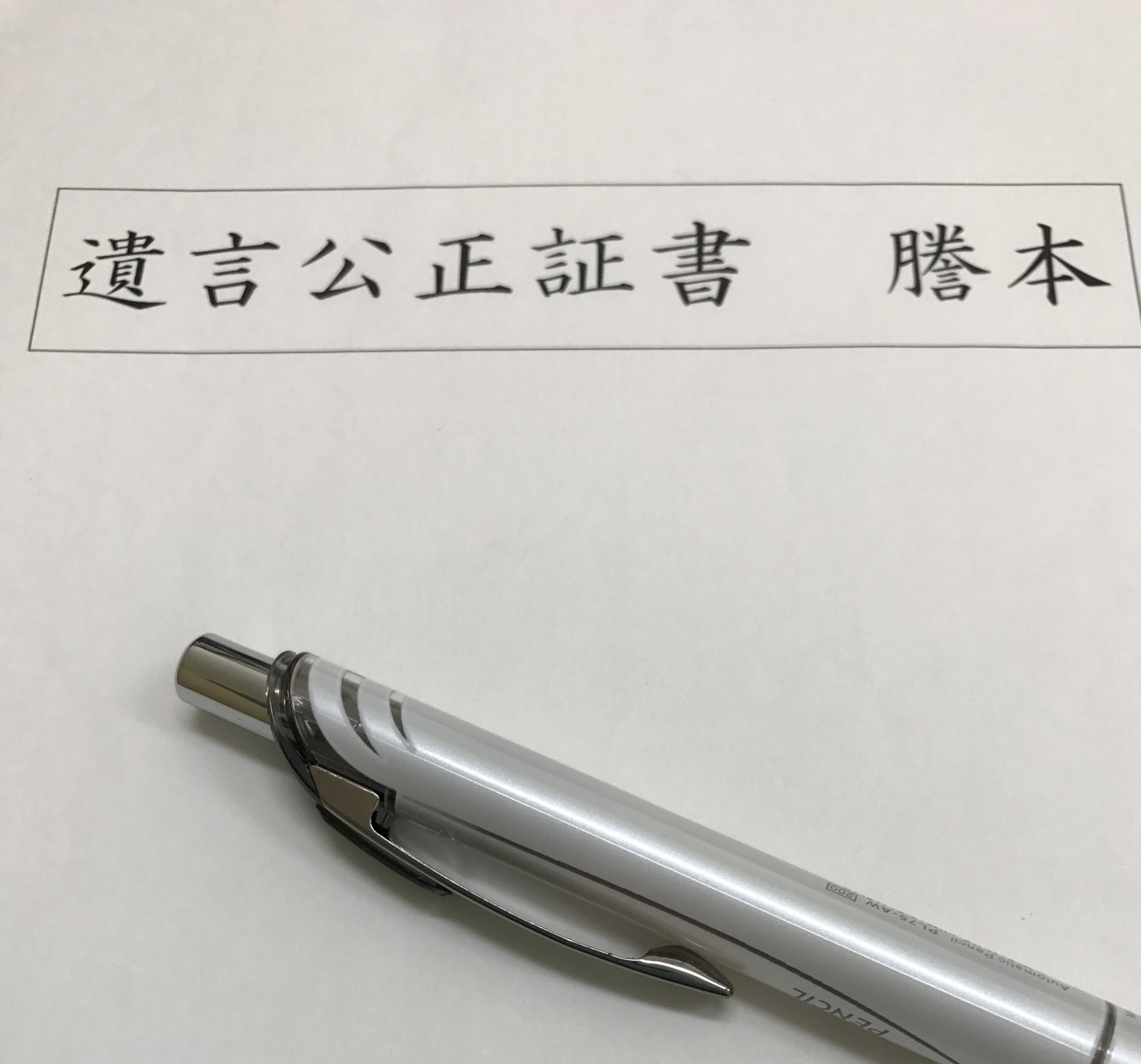東京都江戸川区船堀 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近遺言をする方が増えています。
令和4年1月から12月までの1年間で作成された公正証書遺言は111,977件と10万件を超えています。
また、自筆証書遺言の保管の申請をした件数は20,849件(2020年7月~2021年6月)
遺言を書いている方が徐々に増えている印象です。
そこで自筆証書遺言や公正証書遺言が発見された場合、「相続登記」の手続きはどのように行えばいいか?
あなたの疑問にお答えします。
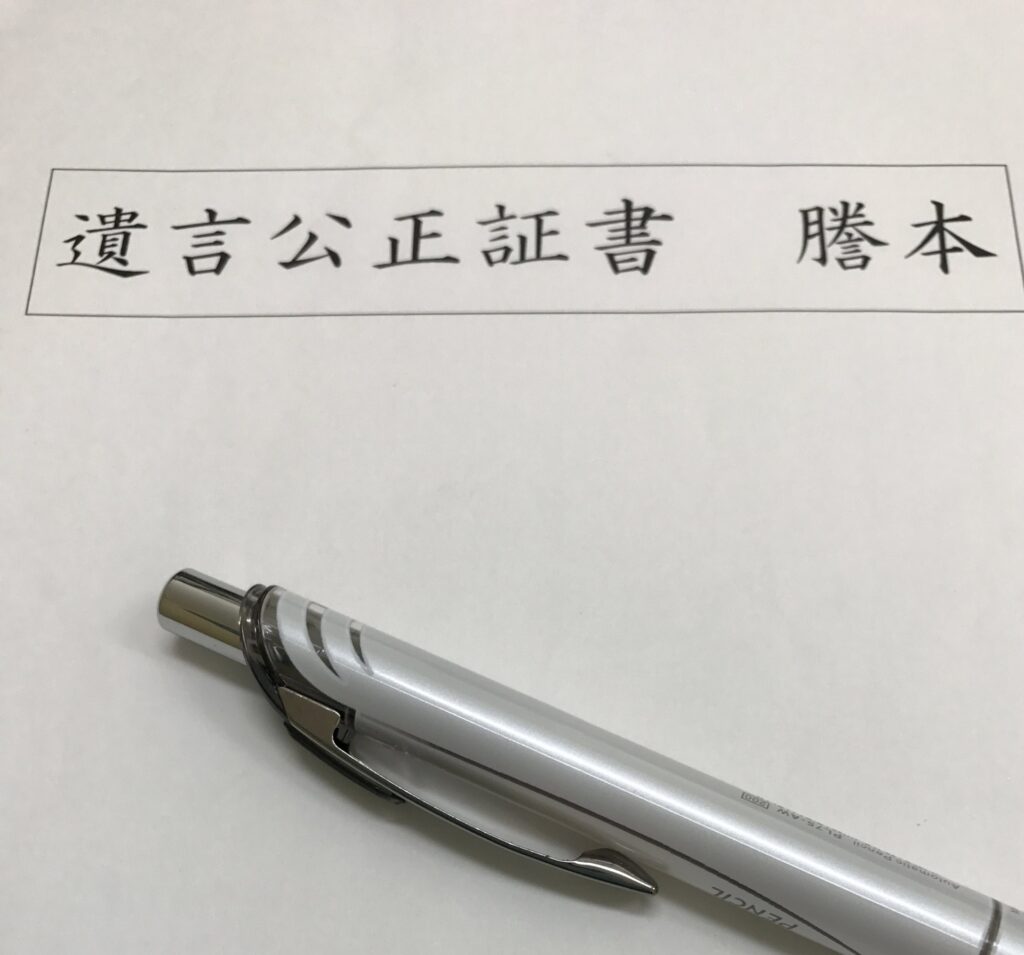
自宅から自筆証書遺言が発見された場合
もし、自宅から自筆証書遺言が発見された場合で、不動産を相続人の誰かに承継させるか決まっている場合、これで相続登記を出せるか?
答えはすぐに出すことはできません。
まずは家庭裁判所で検認手続をする必要があります。
自筆証書遺言が封してある場合はそのまま家庭裁判所にもっていきます。
家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できないことに注意です。
遺言書が封筒に入っていなくても、もしくは開封してしまってもそのまま家庭裁判所で検認手続をします。
法務局で保管してある自筆証書遺言を検索するには、遺言者の死亡後、法定相続人は遺言書保管事実証明書の交付を請求することができ、被相続人が保管を申請した自筆証書遺言の有無を調べることができる。
また、その結果、保管された自筆証書遺言があった場合には、遺言書情報証明書の交付を申請することができ、その証明書は自筆証書遺言原本と同じ効力を持つ書面として利用できます。
なお、法務局に自筆証書遺言を預けた場合、家庭裁判所の検認手続は不要です。
公正証書遺言がある場合
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続は必要ありません。
公正証書遺言については、平成元年以降に行われたものについては、公証役場で検索することができます。
不動産の相続手続の際に必要となる書類は?
不動産を相続人の誰かに承継させる場合を紹介します。
相続人以外の者に不動産を承継させる場合、手続が異なりますので、まずは誰に不動産を承継させるかを確認してください。
登記で必要となる書類は、まずは遺言書です。
先程も書きましたが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受けたものを添付します。
そして相続関係説明図と遺言者が亡くなったという事実と遺言者と相続人のつながりが分かる戸籍謄本等を添付します。
後は相続人の住民票と遺言者の不動産の登記簿上の住所をつなげるため遺言者の住民票の除票が必要です。
住民票については本籍地入りのもので、マイナンバーの記載がないものを添付します。
東京都の場合は、不動産の課税価格を判別するために固定資産評価証明書を添付します。(納税通知書でも可能とされています)
法定相続や遺産分割協議による相続登記との大きな違いは、遺言書で相続登記をする場合、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は不要であること。
相続人が誰かをすべて特定する必要はないからです。

まとめ
これから遺言書を用いた不動産の相続登記案件が増えると思われます。
上記の内容を参考にしていただけると幸いです。
今回は
『相続登記 遺言書があった場合どのように手続をすればいいか?江戸川区船堀の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらを御覧ください。
参考書籍
 | 相続登記の全実務―相続・遺贈と家事審判・調停
田口 真一郎,黒川 龍 清文社 2014-07
| by ヨメレバ | |||
| by ヨメレバ |