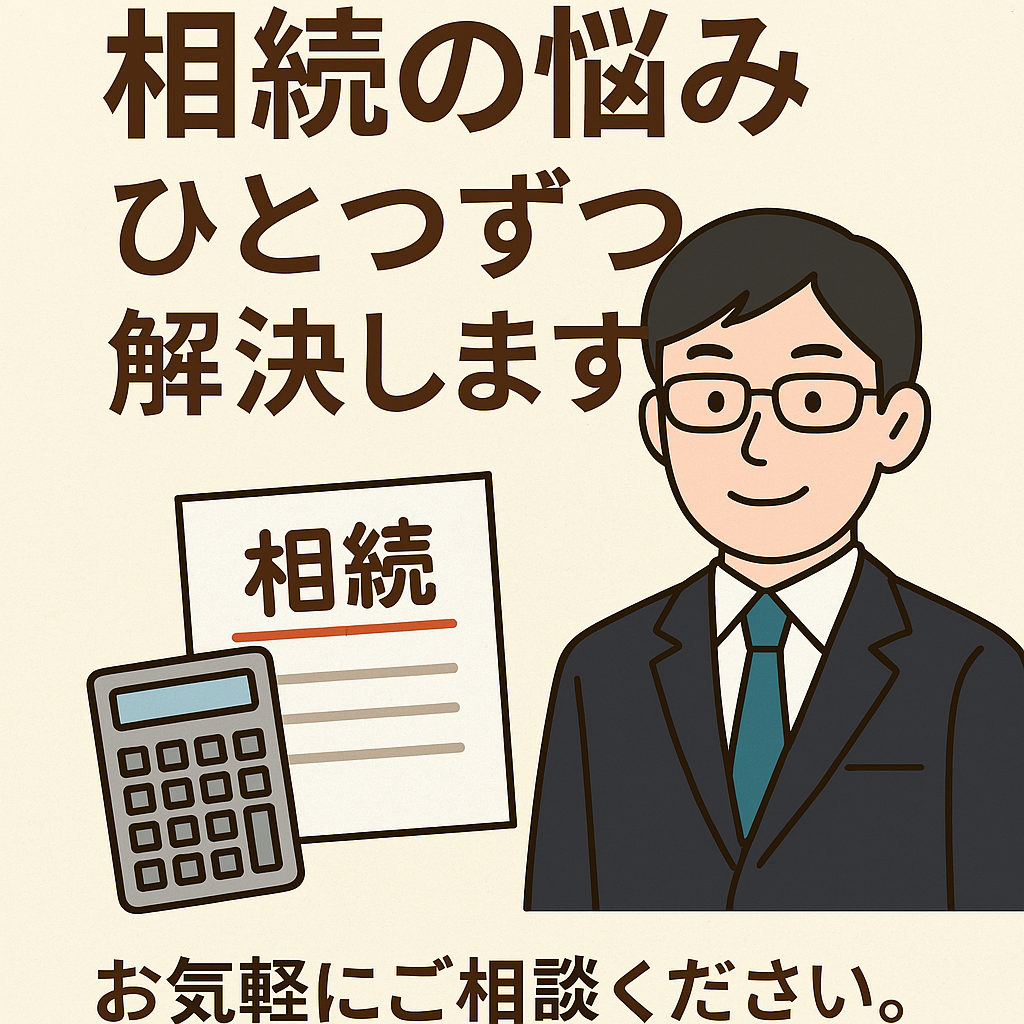こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
「相続」と聞くと、自分にはまだ関係ないと思う方も多いかもしれません。
しかし、親族が亡くなった際に、誰が財産を受け継ぐのかを明確に理解しておくことは、将来のトラブルを防ぐために非常に重要です。
特に、生前に遺言や家族信託などの対策を講じる際には、相続人の範囲と順位を正しく把握しておくことが不可欠です。
江戸川区の司法書士・行政書士きりがや事務所では、相続に関するご相談を多数承っております。
今回は相続人の基本的な知識と、生前対策の重要性について、わかりやすく解説いたします。

相続人とは?
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を法律に基づいて受け継ぐ権利を持つ人のことを指します。
相続人には、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが含まれます。?ただし、誰が相続人になるかは、被相続人との関係や他の相続人の有無によって異なります。
相続人の順位と範囲
法律では、相続人の順位が以下のように定められています。
上位の順位に該当する親族がいる場合、下位の順位の親族は相続人になりません。
第1順位:子ども(直系卑属)
被相続人の子どもが第1順位の相続人となります。
子どもがすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
第2順位:父母(直系尊属)
子どもや孫がいない場合、被相続人の父母が相続人となります。
父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。?
第3順位:兄弟姉妹
子どもや父母、祖父母がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人となります。
なお、配偶者は常に相続人となります。
つまり、配偶者は上記の第1順位から第3順位の親族とともに相続人となります。
相続人を把握することの重要性
相続人を正しく把握しておくことは、生前対策を講じる上で非常に重要です。
以下に、その理由をいくつか挙げます。
1. 遺言書の作成に役立つ
遺言書を作成する際には、誰にどの財産を相続させるかを明確に記載する必要があります。
相続人を正しく把握していないと、遺言書に不備が生じ、遺産分割でトラブルが発生する可能性があります。
2. 家族信託の設計に必要
家族信託を利用する場合、信託契約において受益者や帰属権利者を指定します。
相続人を正しく把握していないと、信託契約が適切に機能せず、意図しない人に財産が渡る可能性があります。
3. 相続トラブルの予防
相続人を事前に把握し、関係性を良好に保つことで、相続発生時のトラブルを未然に防ぐことができます。
特に、再婚や養子縁組など、家族構成が複雑な場合は注意が必要です。
生前対策のすすめ
相続人を正しく把握した上で、生前に適切な対策を講じることが、円満な相続の実現につながります。
以下に、代表的な生前対策を紹介します。?
遺言書の作成
遺言書は、自分の財産を誰にどのように分配するかを明確に示す法的文書です。
公正証書遺言や自筆証書遺言など、形式によって効力や手続きが異なります。
遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぐことができます。
家族信託の活用
家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用してもらう制度です。
認知症などで判断能力が低下する前に契約を結ぶことで、将来の財産管理や相続に備えることができます。

まとめ
相続人を正しく理解し、生前に適切な対策を講じることは、円滑な相続を実現する上で非常に重要です。
江戸川区の司法書士・行政書士きりがや事務所では、相続に関するご相談を承っております。
相続人の範囲や順位、生前対策についてのご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
「相続の悩み、ひとつずつ解決します。」この言葉が、あなたの背中をそっと押せたら幸いです。
今回は
『【相続人の確認】遺言・家族信託を始める前に知っておくべきことを江戸川区の司法書士・行政書士が本音で解説』
に関する内容でした。
電子書籍でさらに詳しく学ぶ:がんばらない相続手続き
相続で悩んでいる場合は、電子書籍『がんばらない相続手続き:効率よく進める3つの方法』をお読みください。
基礎的な相続手続きについて詳しく解説しています。
今すぐ手続きを始めて、安心した未来を手に入れましょう!
あわせて読みたい
相続に関するブログを更新中です。こちらもぜひ御覧ください。