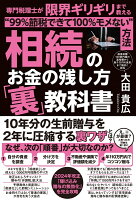こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
前回のブログ「相続とお金 初めて相続に関わる人のために…」では、相続の基本的な手続きを説明しました。
(あわせて読みたいからブログを御覧ください)
今回は、相続手続きを進めるための具体的なステップと、費用面について詳しく解説します。
相続でお金がかかるかもしれないことを心配している40代から50代の皆さんに役立つ情報をお届けします。
最後までぜひ御覧ください。

遺言書の確認と検認
相続の第一歩は遺言書の確認です。
遺言書が存在する場合、その内容に基づいて財産を分配します。
公正証書遺言を残している場合には、公証役場で検索することが可能ですし、自筆証書遺言で法務局に保管している場合も見つけることができます。
自筆証書遺言で法務局に保管していない場合は家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きを受ける必要があります。
検認とは、遺言書の内容を確認し、改ざんされていないことを証明する手続きです。
この手続きを行わないと、遺言書の効力が認められません。
検認手続の申立てに必要な費用は、遺言書1通につき800円(収入印紙)です。
遺言書が封書の場合は封書1通につき800円となります。
検認後に必要な費用は、検認済証明の申請後に検認済証明書を貼り付けた遺言書原本を返還してもらう手数料で、遺言書1通につき150円かかります。
なお、相続登記で自筆証書遺言書を用いるときは、家庭裁判所で検認手続を経たものでないといけないので注意してください(法務局保管制度を利用した場合は除く)。
相続人の確定と相続放棄
次に行うのは相続人の確定です。
相続人とは、法律で定められた遺産を受け取る権利を持つ人のことです。
具体的には、配偶者や子供、場合によっては両親や兄弟姉妹が該当します。
相続人が確定したら、各相続人が相続を受け入れるか放棄するかを決定します。
相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行い、正式に放棄の手続きを取る必要があります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をする際に必要な費用は、相続人1人あたり収入印紙800円分と、家庭裁判所との連絡用の郵便切手300円~500円程度です。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要な場合は発行費用がかさむ可能性もあります。
相続財産の評価と相続税の申告
相続財産の評価は、相続税の計算に直結します。
不動産、現金、預貯金、株式などの財産を正確に評価することで、相続税の額が決まります。
相続税は、一定の控除額を超える場合に課税されます。
相続税の申告と納税は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。
適切な評価と申告を行うために、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
税理士などの専門家に依頼する場合、その費用も考慮に入れておく必要があります。
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人全員で行う遺産分割協議は、相続財産をどのように分配するかを決定するための話し合いです。
全員が納得する形で協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
この協議書は全相続人の署名と押印が必要です。遺産分割協議書が完成したら、不動産の名義変更や預貯金の引き出しなど、具体的な財産分割の手続きを進めることができます。
相続登記には登録免許税を納める必要があり、その他の相続手続きにも費用がかかることを考慮し、余裕を持って準備しましょう。
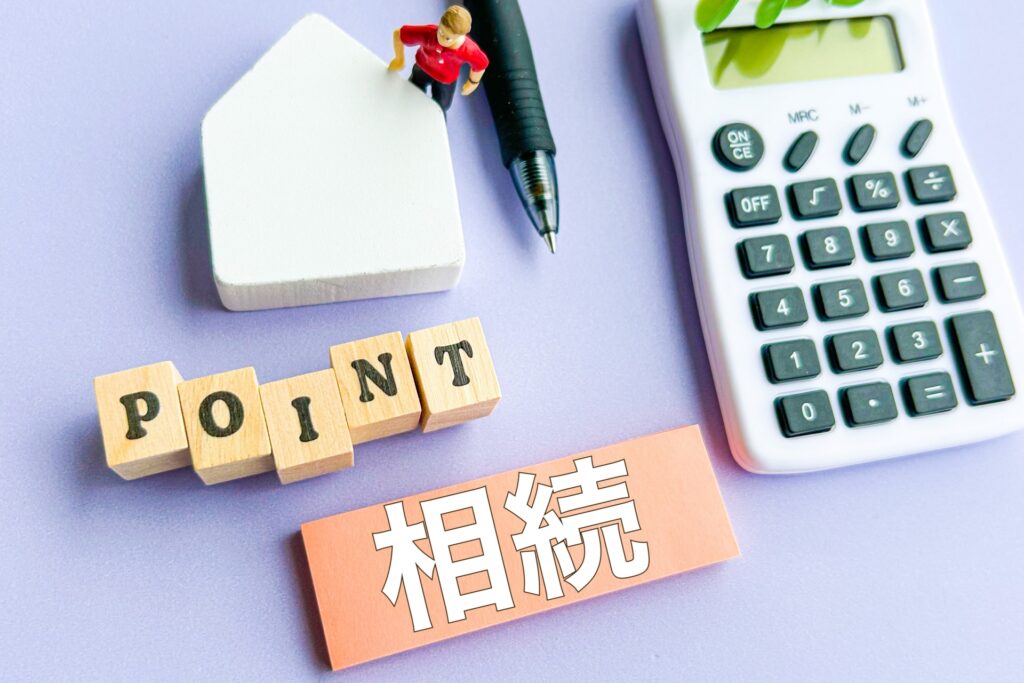
まとめ
相続手続きは複雑で、多くの人にとって初めての経験となりますが、適切な手順を踏むことでスムーズに進めることができます。
遺言書の確認と検認、相続人の確定と相続放棄、相続財産の評価と相続税の申告、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を順に行いましょう。
専門家のアドバイスを受けながら進めることで、トラブルを避け、安心して相続手続きを完了させることができます。
費用面でも計画的に準備を進めることで、予期せぬ出費に備えることができます。
この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『40代50代向け相続手続きの費用とポイント:お金の不安を解消しよう』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら