目次
はじめに
こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
前回は「相続税・贈与税の土地の評価」を中心に紹介しました。
まだの方は、ブログにも書きましたので、ぜひ「あわせて読みたい」から前回のブログをお読みください。
今回はその続きとして、小規模宅地等の課税価格の特例に焦点を当てます
今回もFP2級の試験範囲での紹介にとどめますので、詳しく知りたい方は、税理士に相談してください。。
この本では、FP試験に必要な知識だけでなく、実際に役立つファイナンシャルプランニングの技術についても学べます。
「みんなが欲しかった! FPの教科書 2級」
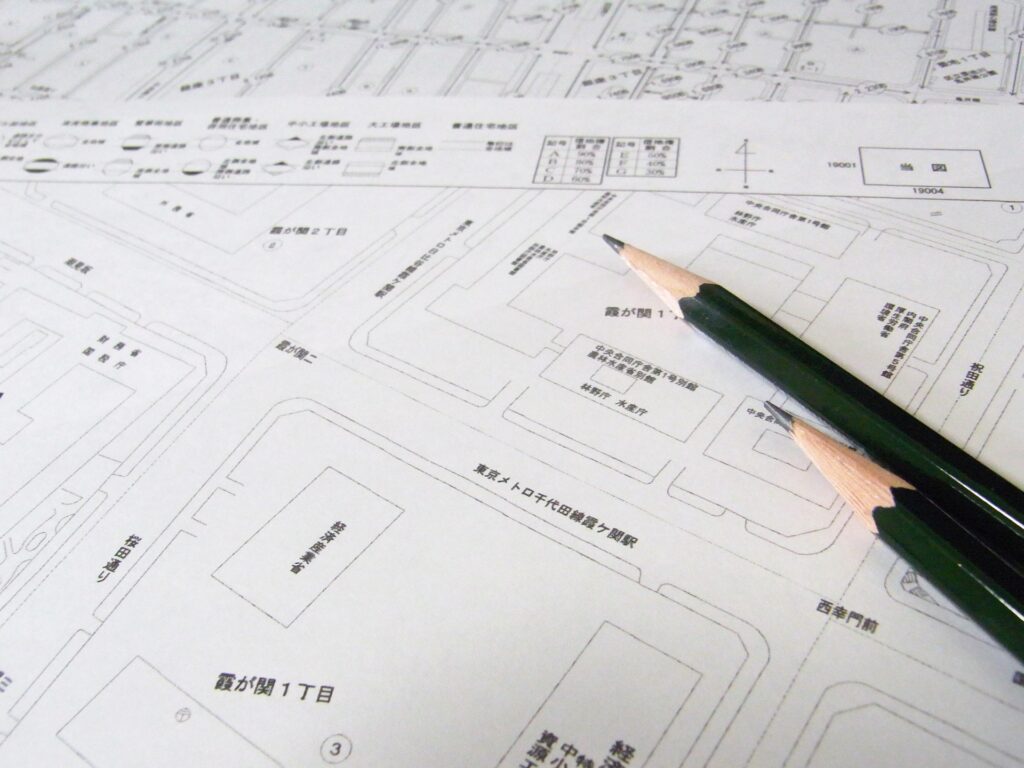
小規模宅地等の課税価格の計算の特例とは?
この特例を知っておくことは相続税対策の一つとして大事なことです。
被相続人の居住用や事業用であった宅地等に高額な相続税を課してしまったらどうなるでしょうか。
そうなると、被相続人が亡くなったあと、相続人が居住したり、事業を引き継ぐことができなくなり、不経済になりますよね。
そこで、一定の要件を満たした宅地には、通常の評価額から一定の割合の評価減を受けることができます。
これが「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」です。
なお、この特例は、相続税のみ適用できて、贈与税の場合には適用できないことに注意です。
適用対象となる宅地の要件
「小規模宅地等の課税価格の特例」の要件を知ることが相続税対策の一歩といえます。
要件は次のとおりです。
- 被相続人または被相続人と生計を一にする親族の、事業用または居住用の宅地であること→ただし、別生計の親族の事業用または居住用の宅地は適用できません。
- 建物または構築物の敷地であること→空き地や青空駐車場の場合は適用できません
- 申告期限までに遺産分割が終了していること→未分割の場合は適用できませんが、申告期限から3年以内に分割が確定した場合は適用できます。
減額割合・限度面積
小規模宅地等の課税価格の特例を受けた場合の減額割合と適用面積は、宅地等の利用区分によって異なります。
| 宅地等の利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | ||
| 居住用 | 特定居住用宅地等 →被相続人が居住用に供していた宅地で、配偶者や一定の親族が取得した宅地 |
80% | 330㎡ | |
| 事業用 |
貸付事業以外 の事業用 |
特定事業用宅地等宅地 →被相続人が貸付事業以外の事業用に供した宅地で一定の親族が取得等した宅地 ※相続開始3年以内に事業の用に供された宅地は除かれます。 |
80% | 400㎡ |
| 貸付事業用 | 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ | |
| 貸付事業用 ※相続開始3年以内に貸付事業の用に供された宅地等は除きます |
50% | 200㎡ | ||
ここで、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等を併用する場合、限度面積として合計730㎡まで適用可能です。
具体的な計算方法
この特例によって、宅地の評価額から減額される金額は次の計算式によって求めます。
減額される金額=宅地の評価額×限度面積(総面積が上限)/総面積×減額割合(80%または50%)
具体的な計算方法について紹介します(「みんなが欲しかった! FPの教科書 2級」より)
例1 地積:400㎡ 特例適用前の評価額:6,000万円 特定居住用宅地等に該当
減額される金額:6,000万円×330㎡/400㎡×80%=3,960万円
課税価格:6,000万円-3,960万円=2,040万円
例2 地積:500㎡ 特例適用前の評価額:9,000万円 特定事業用宅地等に該当
減額される金額:9,000万円×400㎡/500㎡×80%=5,760万円
課税価格:9,000万円-5,760万円=3,240万円
その他の要件
「小規模宅地等の課税価格の特例」を受けるためには、特例適用後の相続税額が0円になった場合であっても、相続税の申告書を提出する必要があります。
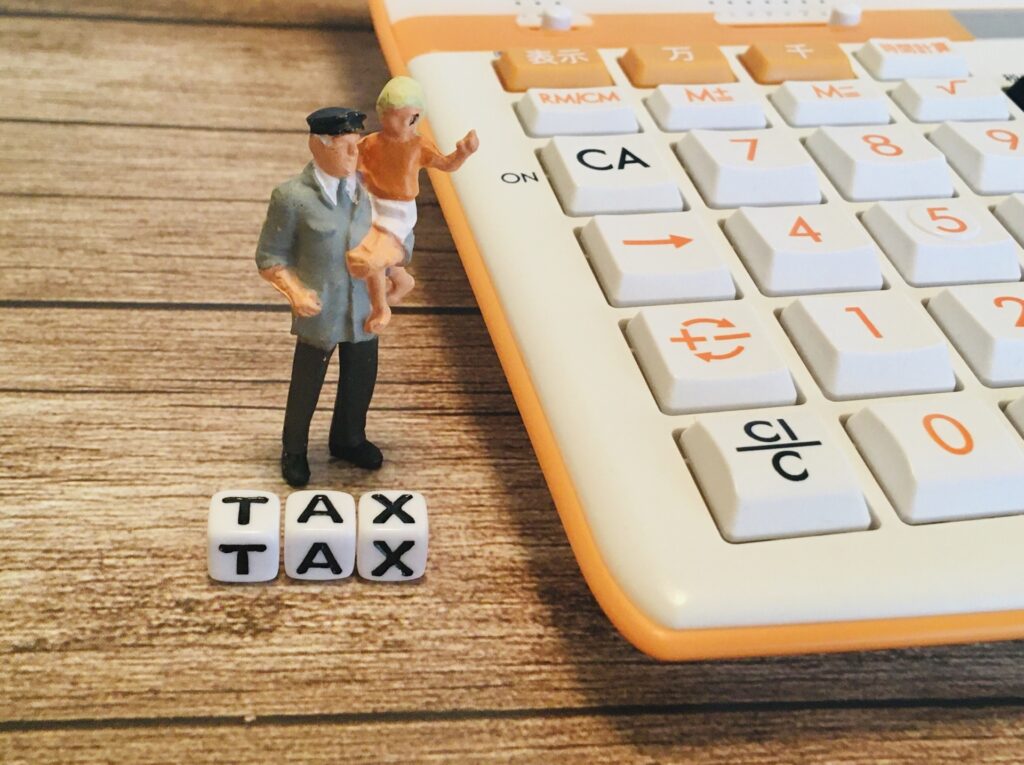
まとめ
相続税・贈与税の評価と相続税の「小規模宅地等の課税価格の特例」を希望される場合、生前相続対策として活用する場合、自分で判断せず、税理士を活用してください。
この記事はあくまでもこの制度があるという紹介にとどめています。
ただ、知っておけば、相続税対策に使えますので、専門家のアドバイスを参考に活用することをおすすめします。
細かい要件など詳しくは国税庁のHPも確認してください。
「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(国税庁HP)
今回は
『小規模宅地の特例とは?相続税を抑えるポイントを司法書士が解説』
に関する内容でした。
当事務所のウェブサイトをチェック
「司法書士・行政書士きりがや事務所」
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら



