東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「資格合格逆算メソッド」。
合格(=受験日)点を取るために、逆算して今何をすべきかを考えるメソッドです。
アウトプットの教材として、資格試験では「過去問」が必須。
過去問は何回回せばいいですか?
過去問何度も回しても無駄だ
という意見を聞きます。
今回は「資格合格逆算メソッド」の著者の立場で「過去問」のあり方を考えます。
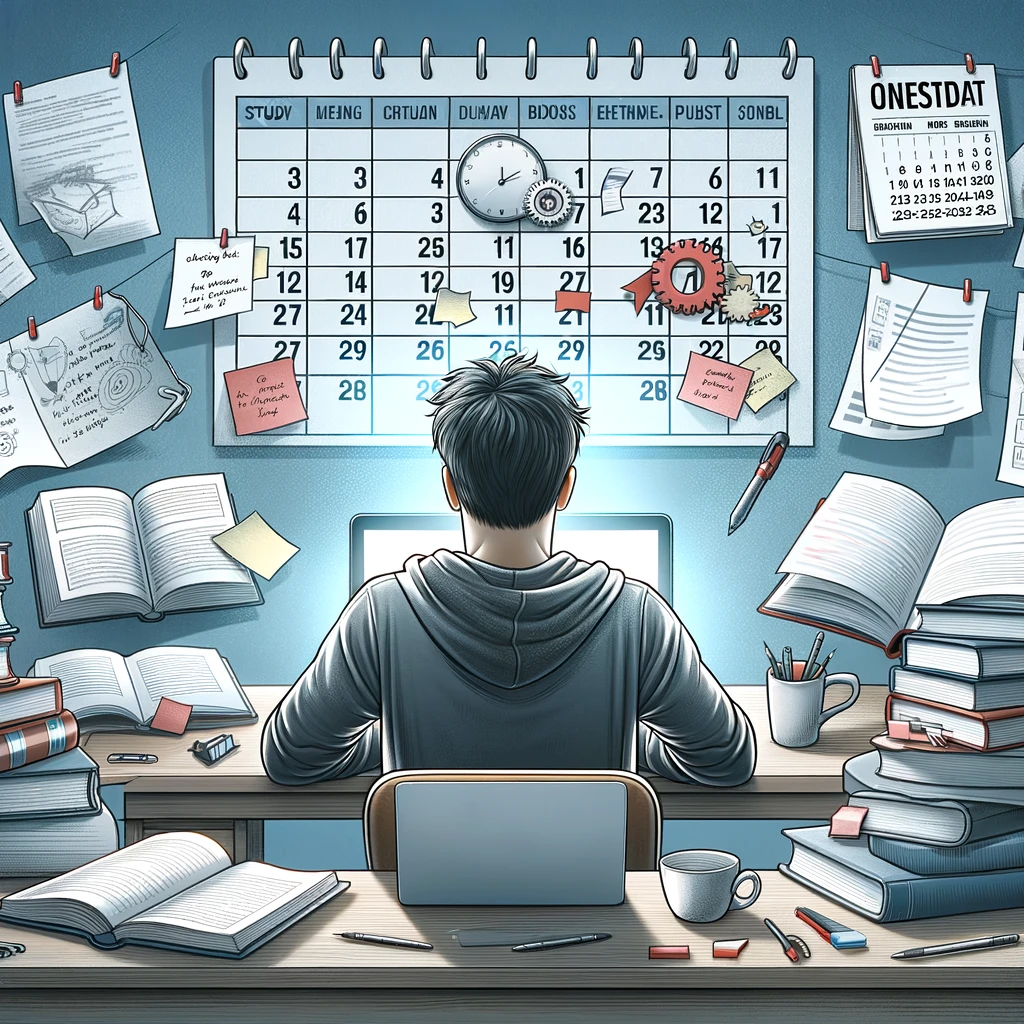
過去問を勉強しないで資格試験を語ることなかれ
「資格試験」を目指す以上は「過去問」は必須です。
テキストも過去問ベースで書いていますが、実際のテキストの記載が過去問でどう聞かれているのか、問題をみなければわかりません。
また、問題を解くのにどのことを理解すれば解答に至るかをしる上でも過去問はみておかないとお話になりません。
なので、難関国家資格試験を受ける以上は、「過去問」は切っても切れない関係になります。
過去問をどう活かすかで合否が変わってくる
私は、過去問を何回も回し、答えを導く根拠や選択肢の消去、その時点での知識がわからないときを想定して、どの選択肢で勝負するかとか多角的にみていました。
過去問を多角的に見るということが実は大事になります。
なので、何度も過去問を回しても正直意味はありません。
勉強段階に応じた「過去問」の使い方が大事になります。
「過去問」の上手な使い方を紹介します
まずは、テキストを読み終えたときに過去問を解く。
その時は間違えていてもいいので、またテキストにもどり、テキストをインプットし直す。
また、次の段階で過去問を解く。
はじめに解いたときに比べると期間が空いているため、もしかしたら間違えるかもしれない、
その場合は、また該当場所を確認する。
次に過去問を解くときは答えを知っている可能性があるので、問題文をしっかり読み込み、関連知識を意識しながら解いてみる。
次は、自分で根拠を確認しながら過去問を解いていく。
さらに年度別で解いてみる…
過去問の使い方はその都度変わってくるので、1回や2回では回し切れないのが私の結論です。
何度もしつこく回していくと答えを覚えていき意味はないという方もいますが、使い方次第でインプット教材にもなります。
逆に、分厚いテキストを読むよりも時間をかけずに復習にも活用できるので、「過去問」は最高の勉強教材となるのです。
最初の頃は過去問を解きながら、関連事項をノートに丁寧にまとめていた時期がありました。
しかし、ノート作る時間は無駄ですし、関連事項はテキストに書き込めばいいことに気づきました。
なので「テキスト」は辞書的に「過去問」はインプット・アウトプット教材みたいに司法書士の勉強はしていきました。
一問一答集の過去問集の活用方法
難関資格試験の過去問集は分厚くて持ち運びも面倒。
スキマ時間でも勉強したい方には、一問一答形式の過去問集を使うのもありです。
知識の整理にもなりますし、過去問を解いている感覚になるので、重宝します。
解説はそこまで細かく書いているものでなくていいので、自分が使いやすいものを利用するといいでしょう。

まとめ
過去問を何回回せばいいのかという質問は実は野暮な質問です。
自分の勉強段階で「過去問」の使い方も変わってくることを意識してください。
今回は
『「資格合格逆算メソッド」:過去問で効率的に学習する秘訣』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください


