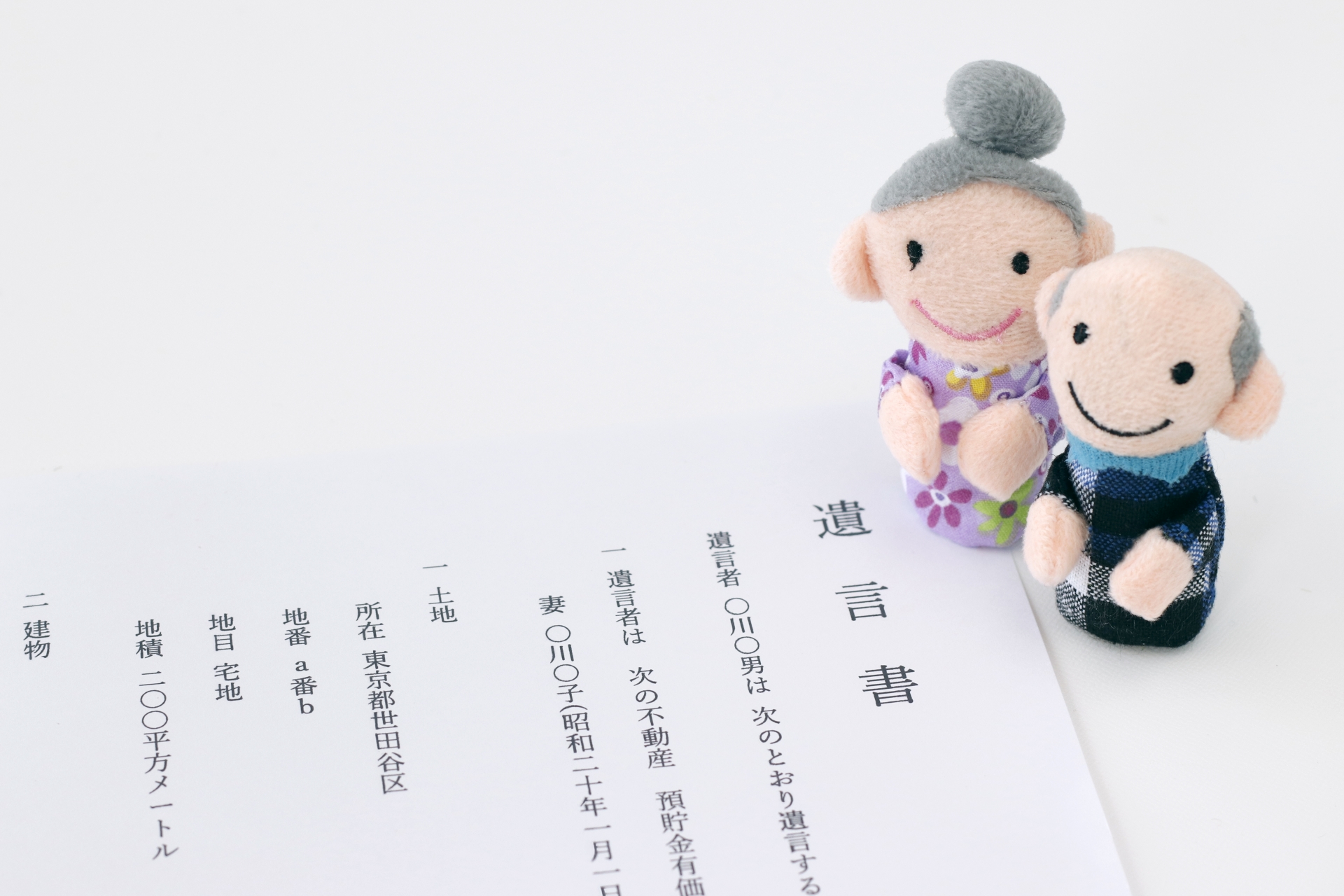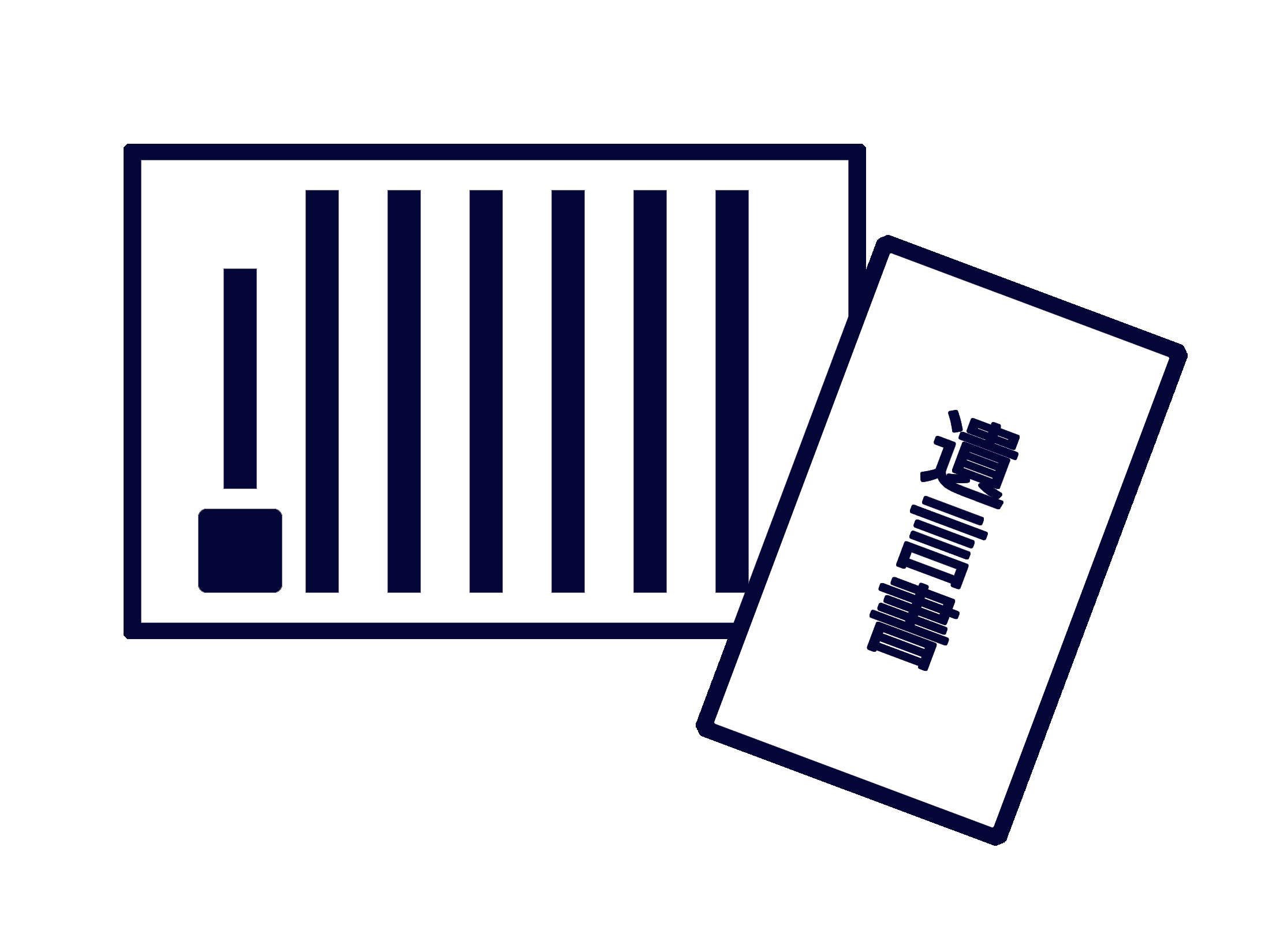東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
これから遺言書を書き始めたいのですが、家族構成がやや複雑です。
なにか気をつけないといけないことはありませんか?
最近は相続開始前の「遺言書」の作成が注目されています。
今回は「遺言書」を書くにあたり、注意すべきところを紹介します。

遺言書を書くにあたっての今回の事例
私の現在の家族は4名です。自分と妻と子供2名と住んでいます。
しかし、私には離婚歴があり、前妻の間に子供が1名いますが、全然連絡が取れていません。
最近その子とは疎遠になっています。
このような場合、「遺言書」を書くにあたり、どのようなリスクが存在するでしょうか?
次から、以下の質問者の家族の場合、「遺言書」を書くとき、どこに注意したらいいかを紹介します。
問題点1 疎遠な前婚の子供の問題
前妻は法定相続人にはなりませんが、前妻の子供は法定相続人となります。
なので、「遺言書」を書かない限り、その子も交えて遺産分割協議をする必要があります。
「遺言書」によってその権利を制限することが可能ですが、これを明確に記載していないと後でトラブルの原因となる可能性があります。
ただし、注意なのは遺言によって前婚の子供の相続権を完全に取り除くことはできません。
最低限の遺留分が保証されています。
問題点2 遺留分の問題
遺留分とは何か?
遺留分とは、特定の法定相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を指します。
要するに、法律が定めた一定の範囲内で、遺言によって相続財産を自由に分けることができますが、その範囲を超えると遺留分として相続人に保障された権利が発生します。
なぜ遺留分を無視できないのでしょうか?
遺留分は法律によって保護された権利です。
もし遺留分を守らない遺言を残した場合、遺留分権者は遺留分減殺請求をすることができます。
これにより、遺言で定めた分配が変わる可能性があるため、事前に注意が必要です。
相続人が遺留分の権利を主張する場合、遺言に基づく分割が覆される可能性があります。
なので、前妻の子供のことを考えないで「遺言書」を書いてしまうと遺留分の問題が起きるので注意です。
ちなみに遺留分は法定相続分の半分です。
例えば、子供1人の法定相続分が1/2であれば、その遺留分は1/4となります。
今回の事例だと、前婚の子も遺留分の権利があるため、その子の遺留分も考慮に入れる必要があります。
問題点3 遺言書の形式と内容の正確さ
遺言書の形式や内容に不備があると、その部分や全体が無効となる可能性があります。
特に自筆証書遺言の場合、正確な形式を守る必要があります。
問題点4 家族間の対立
前婚の子供と現在の家族との間で、相続に関する対立が生じる可能性があります。
遺言書に明確な指示を書くことで、これをある程度は防ぐことができます。
法的効力はありませんが「付言事項」は必ず書く必要があるでしょう。
問題点5 遺言を一度書いて内容を変更したい場合の問題
遺言者の状況や意向が変わることで、遺言書の内容も変更する必要が生じることがあります。
遺言書を定期的に見直すことの重要性をアドバイスすることが大切です。
なお、その場合は後の遺言で前の遺言の内容と抵触する場合は、その部分に関しては無効となります。
ただ、曖昧な遺言の撤回は争いのもとになるので、後の遺言を書くときに前の遺言の内容はすべて無効とするなどの対策が必要です。

まとめ
遺言は、家族関係が複雑な場合は書いておくことが大事になります。
自分の思いを相続人に伝えるためにもぜひ「遺言書」を活用しましょう。
今回は
『複雑な家族構成の人が知るべき!遺言書の作成時のポイントを江戸川区船堀の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら