東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分」について紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。

共有物の管理者に関する現行の問題点は?
現行の共有に関する規定では共有物の管理者に関する規定はありません。
なので、共有物に管理者を選び、管理を委ねることができれば、共有物の円滑な管理の観点からは有用です。
また、管理者の選任の要件や権限の内容が明文規定がないので、判然としないという問題がありました。
共有物の管理者に関する改正内容は?
管理者の選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の価格の過半数で決定します。
共有者以外の人を管理者とすることもできます。
管理者は、管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができます。
なお、軽微でない変更を加えるには、共有者全員の同意が必要です。
所在等不明共有者がいる場合には、管理者の申立てにより裁判所の決定を得た上で、所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て、変更を加えることができます。
管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従ってその職務を行わなければいけません。
違反すると共有者に対して効力を生じませんが、善意(決定に反することを知らない)の第三者には無効を対抗することはできません。
活用例としては、共有物の使用者が決定していないケースで、管理者が第三者に賃貸するなどして使用方法を決定するケースです。
なお共有者が使用する共有者を決定していたのに、管理者が決定に反して第三者に賃貸した場合、共有者は事情を知らない第三者には対抗できないことになります。
共有の規定と遺産共有持分に関する問題点
共有に関する規定は、持分の割合に応じたルールが定められています。
ただ、相続により発生した遺産共有では、法定相続分・指定相続分と具体的相続分のいずれが基準になるのか不明確で問題になっていました。
共有の規定と遺産共有持分についての改正法は?
遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分(相続分の指定があるケースでは、指定相続分)により算定した持分を基準とすることが条文で明確化されました。(新民法898条2項)
(共同相続の効力)
第898条
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
事例として、遺産として土地があり、A、B、Cが相続人(法定相続分各3分の1)であるケースでは、土地の管理に関する事項は、具体的相続分の割合に関係なく、A・Bの同意により決定することができるようになります。
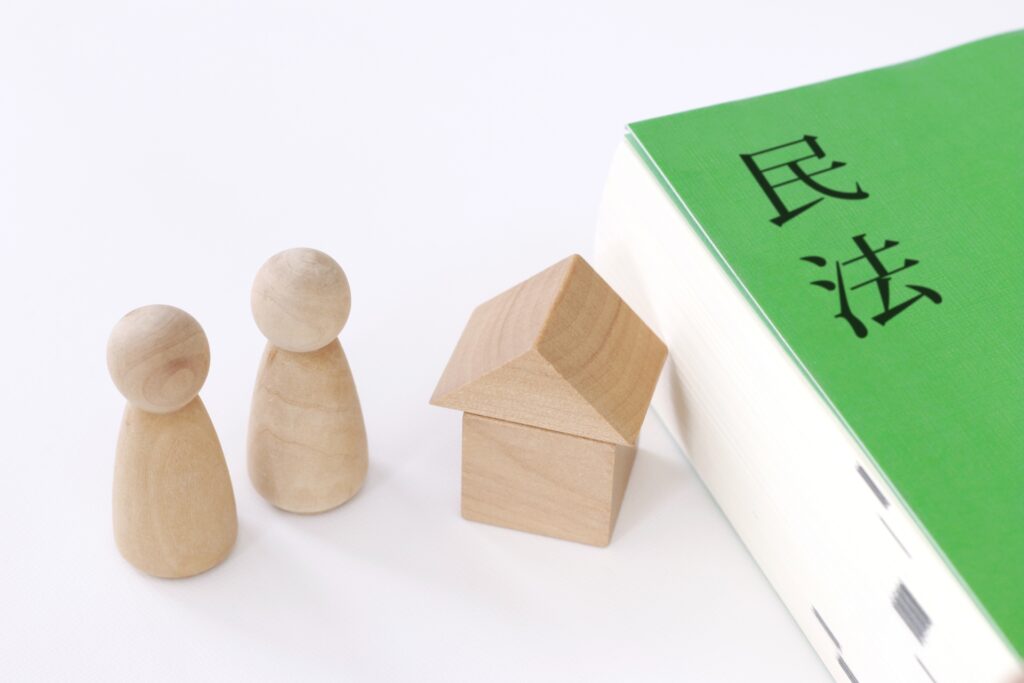
まとめ
共有物の管理者についての規定及び共有の規定と遺産共有持分のルールが明確になりました。
今後の実務の動きに注目したいところです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 「共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
民法改正に関するブログはこちら



