東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、実務でも影響しそうな「所有者不明土地・建物管理制度の改正点」について2回に分けて紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。

現行法での所有者不明土地・建物の管理
現行法では、土地・建物の所有者が、調査を尽くしても不明である場合には、土地・建物の管理・処分が難しくなります。
現行法では、公共事業の用地取得や空き家の管理など所有者の所在が不明な土地・建物の管理・処分が必要であるケースでは、現行法上、所有者の属性等に応じて下記の財産管理制度が活用されています。
不在者財産管理人(現民法25条1項)は、従来の住所等を不在にしている自然人の財産の管理をすべき者がいない場合に、家庭裁判所により選任され、不在者の財産の管理を行います。
相続財産管理人(現民法952条1項)は、自然人が死亡して相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所により選任され、相続財産の管理・清算を行います。
清算人(会社法478条2項)は、法人が解散した(みなし解散を含む)が、清算人となる者がない場合に、地方裁判所により選任され、法人の財産の清算を行います。
現行法上での問題の所在
現行の財産管理制度(不在者財産管理人、相続財産管理人、清算人)は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっています。
財産管理が非効率になりがちになり、申立人等の利用者にとっても負担が大きいです。
土地・建物意外の財産を調査して管理しなければならず、管理期間も長期化しがちです。
さらに予納金の高額化で申立人にも負担が大きいのも問題です。
また、土地・建物の共有者のうち複数名が所在不明者であるときは、不明者ごとに管理人を選任する必要があり、更にコストがかさんでしまいます。
現状では、所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の各種の財産管理制度を利用することができないことが問題になっています。
改正法の概要
現行法上の問題を解決するために、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度を創設しました(新民法264条の2~264条の8)。
この制度が創設されるため、土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現することができるようになります。
他の財産の調査・管理は不要となり、管理期間も短縮化するため、予納金の負担も軽減されます。
また、複数の共有者が不明となっているときは、不明共有持分の総体について一人の管理人を選任することも可能になります。
そのことで、所有者が特定できないケースについても対応可能になります。
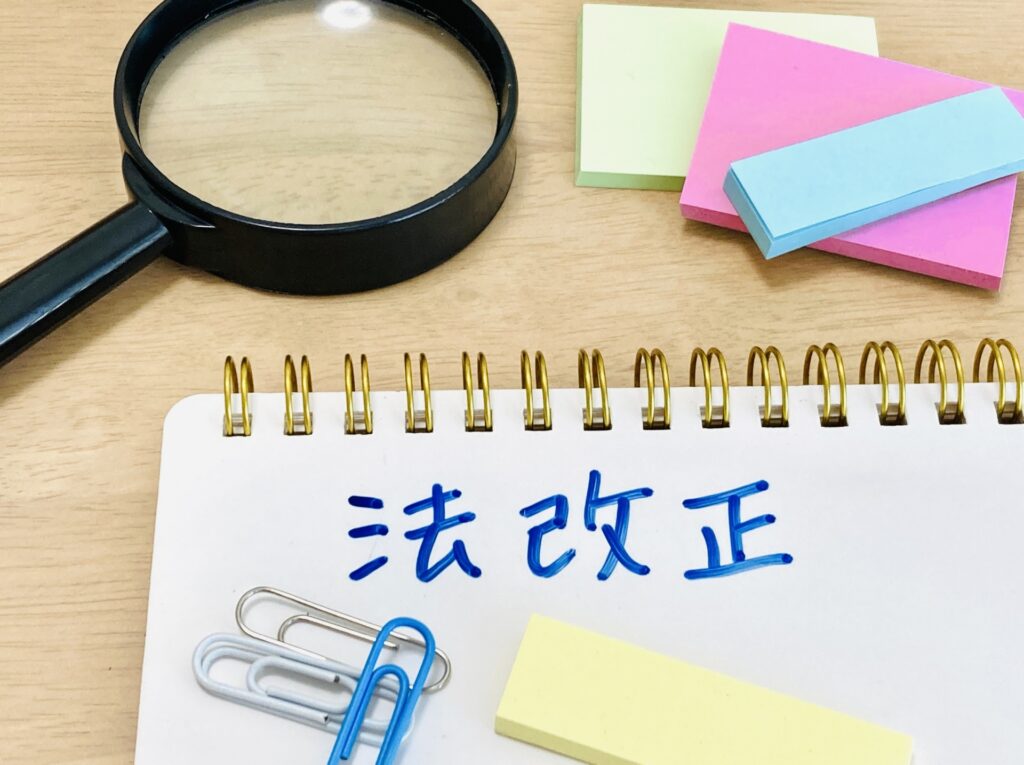
まとめ
所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度ができることで、問題が解決できるのか、これからの実務の動きに注目したいところです。
詳細については、また改めて紹介します。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「所有者不明土地・建物管理制度の改正点」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
民法改正に関するブログはこちら



