東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日司法書士試験の最終合格発表がありました。
私の出身大学でも3年生が合格していました。
この試験の特徴を再度確認するとともに、何が大事なのかも触れていきます。
なお、私自身は予備校関係者でもありませんし、ただ資格試験アドバイザーとしての肩書を有しているに過ぎないことを書いておきます。

令和4年度の司法書士試験の最終結果について
令和4年度の最終結果は下記のとおりです。
合格者数:660名(昨年度が613名だったので37名増加)
出願者数:15,693名(昨年度比 +705名)
受験者数:12,727名(昨年度比 +802名)
対出願者合格率:4.2%(昨年度比 +0.1%)
対受験者合格率:5.2%(昨年度比 +0.1%)
最高年齢:71歳(昨年度:77歳)
最低年齢:20歳(昨年度:21歳)
平均年齢:40.65歳(昨年度:41.79歳)
令和4年度の司法書士試験の結果からわかること
データをみると、対出願者合格率、対受験者合格率が上昇しています。
以前は司法書士試験の合格率は3%台と言われていましたので、やや易化している感じを受けます。
とはいっても、合格率は相変わらず5%台ということで、それなりの対策を講じないといけないことが分かります。
出願者・受験者数が増加していることを考えると、コロナ禍で何か資格試験の勉強をしようとする方が少し増えてきているように感じます。
何か手に職をつけたい人も多いのかとも感じます。
来年以降の対策をどう考えるのか?
コロナ禍の影響で、資格試験の勉強を始めた人は増えているようです。
なので、独立系の難関資格試験をうけて合格して副業として士業を選ぶ方も個人的には増えるのかと思っています。
司法書士試験は科目数が多いのが特徴です。
となると、出題科目が多い民法や会社法、不動産登記法や商業登記法はある程度しっかり勉強しないと受かりません。
それとともに、受験界でマイナー科目と言われている民事訴訟法や民事執行法・民事保全法もしっかり勉強しないと受かりません。
その他の憲法・刑法・供託法・司法書士法もしっかり勉強しないといけません。
こういう試験の場合、まずは過去問で出題されている部分はしっかり押さえることが重要です。
あと、偏りのある分野が出題されているので、ここも基礎としてしっかり押さえる必要があります。
どうしても、長期受験生は余計なことをしがちで、試験の範囲外で点を稼ごうとする傾向があります。
しかし、基礎の部分をしっかりおさえれば8割の点数は確保できます。
残り2割は現場思考力で対応するしかないので、まずは8割しっかり確保できるような勉強をすべきです。
いわゆる絞り込みの勉強が大事になります。
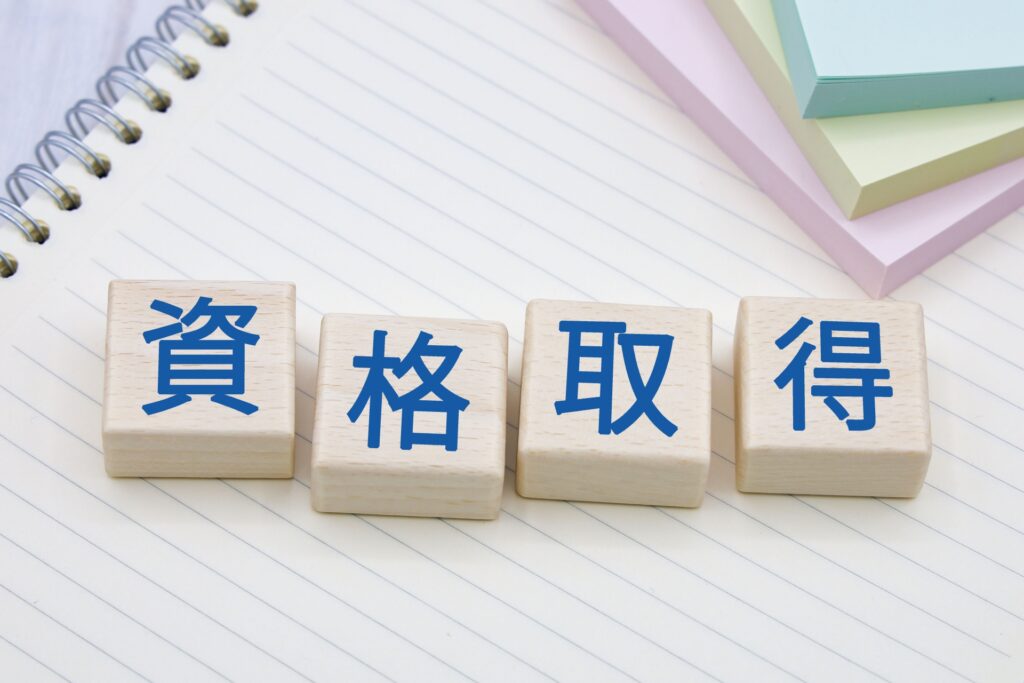
まとめ
司法書士試験の合格率は上がってはいますが、それでも難関資格試験の一つです。
まずは手を広げず、テキストに書かれていることに集中して取り組むこと、過去問をしっかりやることが合格への第一歩です。
今回は
『資格試験 令和4年度の司法書士試験最終結果発表 今後どうやって勉強していくかを江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
資格試験に関するブログはこちらから



