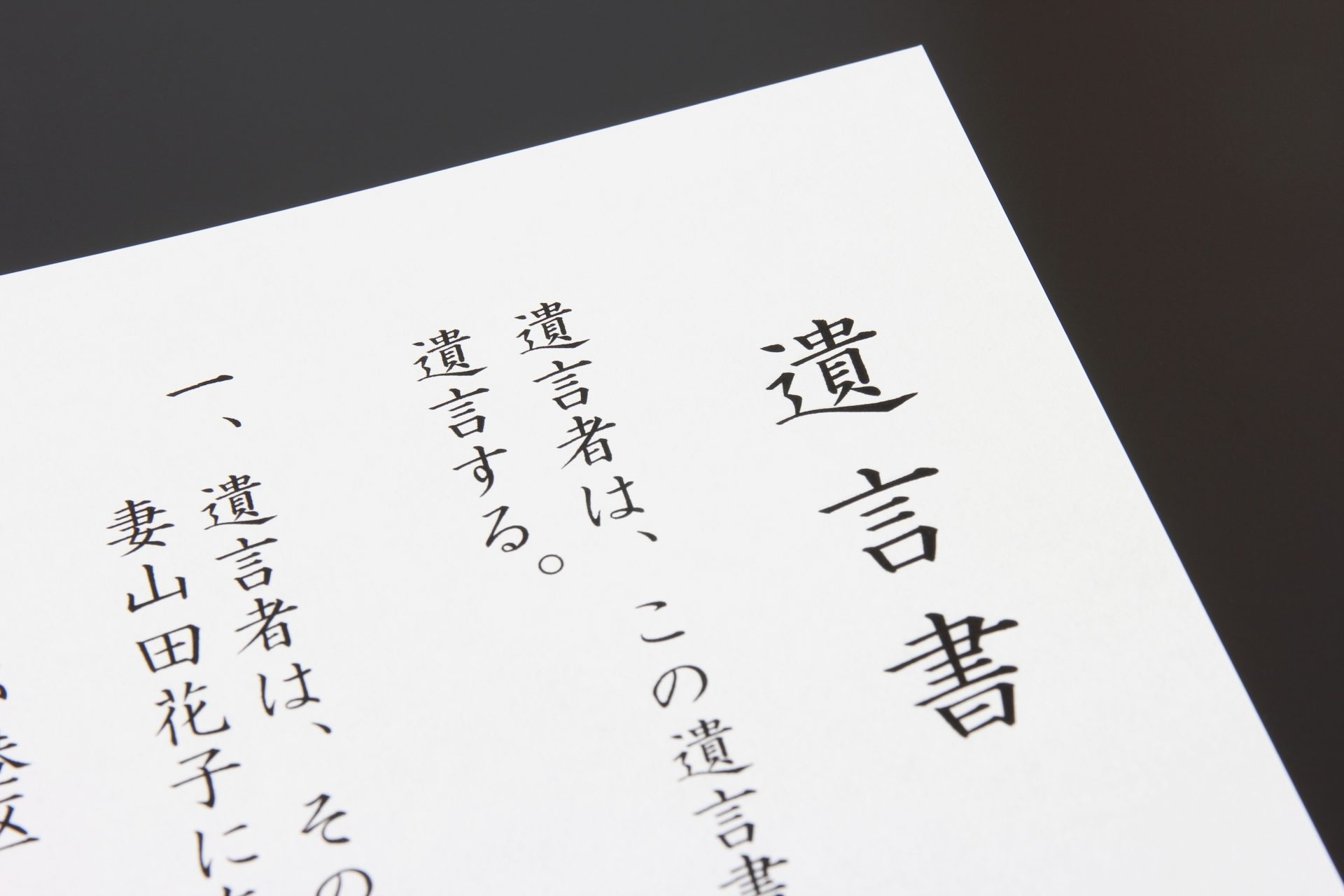東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日、東京司法書士会民法改正対策委員会主催の相続法改正のセミナーがありました。
「Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務」の発刊も兼ねてのセミナーでした。
その中で私が気になった「遺留分」「自筆証書遺言」についての内容をアップします。
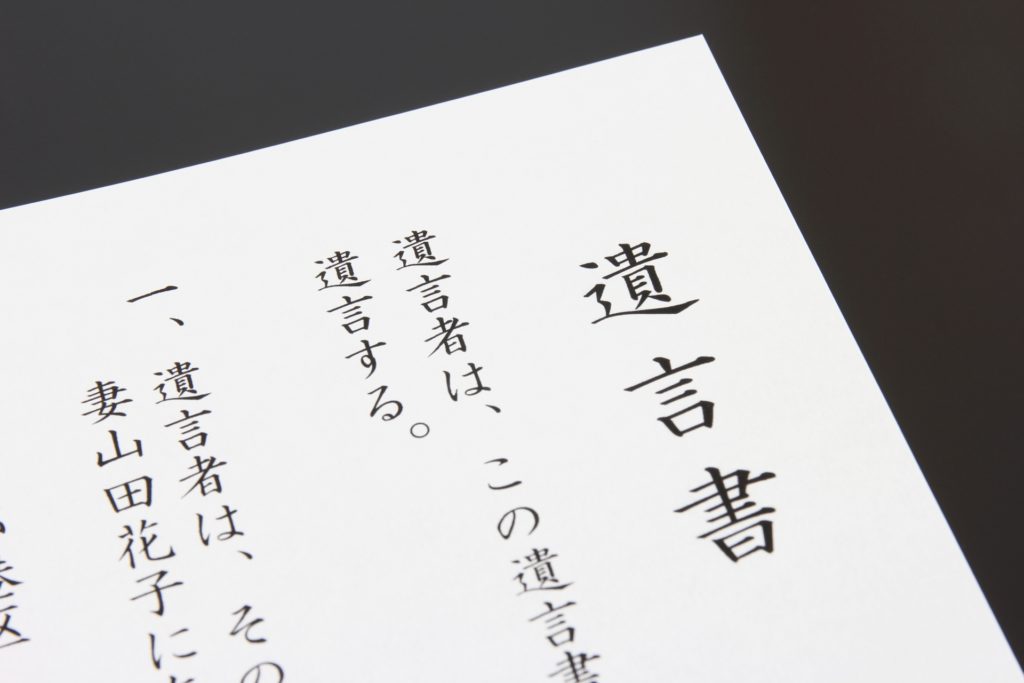
相続法改正のセミナーを受講しての気づき
遺留分制度の見直し 実務でも影響が・・・
遺留分制度については、相続紛争のもとになる制度であるため、廃止をしてほしいと思いましたが、結局は存続することに。
しかし、制度そのものは大きく変わります。
一番大きいのが、遺留分の効力の見直し。
現行制度は遺留分を行使されると、不動産を売却しない限り共有化になったり、自社株の共有化で事業承継がままならないことがありました。
今回の遺留分制度の改正は、時代の流れをくみ、「金銭債権」のみ請求できるところが大きく変わりました。
さらに「相当の期限を許与」されたため、分割払いによる遺留分の支払いも可能となりました。
金銭債権でいいということは事業承継や遺言では効果が大きいです。
つまり、不動産の場合は金銭を借り受け、抵当権を設定することで、遺留分権利者に支払いが可能となり、場合によっては自社株の売却もしないで済むというメリットは大きいです。
あと、遺留分の算定方法の見直しも実務上大きな改正のひとつ。
相続人に対する贈与については、相続開始前10年内のものに限られるため、遺留分対策をしやすくなりました。
遺留分制度については相続法改正で大きく変わり、実務の流れも変わりそうな気がしています。
遺言・事業承継対策で遺留分をどう考えるか、そこが一つの論点に繋がりますね。
自筆証書遺言 訂正する場合は書き直すほうがリスク減
自筆証書遺言はすべて自筆である必要がなくなり、財産に関する部分はパソコンやコピーなどで対応できるようになりました。
しかし、財産部分以外の主要な部分については自筆で書かないといけないのでハードルが高いです。
自筆と自筆によらないものを同一のページにすることができません。
例えば、「左記不動産を〇〇に相続させる」と自筆で記載し、同じページに不動産の表示をパソコンで作成したり、不動産全部事項証明書の余白部分に「上記不動産を〇〇に相続させる」などは無効になります。
あとは訂正方法を間違えてしまうと、遺言書すべてが無効になるリスクが高まります。
一応訂正方法としては、間違えた部分に二重線を引き、遺言書に押印した同じ印鑑で捺印し、余白に訂正内容を記載します。
これは、法律で決まっているので、それ以外の方法で訂正すると遺言書全体が無効になる可能性があります。
もし間違ったのであれば、再度書き直すべきです。

まとめ
今回のブログのまとめ
・遺留分制度が大きく変わる 事業承継や遺言の際に遺留分権利者にどう対応するかはきちんと考える
・自筆証書遺言で訂正があったら、再度書き直すべき
今回は
『相続法改正のセミナーを受講してきた!遺留分制度と自筆証書遺言の気になるところを整理』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
以前も相続法改正のセミナーを受講したのでその気づきも合わせて御覧ください。
2019年は相続法改正で実務はかなり動きそうな予感です。
参考書籍
 |
Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務 東京司法書士会民法改正対策委員会 日本加除出版 2018年12月12日
|